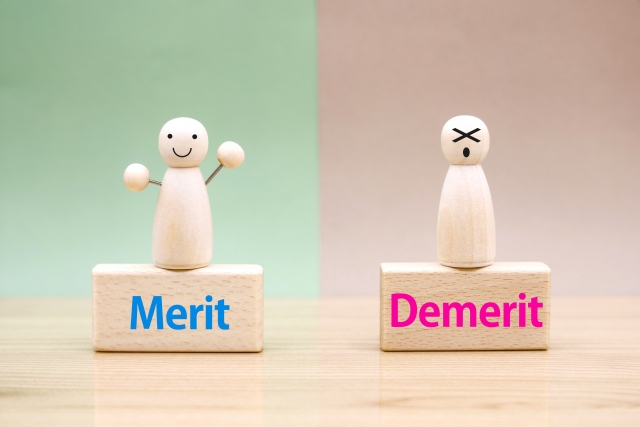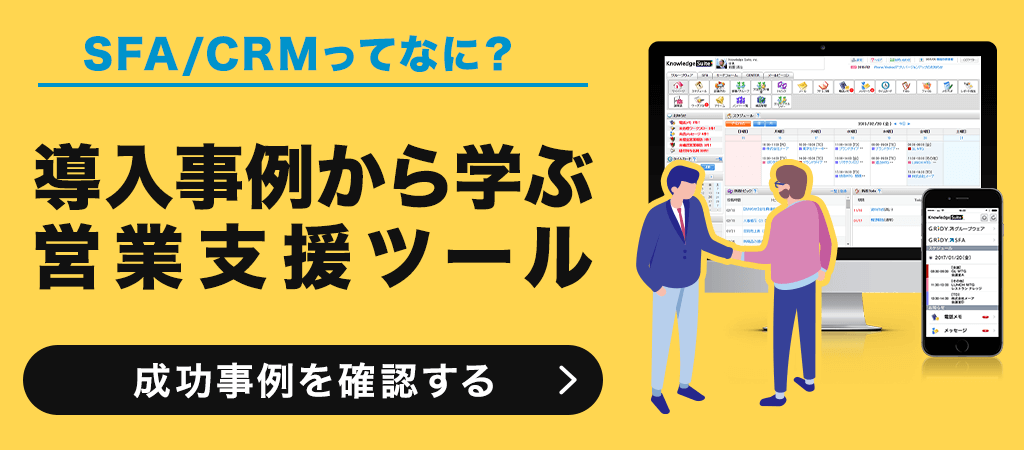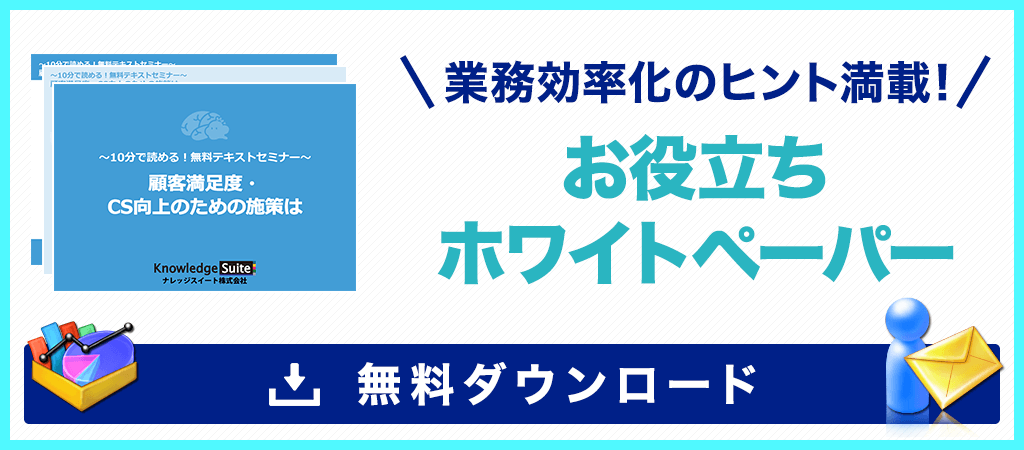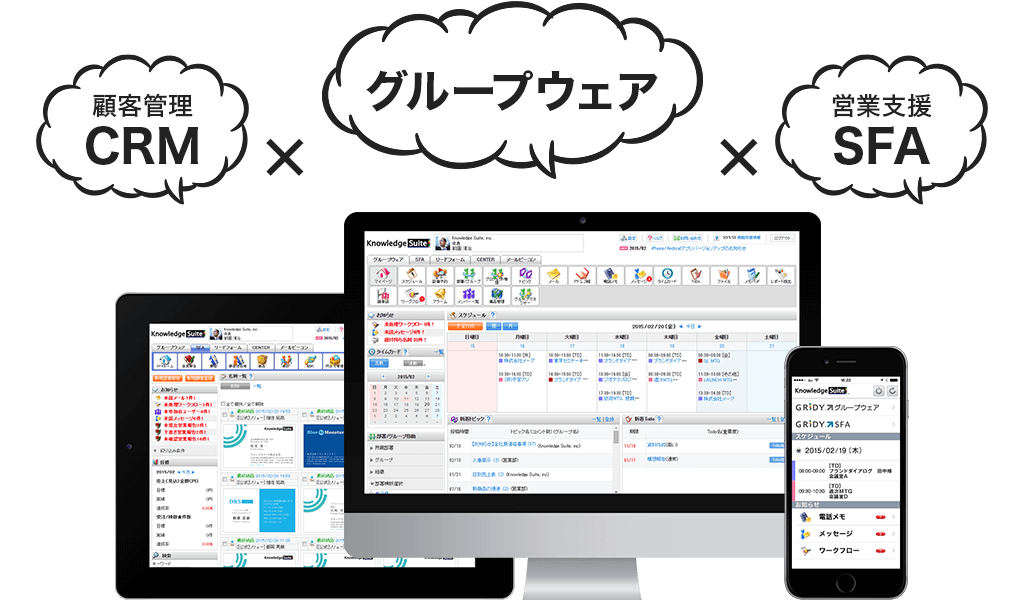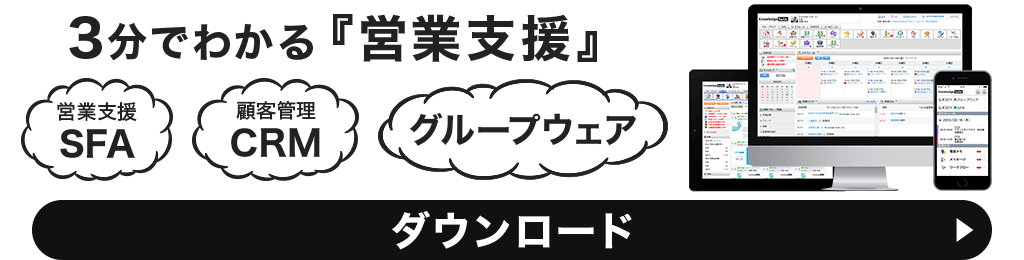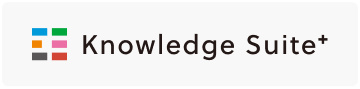PPM分析とは?具体的なやり方や事例を紹介

PPM分析は、複数の事業や製品を市場成長性と自社の競争力の観点から整理し、限られた資源をどこに重点配分すべきかを明確にする戦略フレームワークです。
4つのタイプに分類することで、成長投資を強化すべき領域、収益確保を優先する領域、縮小・撤退を検討する領域を判断しやすくなります。本記事では、PPM分析の概要やメリットに加え、実施時の注意点や企業の活用事例までをわかりやすく解説します。中長期的な成長戦略を検討している経営層や事業責任者の方は、ぜひ参考にしてください。
【この記事の目次】
PPM分析とは何か
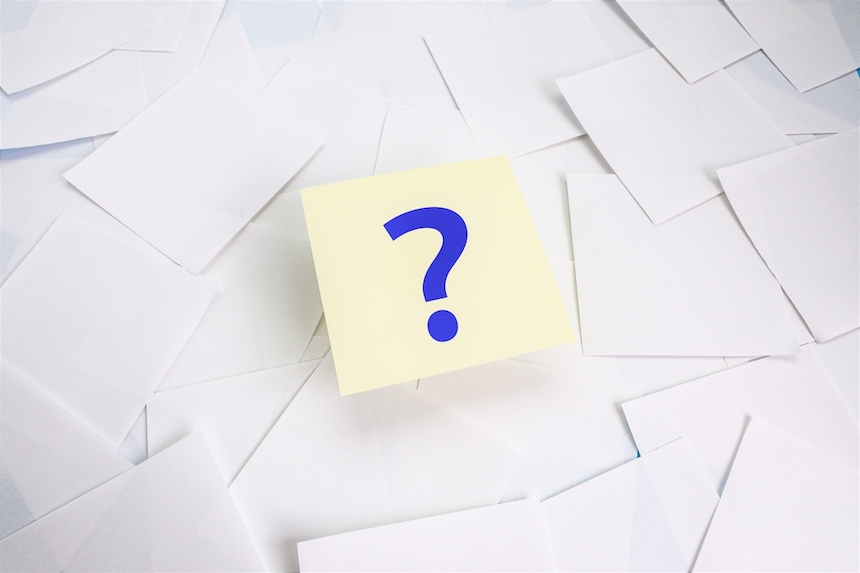
PPM分析は、市場成長率と自社の相対的な市場シェアという2つの指標を用い、事業や製品を4つのカテゴリに分類して経営資源の優先配分先を明確にする手法です。
1970年代にボストン・コンサルティング・グループ(BCG)が提唱し、多角化企業が「投資を強化すべき事業」と「縮小・撤退を検討すべき事業」を迅速に見極めるために利用されてきました。判断を数値ベースで行えるため、意思決定のスピードが上がり、経営陣の合意形成も進めやすくなる点が特徴です。近年では、大企業だけでなく成長段階にあるスタートアップでも活用が広がっています。
目的
PPM分析の目的は、限られた資源を最適な事業に振り分け、企業全体の利益と成長の両立を図ることです。事業を市場成長率とシェアで評価することで、現在の収益源と将来の成長が期待される領域を明確化できます。結果として、短期的な収益確保と中長期的な成長投資のバランスを取りながら、持続的な事業ポートフォリオの構築につなげられます。
歴史
PPM分析は、事業多角化が進むなかで資源配分の判断が複雑化していた1970年代にBCGが開発しました。市場成長率と相対的な市場シェアを軸に事業を評価し、限られた資金や人材をどこに優先投入すべきかを客観的に判断できる仕組みとして誕生したものです。
特に、市場シェアの高さが規模の経済を生みやすく利益率の改善につながるという考え方を背景に、世界中の企業で広く採用されるようになりました。1980年代以降は日本企業にも普及し、現在も基本戦略策定の代表的なフレームワークのひとつとされています。
特徴
PPM分析の最大の特徴は、数値データを基に複数事業の位置づけを一目で可視化できる点です。市場成長率と自社シェアを2軸にマッピングすることで、投資強化、維持、再検討、撤退といった方針が直感的に把握できます。
また、グラフを用いることで経営陣や関係部門の共通理解が得やすく、主観に依存しない議論が進めやすくなります。定期的に活用することで、市場の変化やシェアの推移を追跡し、戦略を柔軟に修正できるのも大きな利点です。
PPM分析の3つのフレームワーク

ここでは、PPM分析を構成する主要なフレームワークについて概要を示し、それぞれの特徴や活用ポイントを整理します。
2つの評価軸:市場成長率と市場占有率
PPM分析では、事業の成長可能性と自社の競争力を見極めるために、「市場成長率」と「市場シェア」の2つの指標を用います。
- ・市場成長率:市場の拡大スピードを示し、将来の投資価値を判断する基準
- ・市場シェア:競合に対する自社の占有率を示し、収益性や競争力を測る指標
この2軸を組み合わせることで、単なる売上規模の比較だけでは見えない事業の位置づけを客観的に把握でき、戦略判断の材料として活用できるようになります。
4つのポジションに分類
このマトリクスを用いることで、事業や製品は4つのポジションに分類されます。
| 成長主力事業(花形) | 市場成長率・シェアともに高く、将来の利益拡大が見込める有望領域。 積極投資がカギ。 |
| 収益基盤事業 (金のなる木) | 市場成長率は低いが高いシェアを維持し、安定収益を生み出す領域。 効率化やコスト管理が重要。 |
| 育成事業(問題児) | 市場成長率は高いがシェアが低く、投資強化か撤退かの判断が求められる領域。 戦略次第で花形に成長する可能性あり。 |
| 縮小・撤退候補事業 (負け犬) | 市場成長率・シェアともに低く、長期的な収益化が難しい領域。 撤退や資源再配分の検討対象となる。 |
事業ポジションの変化と最適化
PPM分析の分類は固定的ではなく、市場環境や自社施策によって変動します。理想は「育成事業 → 花形事業 → 金のなる木事業」と成長し、安定収益を確保する流れです。
一方で、競争力低下や市場縮小により負け犬事業へ転落するリスクもあります。定期的なデータ更新と評価見直しを行い、投資・撤退の判断を適切なタイミングで下すことで、事業ポートフォリオの最適化と持続的成長を実現できるでしょう。
PPM分析の実施手順

PPMを行う前に、事業定義とデータ精度をそろえることがポイントです。以下の4ステップを順に進めるとスムーズに分類が完了します。
事業・製品の整理/分析対象の明確化
PPM分析を始める際は、まず分析対象とする事業や製品を明確に定義する必要があります。同一市場内で比較できる単位まで精緻に絞り込まないと、市場占有率の計算が不正確になり、分析結果の信頼性を損ねかねません。
たとえば製品カテゴリやサービスラインごとに、市場範囲や競合との比較対象を共通化することが重要です。信頼性の高い市場データを用い、定義が曖昧にならないよう注意しましょう。このステップをしっかり押さえておくと、後の市場成長率やシェア計算が整合的にでき、PPMマトリクス上の分類精度も向上します。
指標データの収集と数値化
PPM分析を正確に行うには、信頼できるデータの確保が欠かせません。
まず市場規模を推計し、自社と主要競合の販売数量や売上高を収集します。これらのデータを基に、市場成長率と相対的市場シェアを算出します。公開統計、業界団体の発表資料、調査会社のレポートなどを活用し、データの裏付けを強化することが重要です。根拠が不十分な推計値に頼ると、PPMマトリクスの精度が大きく損なわれる恐れがあります。
マトリクスへの配置
市場成長率と市場シェアを算出した後、各事業をPPMマトリクスにマッピングします。縦軸に市場成長率、横軸に市場シェアを置き、4象限に分類することで事業の立ち位置を直感的に把握可能です。
- ・花形:高成長・高シェアで積極投資が必要
- ・金のなる木:低成長・高シェアで安定収益源
- ・問題児:高成長・低シェアで投資か撤退を選択
- ・負け犬:低成長・低シェアで縮小・撤退を検討
これにより、資源配分の優先順位が明確になり、戦略決定を支援できます。
戦略オプションと資源配分計画の策定
PPM分析の結果を踏まえ、各事業に適した戦略オプションを決定します。
「投資拡大」「安定収益の確保」「重点領域の絞り込み」「撤退検討」といった方向性を整理し、次年度の予算計画や人員配置、設備投資に反映させます。複数のシナリオを数値シミュレーションで比較検討することで、限られた経営資源をより効果的に配分できる最適な計画を導きやすくなるでしょう。
PPM分析を実施するメリット

この章では、PPM分析を行うことで得られる主なメリットを4つ紹介します。
資源配分の最適化によるROI向上
PPM分析で事業を分類することで、投資の優先度を明確にできる点が大きな強みです。花形や問題児には重点的に資源を投じ、金のなる木からの収益を次の成長投資に回すことで、全体のROIを高められます。
このような資源配分の最適化は、無駄なコストを削減し投資効果を最大化する手法として、事業ポートフォリオ管理の現場でも広く活用されているでしょう。
事業ポートフォリオの可視化による意思決定の迅速化
PPM分析で各事業を市場成長率とシェアのマトリクスに整理すると、ポートフォリオ全体を一目で把握でき、投資・撤退の判断がしやすくなります。可視化による主な効果は以下の通りです。
- ・認識差の解消:数値データを基準に議論でき、社内の合意形成がスムーズに進む
- ・投資判断の加速:成長有望事業への投資や撤退判断を迅速化できる
- ・リスクの早期発見:事業依存の偏りや低成長領域への過剰投資を可視化できる
実際に導入した企業では、戦略決定までの期間を3〜4割短縮できた事例もあり、スピードと精度の両面で意思決定を強化できるでしょう。
リスク分散による事業ポートフォリオの安定化
PPM分析を活用し、成長段階の異なる事業をバランス良く組み合わせることで、市場変動や需要の急変に対する耐性を高められます。
- ・安定収益の確保:「金のなる木」の収益が不況時の支えとなる
- ・成長投資の余力確保:「問題児」「花形」への再投資で将来成長を狙える
- ・依存リスクの低減:特定事業が低迷しても他事業が補完し全体を安定化
こうした分散構造は、不確実性の高い市場環境で特に有効であり、持続的な成長戦略を支える基盤となるでしょう。
戦略共有の効率化による意思疎通の加速
PPM分析は事業の位置づけを一目で把握できるマトリクスを用いるため、経営層から現場まで共通の理解を持ちやすくなります。
特に多事業展開している企業では、複雑な戦略方針を文章で説明するより、PPMマトリクス1枚を用いた方が素早く共有できます。これにより、部門間の認識のずれや説明にかかる時間を大幅に削減でき、意思決定までのスピードが向上するでしょう。
PPM分析を実施する際の注意点

PPM分析は事業ポートフォリオを整理し、戦略的な資源配分を考える上で有効な手法ですが、使い方を誤るとかえって判断を誤る原因となる場合があります。
分析結果を正しく読み取り、偏った結論に陥らないためには、いくつかの注意点を理解しておくことが重要です。ここでは、特に押さえておきたい4つの落とし穴を紹介します。
分析の前提条件を正しく理解する
PPM分析の精度は、市場規模や成長率などのデータ信頼性に左右されます。推定値や限定情報に基づく分析では誤った判断につながる恐れがあります。また、PPMは現状の市場環境を評価する手法であり、将来の変化や外部要因までは反映できません。
結果だけに依存した戦略は短期的視点に偏るリスクがあります。信頼性の高いデータ収集と、長期的視点を補う他の分析手法の併用が重要でしょう。
定性的要因を無視しないことの重要性
PPM分析は数値データを基に事業を評価するフレームワークですが、数値だけでは実態を十分に反映できない場合があります。ブランドの認知度や技術力の優位性、顧客の信頼度やサービス品質など、定量化が難しい要素が競争力を大きく左右することも少なくありません。
こうした要因を無視すると、分析結果だけで判断した戦略が現場の実情と乖離し、思わぬ失敗につながる恐れがあります。PPM分析を活用する際は、定性的な情報も組み合わせて総合的に評価し、現実に即した戦略を導き出すことが重要です。
不確実性とリスクを踏まえた判断が必要
PPM分析は過去のデータを基に事業の位置づけを評価するため、将来の市場変化や突発的なリスクを十分に織り込めない場合があります。
特に技術革新のスピードが速い業界や規制の影響を受けやすい市場では、現状の分析結果だけで判断すると、予期せぬ変化に対応できず戦略が陳腐化するリスクが高まります。こうした不確実性を考慮するには、PPM分析に加えて複数の将来シナリオを想定した分析や、潜在リスクの影響を評価する手法を併用することが有効です。
これにより、環境変化への対応力を高め、リスクに強い戦略を構築しやすくなります。
定期的な見直しで分析精度を維持する
市場環境は常に変化しており、一度行ったPPM分析の結果も時間の経過とともに現状と合わなくなる可能性があります。
過去のデータだけを基にした判断を続けてしまうと、実際の市場動向とのズレが生じ、誤った投資判断や戦略の遅れに繋がりかねません。こうしたリスクを防ぐには、PPM分析を単発の作業ではなく、継続的なプロセスとして位置づけることが重要です。年次や四半期単位で市場データを更新し、分析結果を定期的に見直すことで、環境変化に素早く対応できる柔軟な経営判断が可能になります。
PPM分析を上手く活用するコツ

PPM分析の効果を十分に引き出すには、いくつかの重要なポイントを押さえておくことが大切です。ここでは、特に実務で意識したい4つのコツを紹介します。
定量データと定性情報を組み合わせて判断する
PPM分析は数値データに基づいた評価が基本ですが、ブランド力や顧客ロイヤルティ、技術的優位性など、数値化しにくい要素も意思決定に大きな影響を与えます。こうした情報はメモ欄や補足資料として記録し、分析結果の検討時に併せて考慮しましょう。
定量と定性を統合することで、より実態に即した戦略判断が可能になります。
定期的なデータ更新で精度を維持する
PPM分析は一度きりの実施では効果が薄れやすいため、継続的なデータ更新が欠かせません。少なくとも半年に一度は市場データや事業の実績値を見直し、ポートフォリオの変化を把握しましょう。こうした定期的なアップデートにより、戦略判断の精度を高め、環境変化に柔軟に対応できる体制を維持できます。
シナリオ分析を取り入れて将来の不確実性に備える
市場成長率や競争環境は変動する可能性が高く、PPM分析の結果が長期的に有効とは限りません。複数のシナリオを想定し、それぞれのケースで事業ポートフォリオがどう変化するかを試算しておきましょう。こうした事前検討により、想定外の環境変化が起きても柔軟に対応できる戦略を構築しやすくなります。
BIツールを活用したリアルタイム可視化
PPM分析をスプレッドシートだけで管理すると、更新や共有に手間がかかり、情報が古くなりやすいのが課題です。BIツールを導入し、マトリクスをダッシュボード上に埋め込むことで、最新データを自動反映させながらリアルタイムに可視化できます。
これにより、意思決定のスピードと精度を高め、変化に強いポートフォリオ管理が実現しやすくなります。
モニタリング体制を整え、改善を繰り返す仕組みを築く
PPM分析は一度実施すれば終わりではなく、継続的に見直すことで真価を発揮します。市場環境や競合状況は刻々と変化するため、定期的な分析を通じて事業ポートフォリオを最新の状態に保つことが欠かせません。そのためには、モニタリング体制を整備し、PDCAサイクルを回す仕組みを組織に根付かせる必要があります。
具体的には、市場データの収集・分析手順を標準化し、定期的な報告会や戦略検討の場を設けることが効果的です。こうした取り組みを継続すれば、環境変化に柔軟に対応しながら、事業ポートフォリオを最適化し続けられるでしょう。
PPM分析とあわせて実施したい他の分析手法

PPM分析だけに頼るのではなく、異なる角度からの分析を組み合わせることで、戦略の精度を大きく向上させられます。ここでは、PPMと併用することで有効性が高まる代表的な分析手法を5つ紹介します。
SWOT分析による戦略補強
自社の内部資源(強み・弱み)と外部環境(市場機会・潜在的脅威)を体系的に洗い出す手法です。PPM分析だけでは示しきれない要因を補完でき、各事業の象限ごとにより具体的な戦略アクションを設計しやすくなります。
たとえば、問題児事業で「強み×機会」を活かせば成長加速の方針を立てやすく、「弱み×脅威」が多い事業は撤退判断を後押しする材料となるでしょう。
PEST分析による外部環境の把握
PEST分析は、政治(Political)・経済(Economic)・社会(Social)・技術(Technological)の4つの観点から、事業に影響を与える外部環境を整理する手法です。PPM分析で分類した各事業に対し、将来的にどのような外部要因が作用するかを把握できます。市場成長率の変化や競争構造のシフトを予測し、投資判断やリスク対策をより精度高く立てられるでしょう。
5フォース分析で競争圧力を可視化する
PPM分析だけでは、事業が長期的に高収益を維持できるか判断しづらい場合があります。そこで有効なのが、業界構造を5つの競争要因から評価する5フォース分析です。
- ・既存競合との競争の激しさ
- ・新規参入のしやすさ
- ・代替品の登場リスク
- ・顧客の交渉力
- ・供給者の交渉力
たとえPPM上で「花形」に位置づけられても、これらの圧力が強ければ収益が維持できない可能性があります。PPMと5フォース分析を併用すれば、より現実的で堅実な戦略判断ができるでしょう。
バリューチェーン分析による価値創出ポイントの特定
バリューチェーン分析とは、企業活動を「調達」「製造」「物流」「販売」「サービス」などの工程に分解し、どのプロセスで価値が生まれているかを明確化する手法です。PPM分析の結果と組み合わせることで、各事業における強みの源泉を把握し、重点投資やコスト削減の優先度を再確認できます。無駄なリソース投下を減らし、利益率を高める戦略設計に役立つでしょう。
バランススコアカードで戦略を見える化
バランススコアカードは、財務・顧客・業務プロセス・学習成長の4つの視点から指標を設定し、企業の戦略実行を数値で管理する手法です。PPM分析で策定した投資・撤退方針を、具体的な行動計画や評価指標に落とし込み、進捗を継続的に把握できます。
これにより、戦略とオペレーションのずれを早期に発見し、迅速な修正が可能となります。
PPM分析の実施例

PPM分析は、事業ごとに最適な戦略を決める「選択と集中」に役立ちます。ある大手日用品メーカーでは、自社事業をPPMマトリクスに分類し、分野ごとに異なる方針を採用していました。家庭用洗剤事業は市場シェアが高く「花形」と位置づけられ、品質改善や新商品開発、積極的なマーケティングで市場トップを維持しています。
一方、医療用合成洗剤事業は「金のなる木」とされ、TCR(Total Cost Reduction)を導入し、発売当初800円だった価格を約300円まで削減。投資回収が難しい市場では、コスト削減重視の戦略が有効だと示されました。このように、PPM分析を活用することで、事業ごとに異なるアプローチで成長と収益の最大化を図れることがわかります。
SFAなら『Knowledge Suite』

自社ポートフォリオをリアルタイムで管理するには、営業現場からの一次情報をスムーズに収集できるSFAツールが欠かせません。ブルーテック株式会社が提供する『Knowledge Suite』は、名刺・顧客・案件情報を一元管理できるクラウド型SFAです。
顧客や営業状況をデータベース化させることで分析の基盤を作成し、売上や市場シェアの最新情報を把握しやすくなり、PPM分析に基づいた戦略判断を迅速に行えるでしょう。
まとめ
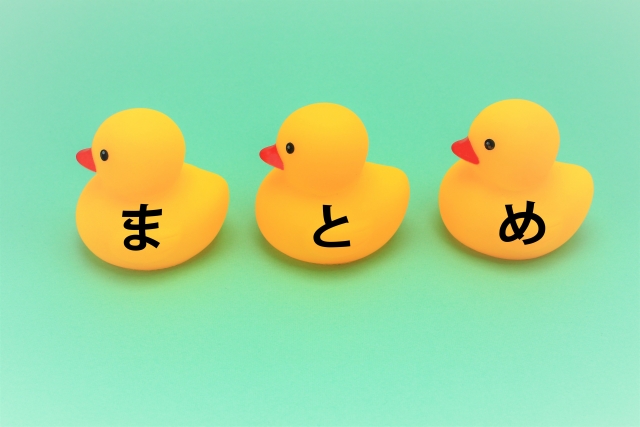
PPM分析は、事業や製品を4つのタイプに分類し、定量データをもとに経営資源の配分を最適化できる代表的な戦略フレームワークです。分析の目的を明確にし、信頼性の高いデータで定期的に見直すことで、事業ポートフォリオのバランスを保ちやすくなります。
さらに、SWOT分析やPEST分析などの他手法を組み合わせ、SFAツールで情報管理を効率化すれば、戦略立案から実行までをスムーズに進められるでしょう。ぜひ本記事の内容を参考に、PPM分析を自社の経営判断に取り入れてみてください。
ユーザー数無制限で利用できるシンプルで使いやすい
SFA/CRMツール Knowledge Suite!
営業活動の効率化と情報共有を一体化におすすめ!
【執筆者】
![]()
松岡 禄大朗
ブルーテック株式会社・デマンドジェネレーション部所属。
前職のWEB広告代理店で広告運用やアクセス解析を担当。
WEBマーケティング知識を活かして、現在はコンテンツマーケティングに携わり数多くの記事を執筆。