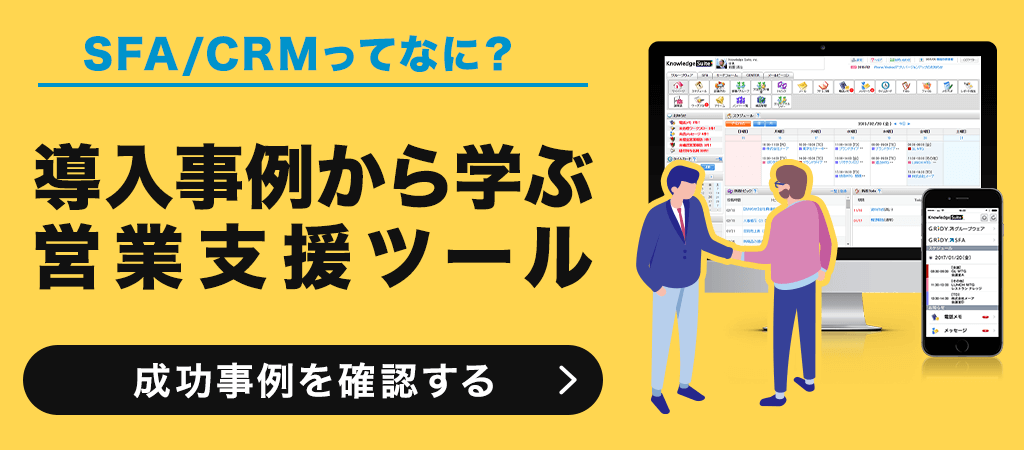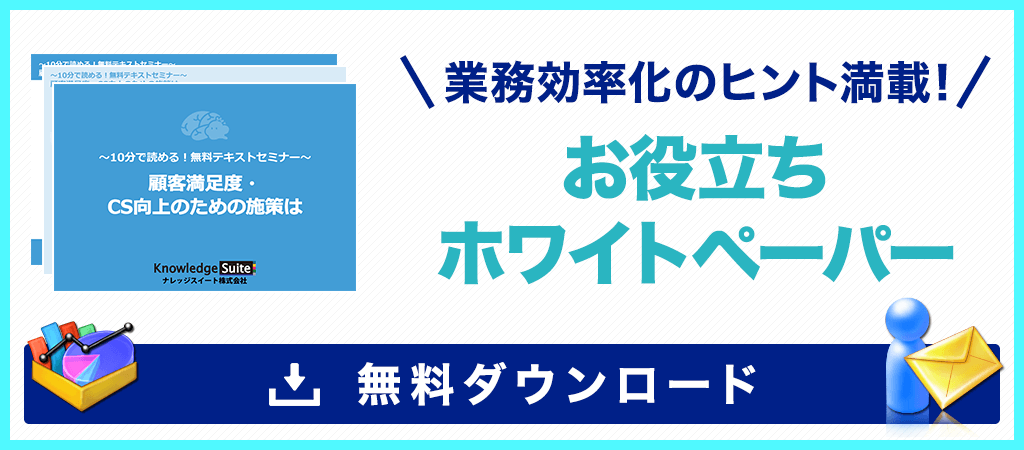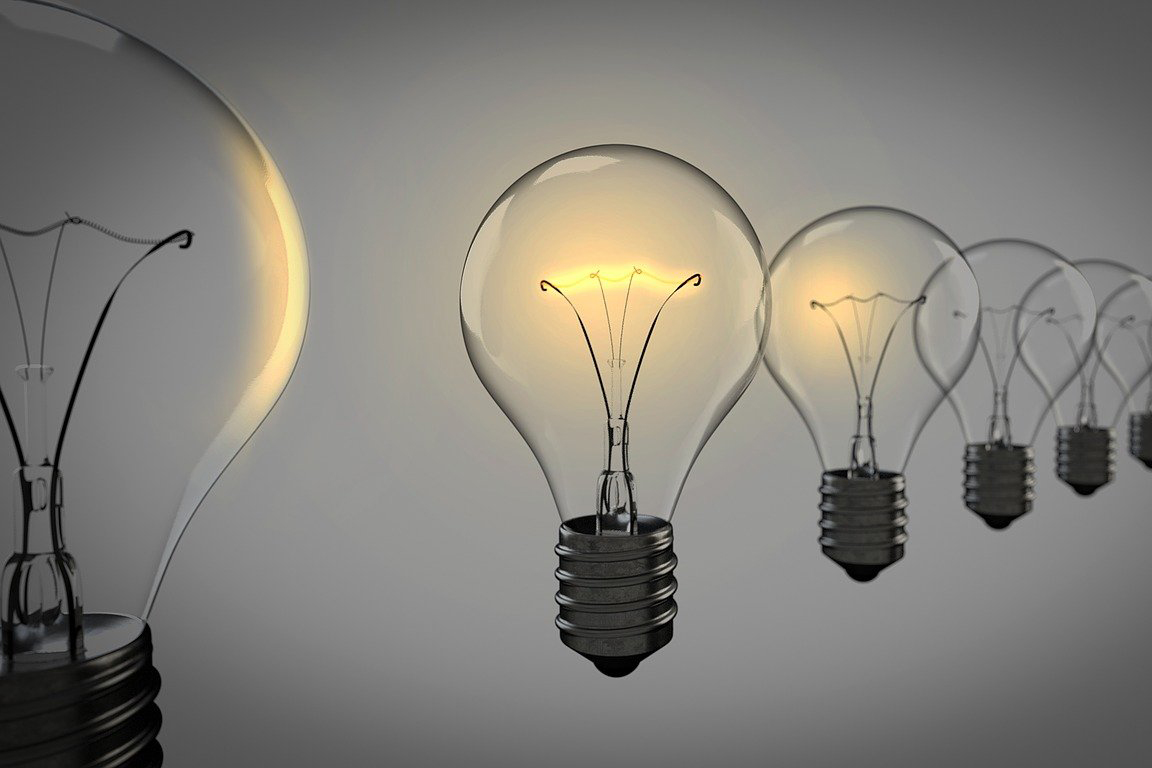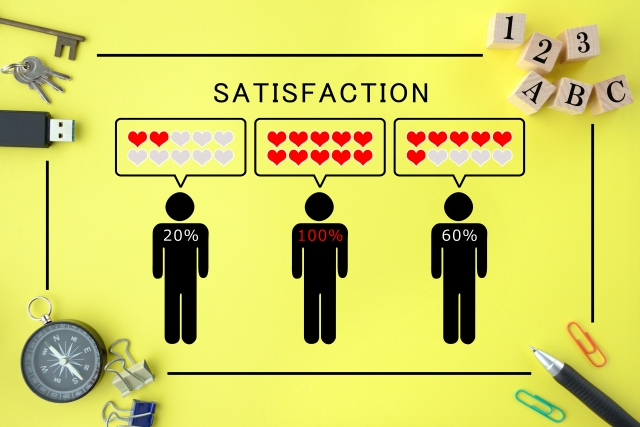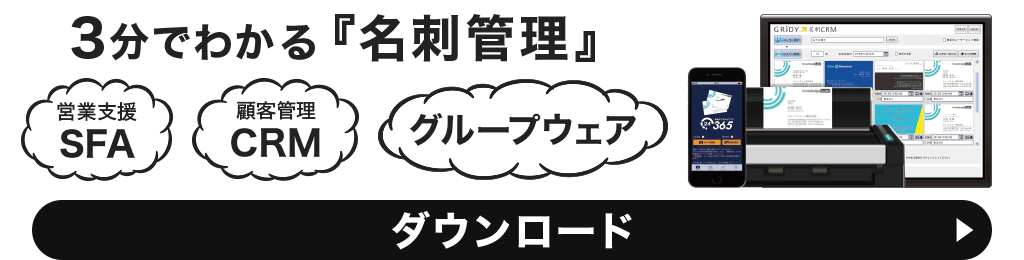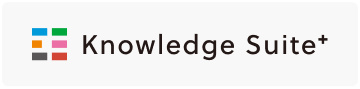CX(カスタマーエクスペリエンス)とは?向上させるコツや成功事例を紹介

CXとは、顧客が商品やサービスを通じて得る体験全体を指す言葉です。この「体験価値」を磨くことで、企業は顧客との信頼関係を深め、結果としてロイヤルティや収益性の向上につながります。
そこで本記事では、CXの定義や重要性、向上によるメリット、具体的な改善手法や成功事例までを詳しく解説します。顧客満足度を高めたいマーケティング担当者や、CX向上に取り組む企業のご担当者様は、ぜひ参考にしてください。
【この記事の目次】
CX(カスタマーエクスペリエンス)とは

CXとは、商品やサービスの利用を通じて顧客が体験する「すべての価値」を意味します。この価値には、価格や性能・使いやすさといった合理的な価値だけでなく、「信頼できる対応だった」「気持ちよく利用できた」といった感情的な価値も含まれます。
たとえば、購入前の問い合わせ対応・サイトや店舗の雰囲気・商品受け取り後の満足感など、顧客と企業が接するあらゆる接点がCXを構成する要素です。CXを高めることで、顧客はその企業に「また利用したい」「人に勧めたい」と感じ、結果として継続的な利用やファン化につながります。
CX(カスタマーエクスペリエンス)が重要な理由

CXが注目されている最大の理由は、感情に響く体験が、顧客の信頼や好感につながるからです。最近では、価格や機能だけでは差別化が難しくなり「どんな体験をしたか」が企業選びの決め手になることが増えています。
たとえば、商品にトラブルがあっても、丁寧で素早い対応をしてもらえたら「またこの会社を使いたい」と感じるものです。逆に、商品自体に問題がなくても、対応が冷たければ印象は悪くなります。このように、人の感情に寄り添う対応や演出があるだけで、継続利用や口コミによる新規顧客の獲得につながり、企業の成長にも好影響をもたらします。
つまり、CXを高めることは「お客様に気持ちよく使ってもらう」だけでなく、売上やファンづくりに直結する、大事な経営戦略のひとつなのです。
感情的な価値とは何か
感情的な価値とは、顧客がサービスや商品を通じて感じる「安心感」「喜び」「驚き」「信頼」など、心に残るポジティブな感情のことを指します。
たとえば金融サービスにおいて、「ATMを探さずにスマホだけで決済できた」という体験は、単なる利便性を超えた「快適さ」や「便利さへの感動」として印象に残ります。これは、顧客自身が明確に意識していなかった潜在ニーズを満たした結果といえるでしょう。こうした体験が積み重なることで、顧客は「また利用したい」と感じるようになり、企業への信頼や愛着(=ロイヤルティ)が深まります。
その結果、リピート利用や口コミによる紹介が生まれ、企業にとっては長期的かつ安定した収益を生み出す原動力となります。
CXを向上させることで得られる3つのメリット

CXを向上させることは、企業にとってさまざまな利点をもたらします。
なかでも注目すべきメリットは、次の3つです。
- ・顧客ロイヤルティの向上
- ・収益性やLTV(顧客生涯価値)の改善
- ・ブランド信頼の獲得と他社との差別化
それぞれのメリットについて詳しく見ていきましょう。
顧客ロイヤルティの向上
優れたCX(顧客体験)は、「この会社だと安心できる」「次もここで買いたい」といった感情を生み出し、価格競争から一歩抜け出す強力な武器となります。
この顧客との感情的な繋がりを測る指標の一つとして、NPS(ネット・プロモーター・スコア)という指標があります。NPSでは、顧客を「推奨者(ファン)」「中立者」「批判者」に分類しますが、CX向上によって「批判者」が「推奨者」に変わると、リピート購入や知人への紹介が活発化し、収益は劇的に改善します。
実際に米国の銀行業界では、NPSスコアの高い企業はそうでない企業に比べ、業績成長率が2倍以上に達したという調査結果もあります。このように、CXを磨き、自社のファンを増やすことは、企業の持続的な成長に不可欠な戦略なのです。
収益性やLTV(顧客生涯価値)の改善
LTV(顧客生涯価値)とは、1人の顧客が企業にもたらす生涯利益のことです。CXを向上させることで単発購入だけでなく、定期利用やアップセル・クロスセルの機会が広がり、結果として収益の厚みが増していきます。
実際、野村総合研究所(NRI)の調査では、「感情的に満足している顧客」は「論理的に納得している顧客」と比べて、収益への貢献度が25〜100%高いことが明らかになっています。このように、CXの改善は単なる満足度の向上にとどまらず、LTVの最大化や安定した収益基盤の構築、さらにはマーケティング投資の最適化にもつながる戦略的な施策といえるでしょう。
ブランド信頼の獲得と他社との差別化
現在、多くの商品やサービスがコモディティ化しており、価格や機能だけでは他社との差別化が難しくなっています。そのなかで、企業が独自の価値を打ち出すためのカギとなるのが「体験価値」です。
たとえば、顧客が「大切に扱ってくれた」と感じた体験は、その企業への信頼を深めるきっかけになり、また利用したいと思われるブランドへと成長する土台になります。実際に、UberやAirbnbのような企業はサービスの透明性やホスピタリティを重視し、体験そのものに価値を見出すことで、競合との差別化に成功しています。
つまり、CXを強化し「ブランドらしさ」を体現することは、顧客の信頼を高めるだけでなく、実際の業績改善にもつながる実効的な戦略なのです。
CX(カスタマーエクスペリエンス)を向上させるコツ

CXの向上には戦略設計も大切ですが、まずは実行可能な具体策を押さえることが肝心です。ここでは、以下の3つの観点から、成功に導くための実践的なコツを紹介します。
- ・顧客理解の深化
- ・社内連携と現場巻き込み
- ・効果測定と改善サイクル
顧客理解の深化
CXを高めるための第一歩は、顧客がどのような経緯や感情でサービスを利用しているのかを深く理解することです。「なぜその行動をとったのか」という視点で分析することで、表面的なニーズだけでなく、本人も気づいていない潜在的なニーズまで見えてきます。
たとえば「ATMの場所がわからない」といった悩みの裏には、「そもそもATMを探す手間をなくしたい」という本質的なニーズが隠れています。顧客の視点を丁寧に読み解くことが、CX改善の出発点になるのです。
社内連携と現場巻き込み
CXの取り組みは、一部門だけで完結させるのではなく、全社的な連携が必要です。とくに顧客と直接接する現場の社員が、CXの意義を理解し、自らの業務に反映できる状態をつくることがカギとなります。
たとえば、社内の朝会で顧客の声を共有したり、CXに関する指標を評価制度に取り入れたりすることで、社員の意識は自然と高まります。さらに、専門チームを設けて横断的に支援する体制を整えれば、現場レベルでも一貫性のある改善が進みやすくなるでしょう。
効果測定と改善サイクル
CXを一時的な施策で終わらせず継続的な改善を進めるには、測定と振り返りの仕組みが不可欠です。たとえば、顧客に「このサービスを他人に勧めたいか?」を尋ねるNPSを定期的に集めることで、体験の良し悪しを客観的に把握できます。
さらに、アンケート結果や利用ログから課題を見つけ出し、施策を講じたあとに再評価するというサイクルをまわすことで、確実にCXを高めていくことが可能です。こうした地道な積み重ねが、顧客の信頼を育てる土台になっていきます。
CXと似た言葉との違い

CXと混同されやすい概念として、UX(ユーザーエクスペリエンス)やCS(カスタマーサポート)、DX(デジタルトランスフォーメーション)があります。それぞれ似ているようで、焦点の置きどころや対象が異なります。ここからは、これらの言葉の違いについて、具体的に見ていきましょう。
UX(ユーザーエクスペリエンス)とは
UXとは、ユーザーがウェブサイトやアプリなどを利用する際に感じる使いやすさや快適さを指します。
たとえば「アプリの操作が直感的だった」「フォームの入力がスムーズにできた」といった、操作体験や画面設計のわかりやすさなどが評価の対象です。一方CXは、商品の購入・利用・アフターサポートまで、顧客が企業と関わるすべての体験を含む広い概念です。
UXはこのCXの一部にあたり、例えるなら「旅全体がCX」、そのなかの「歩きやすさ」がUXです。
CS(カスタマーサティスファクション)とは
CSは顧客満足度を指し、価格・性能・品質など、合理的要素に対する評価が中心です。「スタッフが丁寧だった」「気持ちよく買い物できた」といった体験全体を通じて、顧客の信頼や愛着を育て、継続利用や紹介につなげることを目的としています。
ただし、CSはあくまで「満足しているかどうか」を測る指標であり、感情的なつながり(ロイヤルティ)までは捉えきれません。そのため、顧客との継続的な関係構築やLTV(顧客生涯価値)の最大化を図るには、体験全体に着目するCXの視点を取り入れることが重要です。
DX(デジタルトランスフォーメーション)との違い
DXとは、デジタル技術を活用し、業務プロセスやビジネスモデルを抜本的に変革する取り組みです。目的は、業務の効率化や新たな収益モデルの創出など、企業の「仕組み」を進化させることにあります。
これに対してCXは、顧客が商品やサービスを通じて得る体験の質に注目し「どのように感じたか」「どんな印象が残ったか」といった感情面の価値を重視します。DXは企業の内側から変革を促す手段であり、CXはその変化を、顧客にとって魅力ある体験として実感させる結果です。両者は補完関係にあり、DXの推進はCX向上を実現するための基盤として機能します。
CX(カスタマーエクスペリエンス)向上の指標NPS

NPSとは「この企業やサービスを他人に勧めたいと思うか?」を0〜10点で尋ね、その結果から【推奨者(9〜10点)】と【批判者(0〜6点)】の割合をもとに算出する指標です。計算式は「推奨者の割合 − 批判者の割合」で表され、スコアは「-100から+100」の範囲で示されます。
CXの成果を数値で把握できるため、多くの企業が指標として導入しており、とくに金融・保険・小売といった「感情価値」が収益に直結する業界では重視されています。スコアが高ければ高いほど、顧客のロイヤルティも強化され、継続利用や口コミによる新規顧客の獲得につながるでしょう。
NPSを調べる方法
NPSの測定は、以下の4ステップで行います。
ステップ①:アンケート設計
「あなたはこの商品・サービスを他人にお勧めしたいですか?」といった設問を用意し、0〜10の11段階で回答してもらいます。必要に応じて自由記述欄を設け、理由や感情も収集します。
ステップ②:分類とスコア計算
回答をもとに、以下のように分類します。
- ・推奨者(9〜10点)
- ・中立者(7〜8点)
- ・批判者(0〜6点)
スコアは「推奨者の割合 - 批判者の割合」で算出され、結果は-100〜+100の数値になります。
ステップ③:結果分析と改善アクション
コメントや数値結果を分析し、批判者の不満点や推奨者の評価ポイントを明確にします。これをもとに、CX向上のための施策を立案・実行していきます。
ステップ④:ビジュアル化と社内共有
結果はグラフやチャートにまとめ、各部署間で積極的に共有します。こうしたデータは、継続的に改善サイクルをまわすうえでの共通言語となり、組織全体のCX意識を高める助けとなります。
CX(カスタマーエクスペリエンス)の向上に成功した事例2選

CXの改善によって企業価値や収益性の向上を実現した好例として、2つの業界から代表的な取り組みを紹介します。それぞれの課題と施策、そして得られた成果を通じて、CXの具体的な効果を見ていきましょう。
関係性重視型金融機関の事例
大手銀行との差別化が難しいなかで、この金融機関は、長期的な信頼関係を築くことを目的に、CXに着目した戦略を打ち出しました。
具体的には、顧客との対話を大切にする「スローバンキング」の考え方を取り入れ、定期的な接点を持つ仕組みを構築。ヨガ教室や地域交流イベントなどを開催し、生活に寄り添った体験を提供することで、顧客との距離を縮めました。また、社員の評価基準には短期的な手数料実績ではなく、顧客とのコミュニケーションの頻度や質を重視する方針を導入し、組織全体でCXに向き合う体制を整えました。
その結果、リーマン・ショック後も業績を堅調に維持し、他行の買収にまで至るなど、顧客ロイヤルティと収益性を両立した優れた事例となっています。
損害保険会社の事例
この損害保険会社では、事故対応への不安が顧客満足度を下げ、継続契約の妨げになっているという課題を抱えていました。そこで、事故受付から夜間にかけての迅速な対応体制を整備し、緊急時にも安心感を提供する仕組みを構築しました。
さらに、ドライブレコーダーの映像を活用して事故の解決方針を視覚的に伝えることで、納得感と透明性を高めています。コールセンターの応対品質向上にも取り組み、高齢者向けの専用デスクを設置するなど、ユーザー層に応じた配慮も強化しました。
こうしたCX向上の取り組みにより、外部評価やCS調査で高評価を獲得。NPSスコアの改善も確認されており、事故対応の信頼性向上が契約更新率の上昇と収益力の強化へとつながった実例です。
CRMなら『Knowledge Suite』

ここまで、CXを向上させる重要性や、そのための具体的な取り組みについて解説してきました。こうした施策を継続的かつ効果的に実現するためには、顧客との接点を一元管理し、日々のコミュニケーションや商談プロセスを見える化できるCRM(顧客関係管理)ツールの活用が不可欠です。
そこで注目したいのが、ブルーテック株式会社が提供するクラウド型CRM・SFA統合ツール『Knowledge Suite(ナレッジスイート)』です。
このツールは、見込み客の情報管理から案件進捗の把握、アフターフォローまで、営業活動全体を一元的に管理できる仕組みを備えています。最大の特長は、SFA(営業支援)とCRMが完全に統合されている点にあり、商談履歴や対応内容がリアルタイムで蓄積されるため、顧客ごとのニーズや行動傾向を精緻に把握することが可能です。
さらに、蓄積されたデータは自動でグラフやチャートに可視化されるため、CXに関する課題を素早く特定し、改善策を立案・実行しやすくなります。このように『Knowledge Suite』は営業活動を効率化するだけでなく、顧客との関係性を深め、CX向上につなげる実践的な基盤となります。CXを戦略的に強化したい企業にとって、有力な選択肢となるでしょう。
まとめ
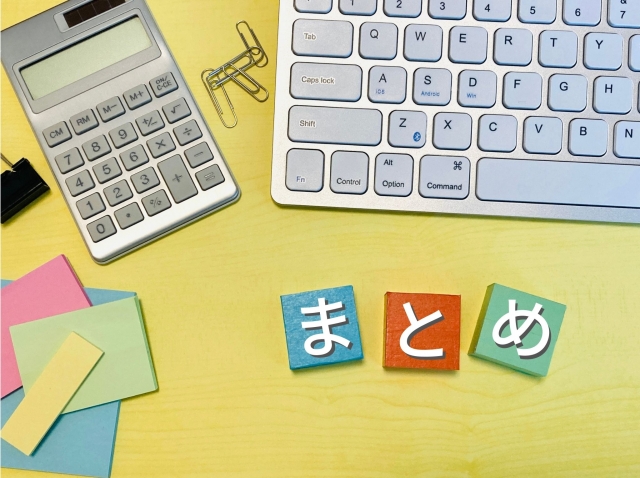
CXとは、顧客にとっての合理的・感情的な価値を含む体験全体を最適化する取り組みであり、ロイヤルティや収益性、ブランド力の向上に直結します。「感情的な価値」をいかに継続的に提供できるかが、他社との差別化と企業成長のカギを握ります。
今回紹介した「メリット」「向上策」「指標(NPS)」「成功事例」を活用し、Knowledge SuiteのようなCRMツールも取り入れることで、御社でも一歩先のCX経営を実現できます。継続的な改善で、顧客と共に成長する体制を築きましょう。
ユーザー数無制限で利用できるシンプルで使いやすいKnowledge Suite!
各種お問い合わせはこちらからお願いします!
【執筆者】
![]()
松岡 禄大朗
ブルーテック株式会社・デマンドジェネレーション部所属。
前職のWEB広告代理店で広告運用やアクセス解析を担当。
WEBマーケティング知識を活かして、現在はコンテンツマーケティングに携わり数多くの記事を執筆。