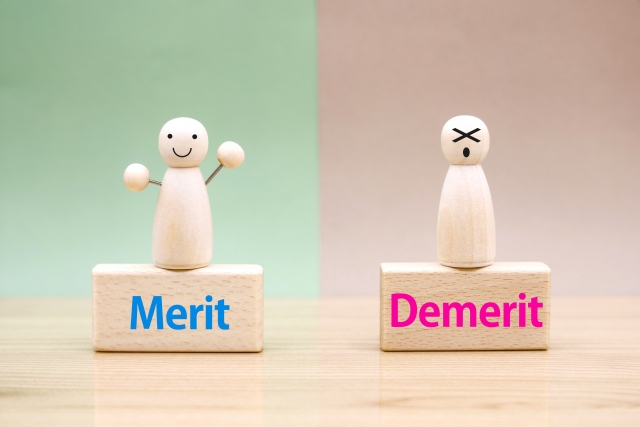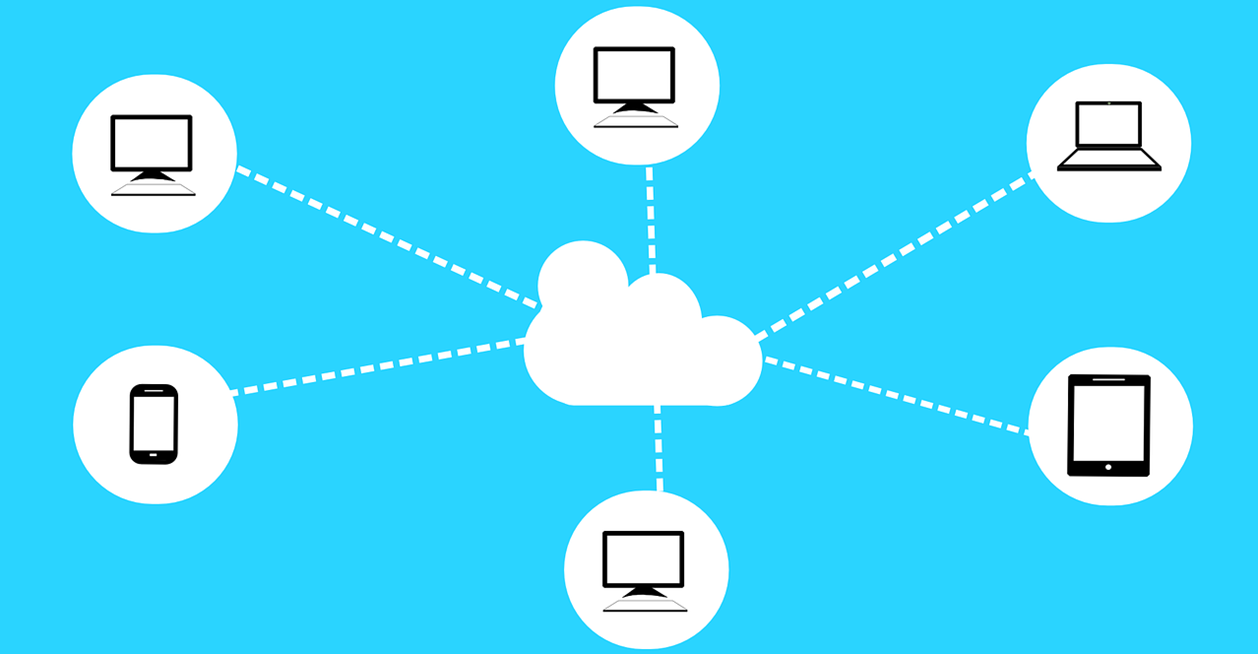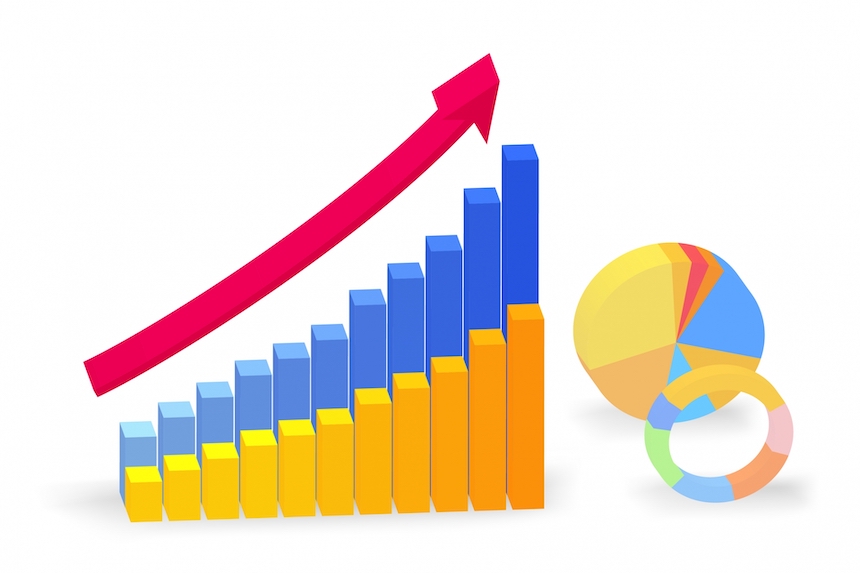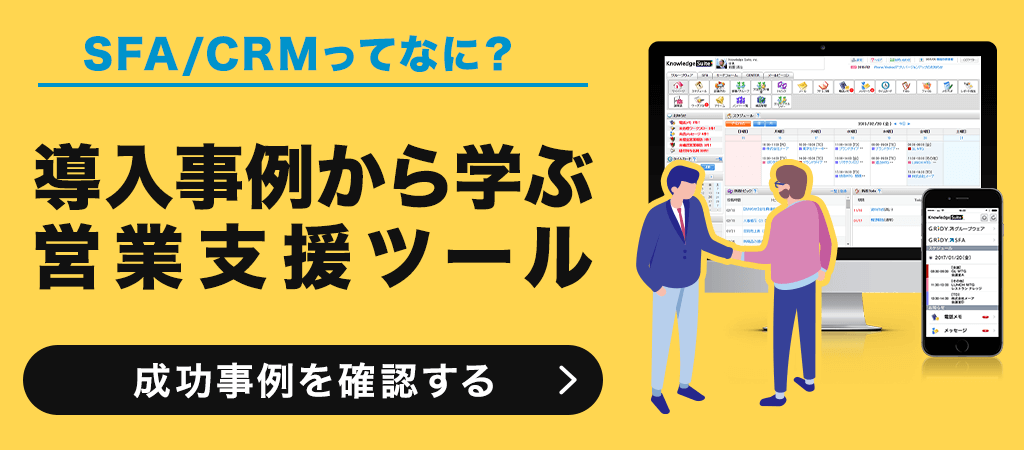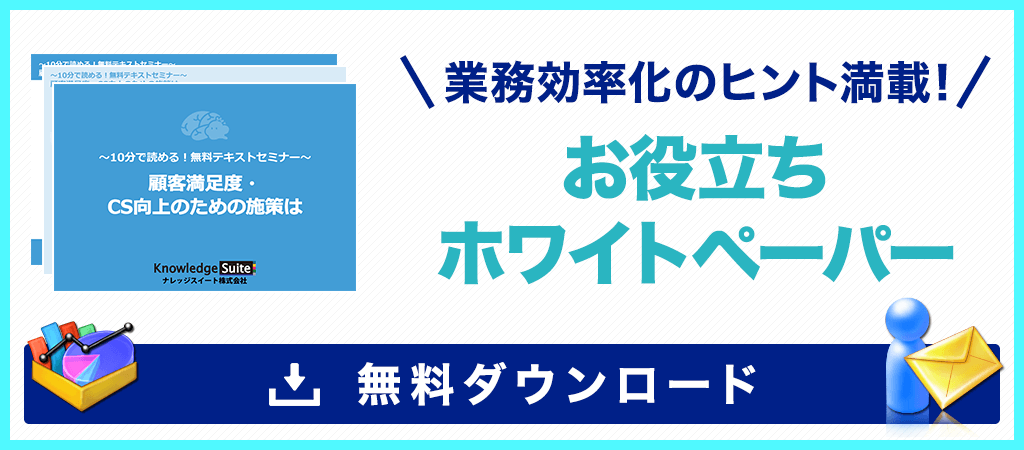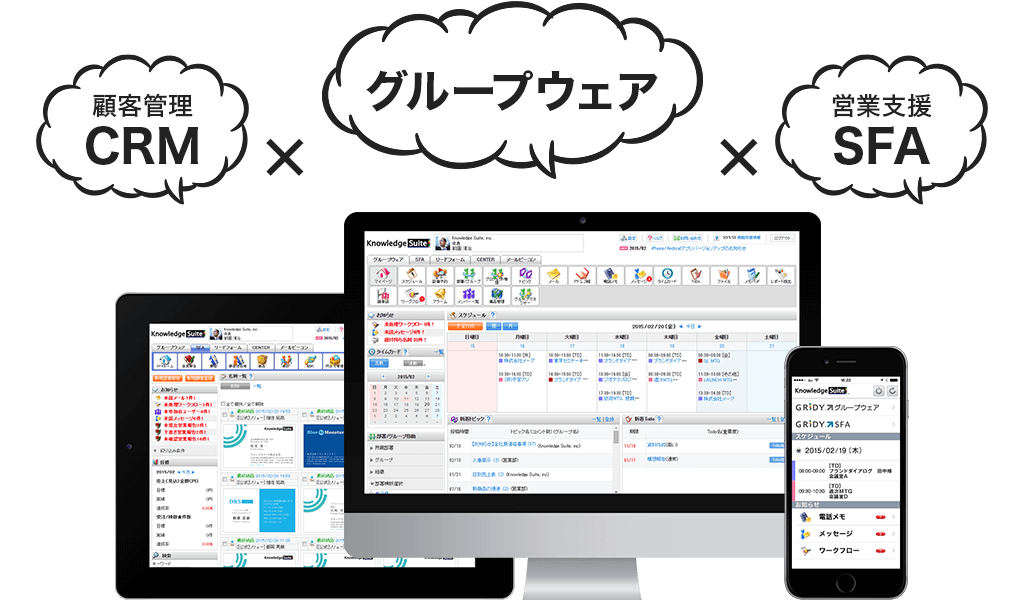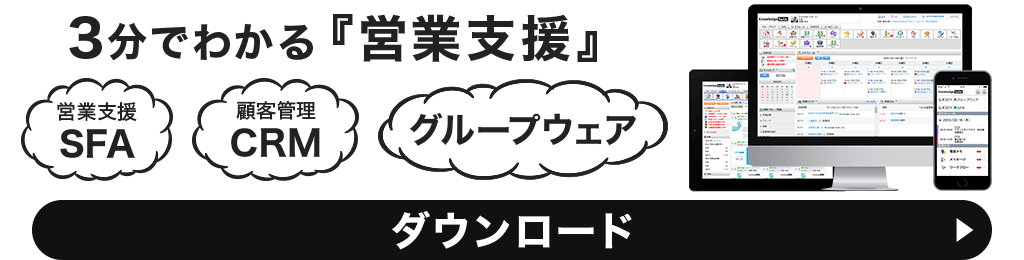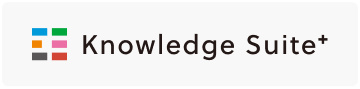セールスイネーブルメントとは何?概念・ツール・取り組み事例を解説

営業組織の生産性や成約率を効率的に高める施策として、近年セールスイネーブルメントへの注目度が一段と上がっています。
そこで本記事では、セールスイネーブルメントの定義やメリット・市場規模の動向・具体的な実施ポイントを整理し解説します。営業力を強化し、組織全体の成果を向上させたい方は、ぜひ参考にしてください。
【この記事の目次】
セールスイネーブルメントとは?

セールスイネーブルメントとは、 何か。まず、言葉を分解して考えてみましょう。セールスイネーブルメント(Sales Enablement)は、「Sales(営業)」と「Enablement(可能にすること)」という2つの単語から成り立っています。
「Enable」とは、「~できるようにする」「可能にする」という意味の動詞です。つまり、セールスイネーブルメントとは、「営業担当者や営業組織が、継続的に成果を上げられる状態にする」という考え方が根底にあります。
これを踏まえて、セールスイネーブルメントとは何かを改めて定義すると。
「営業担当者が成果を最大化できるよう、必要な情報、ツール、トレーニングなどを継続的に提供する、データに基づいた全社的な戦略・仕組み」
と言えるでしょう。
近年のビジネス環境では、顧客ニーズの多様化が進み、営業担当者が扱う情報量が格段に増えています。そのため、セールスイネーブルメントは単なる営業研修といった一時的かつ限定的な規模のものではなく、マーケティングやカスタマーサポートなど部署横断的に連携しながら、様々な手段を講じて営業プロセス全体を最適化します。
セールスイネーブルメントの効果・メリット

先ほども言った通り、セールスイネーブルメントは、営業組織全体のパフォーマンスを継続的に向上させる仕組みを指します。
代表的なセールスイネーブルメントの取り組みとして、トップセールスの知識や成功パターンを組織で共有していくことが挙げられますが、これによって営業組織全体のスキルを標準化することができます。一部のエース営業に依存している組織の場合は、個人への依存から脱却し、新人でも早期に戦力化を図れるようになるでしょう。
また、必要な営業資料やコンテンツの一元管理などもセールスイネーブルメントの一つです。営業担当者は資料作成といったノンコア業務から解放され、顧客への提案活動に集中できるようになるのも、セールスイネーブルメントのメリットの一つと言えるでしょう。
セールスイネーブルメントが注目されている背景

なぜ今、多くの企業が「セールスイネーブルメント」に注目しているのでしょうか。その背景には、企業を取り巻く3つの大きな環境変化があります。これらは、従来の「個人の頑張り」に頼った営業スタイルでは乗り越えられない、構造的な課題を生み出しています。
背景1:営業スタイルの多様化とスキルの属人化
コロナ禍を経て、営業活動は対面だけでなく、オンライン商談やリモート営業が当たり前になりました。これにより、営業担当者には従来のコミュニケーション能力に加え、オンラインツールを使いこなすスキルや、画面越しでも相手のニーズを正確に引き出す高度なヒアリング能力が求められるようになりました。しかし、こうした新しいスキルは個人任せになりがちで、組織内でのレベルの差が拡大。ベテランの暗黙知も共有されにくく、営業スキルの属人化がより深刻な課題となっています。
背景2:顧客の購買プロセスの変化と情報過多
現代の顧客は、営業担当者に会う前に、インターネットで自ら情報を収集し、比較検討を終えていることがほとんどです。そのため、営業担当者には、Webサイトに載っているような単なる製品説明ではなく、「顧客自身も気づいていない課題」を指摘し、最適な解決策を提示する、コンサルタントのような役割が求められます。顧客ごとに異なる状況やニーズを瞬時に理解し、パーソナライズされた価値提供を行うには、個人の知識だけでは限界があるのです。
背景3:ビジネスモデルの変化(The Model型組織の普及)
多くのBtoB企業では、マーケティングが見込み客を獲得し、インサイドセールスが育て、フィールドセールスがクロージングし、カスタマーサクセスが定着を支援するといった、部門横断型の営業プロセス(The Model)が主流になりました。
このモデルで成果を上げるには、各部門が持つ顧客情報をスムーズに連携させ、組織全体で一貫した顧客体験を提供することが不可欠です。しかし、実際には「マーケと営業で顧客の定義が違う」「営業とカスタマーサクセスで情報が共有されていない」といった部門間の分断が大きな障壁となっています。
セールスイネーブルメントの市場について

セールスイネーブルメントの市場は、近年急速に拡大しています。株式会社アイ・ティ・アール(ITR)の報告によれば、2017年度の国内セールス・イネーブルメント・ツール市場の売上は約14億円で、前年度比6.1%の増加を示しました。 その後も市場は成長を続けており、2022年度には約31億円に達すると予測されています。
この成長の背景には、働き方改革やデジタルトランスフォーメーションの推進があり、コンテンツ管理・SFA・カスタマーデータ分析などのツール導入が進んでいます。とくに、外部環境の変化に柔軟に対応できる営業基盤の構築手段として、セールスイネーブルメントの重要性が高まっており、企業規模を問わず多くの分野での活用が見込まれています。
セールスイネーブルメントの実施ポイント

セールスイネーブルメントを実施するには、営業活動の可視化やコンテンツ管理、教育プログラムの整備など様々な要素が関連します。
この章では5つのポイントを解説し、それぞれの進め方を検討し対策を紹介します。
- ・営業プロセスの可視化
- ・コンテンツの管理と最適化
- ・営業担当者の教育とスキルアップ支援
- ・部門間の連携強化
- ・ツールやシステムの継続的な運用体制の構築
営業プロセスの可視化
まず最初のポイントは、営業プロセスの可視化を徹底することです。具体的には、商談開始から成約に至るまでのフローを明確に定義し、どの段階でどのような情報を活用すべきかを整理します。
たとえば商談フェーズごとに使う資料や提案トークを標準化しておけば、担当者間の属人化が防げます。さらにSFAやCRMなどのツールを導入し、案件ステータスを一元管理することが重要です。これにより、各担当者が常に最新の進捗状況を共有しながら次のアクションを検討できます。また管理職は全案件を俯瞰できるため、早期にボトルネックを把握し、必要に応じて人的リソースや追加施策を投入しやすくなります。
コンテンツの管理と最適化
次のポイントは、コンテンツの管理と最適化を実行することです。提案資料やケーススタディ、FAQなど営業活動で用いるコンテンツが散在している状態では、担当者が最新の情報にアクセスしにくくなります。この問題を解決するため、社内ポータルやクラウドストレージを活用してコンテンツを集約し、常にアップデートされたデータを参照できる仕組みが必要です。
また、顧客の反応や利用状況を分析しながらコンテンツを磨き込むことも大切になります。たとえば、ダウンロード数や閲覧時間の長さ、実際の受注率などを指標として活用し、効果の高い資料を優先的に更新する仕組みを整えます。こうした継続的なブラッシュアップによって、営業担当者は顧客ニーズに合った情報を瞬時に提供できるようになり、商談の質を高めやすくなるでしょう。
営業担当者の教育とスキルアップ支援
3つ目のポイントは、営業担当者への教育とスキルアップ支援に力を入れることです。新人研修だけでなく、既存の担当者にも継続的な学習機会を提供しないと、環境変化に対応しきれなくなるおそれがあります。オンライン講習やウェビナー、eラーニングなどを取り入れることで場所を選ばず学習可能にし、最新情報や事例を共有する場を定期的に設定します。
また、外部の専門家を招いてワークショップを開催する方法も有効です。営業トークのロールプレイやマーケティング知識の習得など、部署横断的な視点を取り入れるほど学習効果が高まりやすくなります。さらに、学習成果を定量評価できるように試験やチェックリストを設定すれば、達成度や理解度を可視化できます。
部門間の連携強化
4つ目のポイントは、マーケティング部門やカスタマーサクセス部門との連携を強化することです。マーケティング部門やカスタマーサクセス部門との連携を強化し、顧客獲得から育成、長期的な関係構築まで一貫して取り組む体制を構築します。
具体的には、マーケティングオートメーション(MA)と連携し、見込み顧客の行動履歴を営業が把握できるようにします。また、契約後のアフターサポートや追加提案をカスタマーサクセス部門と協力して進めることで、アップセルやクロスセルの機会を増やすことも可能です。定期的なミーティングや情報共有の仕組みを設け、部署間の目標やKPIをすり合わせることで、効果的な連携が可能になるでしょう。
ツールやシステムの継続的な運用体制の構築
最後のポイントは、導入ツールやシステムを運用し続けるための体制づくりです。セールスイネーブルメント関連のSFA・CRM・コンテンツ管理システムなどを導入しても、定期的なメンテナンスや機能更新を怠ると使い勝手が低下し、現場が活用しなくなる恐れがあります。
そこで、専任担当や運用ガイドラインを用意し、システムの更新内容や活用方法を周知する仕組みを作っておきます。加えて、実際の利用データを分析し、どの機能がどの程度活用されているかを定期的にチェックすることも重要です。利用率が低い機能を放置せず、原因を洗い出して改善する努力が必要になります。
また、導入コストやライセンス費用に見合った効果を得るためには、営業現場からのフィードバックを早い段階で取り入れて柔軟に運用を変えていく姿勢が不可欠です。こうした継続的な運用体制が整ってこそ、セールスイネーブルメントの効果を安定的に発揮できます。
セールスイネーブルメントの取り組み事例2選

ここからは、実際にセールスイネーブルメントを導入し成果を上げている企業事例を紹介します。
異なる業界の事例を取り上げることで、どのような組織でも応用可能なヒントを得られるでしょう。
国内企業の事例
日本国内でも、営業力の強化によって高収益を実現している企業があります。この企業では、営業ノウハウを社内のポータルサイトに集約し、全員が同じ情報を活用できる仕組みを構築しています。営業マネージャーは商談への同行ではなく、どの場面でどのナレッジを活用すべきかを指導するスタイルを採用しました。これにより、属人化を防ぎつつ、誰もが成果を上げやすい営業体制を確立しています。
また、革新的な製品開発にも力を入れており、新商品の多くが市場の先駆けとなるケースが目立ちます。営業戦略と商品力の相乗効果によって、高い利益率を維持しながら、持続的な成長を遂げている企業のひとつです。
海外企業の事例
海外では、営業力の向上に成功している企業がいくつもあります。なかでも、顧客管理システム(CRM)の分野で世界をリードする企業が、営業ナレッジの共有と学習環境の充実に積極的に取り組んでいます。この企業では、社内SNSや営業ポータルを活用し、営業ナレッジを体系的に展開。
さらに、現場で実践されている成功事例を整理し、再現性の高いベストプラクティスとして共有しています。実践的な学習機会を充実させることで、営業担当者が成長し続けられる環境を整備している点が特徴です。このように、ナレッジ共有と教育プログラムを組み合わせた仕組みの構築によって、営業力の均質化とパフォーマンス向上を実現しています。のが効果的です。まずは小さな業務から始めて、成果を見ながら段階的に広げていくことで、リスクを抑えて着実に進められます。
SFAなら『Knowledge Suite』

近年、営業活動の成果を最大化するための新しい考え方として注目されている「セールスイネーブルメント」。このセールスイネーブルメントを現場で実現するには、情報が分断されず、一元的に管理できる仕組みが不可欠です。
そこで私たちブルーテック株式会社がご提供するCRM/SFA『Knowledge Suite(ナレッジスイート)』が、その基盤となります。『Knowledge Suite』は、名刺管理・顧客管理(CRM)、営業支援(SFA)、グループウェアをひとつにまとめた、オールインワン型のクラウド型ビジネスアプリケーションです。
- ・現場主導で使えるシンプルUIだから、ITツールに不慣れな営業担当者も迷わず操作
- ・名刺・案件・メール・スケジュールなどの情報を一元管理&共有できるため、
チーム全体のナレッジ活用がスムーズに - ・ユーザー数無制限、月額5万5千円という圧倒的なコストパフォーマンスで、チーム拡大も柔軟に対応
- ・名刺はオペレーターによる目視補正付きで、精度の高いデータを即座に営業活動へ活かせます
つまり『Knowledge Suite』は、セールスイネーブルメントを「現場から実践できる」ツールなのです。
まとめ
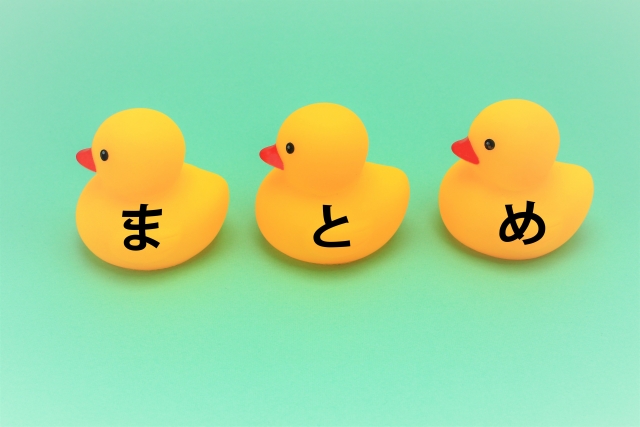
本記事では、セールスイネーブルメントの概要や市場動向、具体的な実施ポイントについて解説しました。セールスイネーブルメントは、営業担当者だけでなく組織全体が適切な情報やツールを共有し、営業成果を最大化するための取り組みです。市場規模は拡大を続けており、業種や企業規模を問わず導入が進んでいます。
実施にあたっては、営業プロセスの可視化や運用体制の確立といったポイントを押さえることが重要です。そこで「Knowledge Suite」のようなSFAを導入することで情報共有を促し、一元的に管理できる仕組みを実現してきましょう。
ユーザー数無制限で利用できるシンプルで使いやすい
SFA/CRMツール Knowledge Suite!
営業活動の効率化と情報共有を一体化におすすめ!
【執筆者】
![]()
松岡 禄大朗
ブルーテック株式会社・デマンドジェネレーション部所属。
前職のWEB広告代理店で広告運用やアクセス解析を担当。
WEBマーケティング知識を活かして、現在はコンテンツマーケティングに携わり数多くの記事を執筆。