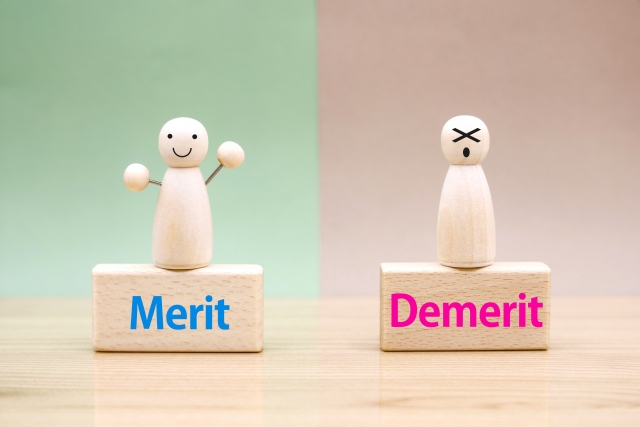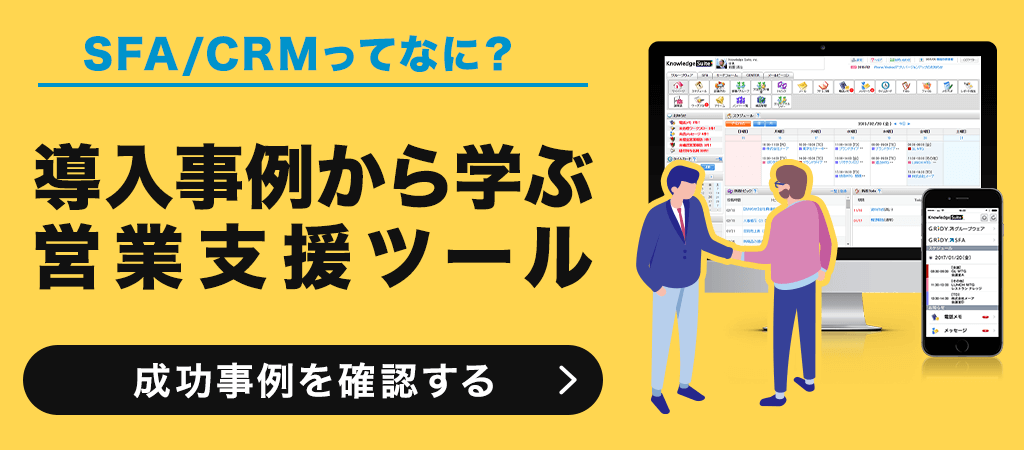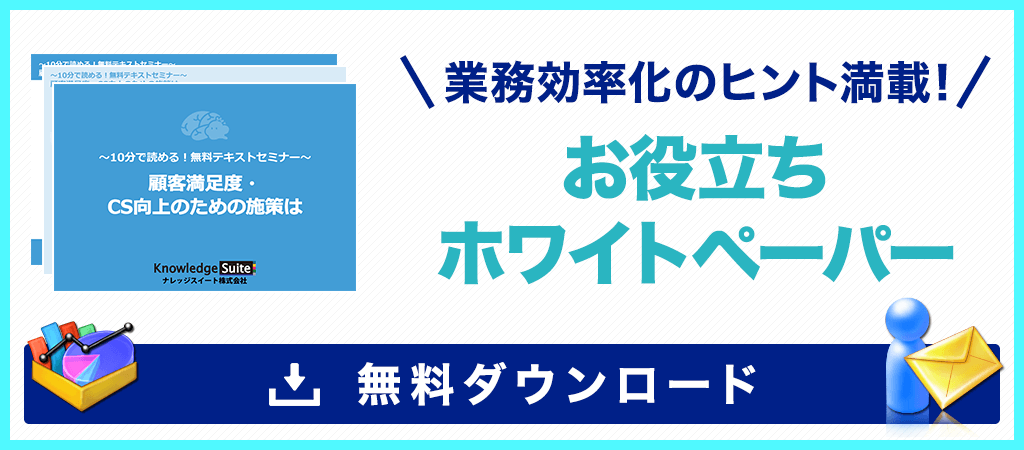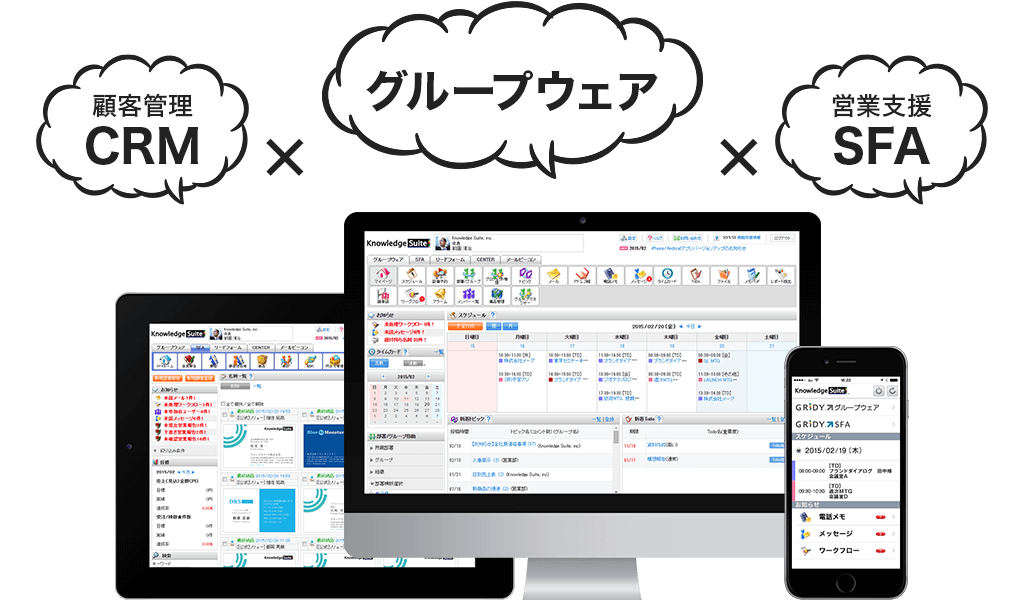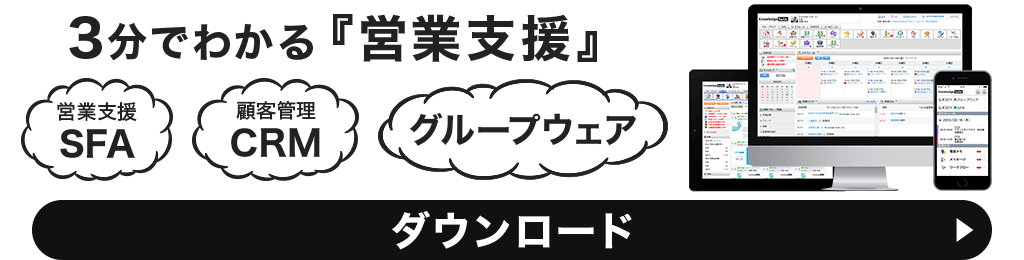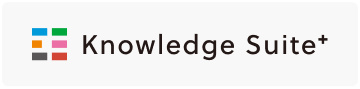webマーケティングとは何?施策や分析の方法

企業や個人が、自社の商品やサービスをオンラインで効果的に届けるためには、戦略的なwebマーケティングが欠かせません。たとえば、SEO対策やSNS運用、メールマーケティングなど、複数の手法を組み合わせて成果を最大化するのが一般的です。近年はオンラインでの消費行動が活発になり、デジタル領域におけるプロモーション力がますます重要視されています。
そこで本記事では、webマーケティングの基礎から施策例・効果測定・実践時のマナーまでをわかりやすく解説します。
「SEOって結局なにから始めればいいの?」
「SNSってただ更新すればいいの?」
「効果測定ってどうやるの?」
こういった今さら聞きにくい疑問も、この記事を通して基礎知識からしっかり身につけて解消していきましょう。
【この記事の目次】
webマーケティングとは何?

webマーケティングとは、インターネット上のメディアやツールを活用して、自社のブランドや商品、サービスを認知拡大から購買・継続利用にまで導く一連の活動を指します。具体的には、自社サイトへの集客やSNSを通じたコミュニケーションなど、多角的な施策によって顧客とつながりを築く点が特徴です。
オフラインに比べ、成果の可視化や運用の柔軟性が高いこともメリットとして挙げられます。
デジタルマーケティングとの違いを比較
webマーケティングは「webサイトやSNSを中心に行う施策」を指すことが多いのに対し、デジタルマーケティングは「あらゆるデジタル技術を活用したマーケティング全般」を含む点が異なります。たとえば、メールやアプリ、デジタルサイネージなど、インターネット以外の電子媒体も含むのがデジタルマーケティングの特徴です。
目的や対象顧客によって、どちらの枠組みを重視するかが変わってきます。
webマーケティングが重要視されている理由

近年はスマートフォンやタブレットの普及により、オンラインで情報収集や購買を行う消費者が急増しています。そうした背景のもと、企業がデジタル領域で存在感を示すことは売上拡大だけでなく、ブランドの信頼獲得にも直結します。
また、オンライン施策はアクセス解析や行動データの取得が容易なため、リアルタイムで効果を可視化して改善を進めやすい点も大きな魅力です。こうした利便性と即時性が評価され、webマーケティングが経営戦略として重要視されるようになっていきました。
webマーケティングの9つの基本施策

リスティング広告(検索連動型広告)
リスティング広告は、GoogleやYahoo!などの検索エンジンで特定のキーワードを検索したユーザーに向けて、検索結果ページの上部などに広告を表示する手法です。ユーザーの検索意図に直接応じて表示されるため、購買意欲の高い層に効率よくアプローチできます。
たとえば「引越し 見積もり」「資料請求 無料」など、明確な目的を持つユーザーに訴求できるのが大きな強みです。クリック課金型(PPC)のため、広告が表示されるだけでは費用が発生せず、運用次第で高い費用対効果も期待できます。
一方で、競合が多いキーワードでは入札単価が高騰する可能性があるため、キーワードの選定や広告文の最適化、定期的なPDCA運用が欠かせません。
SNSマーケティング
SNSマーケティングは、Instagram・X(旧Twitter)・TikTok・Facebookなどのソーシャルメディアを活用して、顧客との接点を作ってファン化や認知拡大を目指す手法です。日々の投稿やストーリーズによる情報発信のほか、キャンペーン・コメント対応・DMでのやりとりなど、双方向のコミュニケーションが強みです。
たとえばアパレルブランドがInstagramでコーデ写真を投稿し、フォロワーの共感を得ることで自然に拡散されるような事例もあります。SNSは拡散力が高く、バズが起きれば一気に注目を集めることも可能ですが、その反面炎上リスクやネガティブな反応にも注意が必要です。
運用方針や投稿ルール、対応フローなどを整えたうえで、継続的に関係性を育てることが成功のカギとなります。
メールマーケティング
メールマーケティングは、見込み客や既存顧客に対して定期的に情報を届ける、ダイレクトなコミュニケーション手法のひとつです。たとえば「新商品発売のお知らせ」や「限定クーポンの配布」などをメールで配信し、開封からクリック、そして購入といった具体的なアクションへと誘導していきます。
とくに、ユーザーの行動履歴や属性に応じて内容を出し分ける「ステップメール」や「セグメント配信」は、高い成果につながりやすい手法として知られています。コストを抑えながら継続的な接点を持てる点は大きな利点ですが、情報の一方通行になりすぎるとスパムと判断されたり、開封率が下がったりする可能性もあるため注意が必要です。件名の工夫や配信タイミングの最適化、読みやすく魅力的なコンテンツ設計など、受け手にとって価値あるメールを届ける姿勢が重要になります。
コンテンツマーケティング
コンテンツマーケティングは、ブログ・動画・PDF資料などを通じて、ユーザーにとって有益な情報を提供することで信頼を築き、最終的な購買や問い合わせにつなげる手法です。
たとえば「業界トレンド解説」や「お悩み解決Q&A」「初心者ガイド」など、読者にとって価値のある知識を発信することで、検索からの流入を増やしながら自社の専門性をアピールできます。とくにBtoB分野ではホワイトペーパーや導入事例集が有効で、リード獲得のきっかけにもなります。コンテンツは資産として蓄積され、SEOとの相乗効果で中長期的に集客を続けることが可能です。
一方で、継続的な更新や質の維持が重要であり、テーマ設定・構成力・ライティング力など複数のスキルが必要です。外注や社内編集体制の整備も成果を左右します。
SNS広告(ターゲティング広告)
SNS広告は、InstagramやFacebook、LINE、X(旧Twitter)などのSNS上に配信する有料広告です。ユーザーの年齢・性別・居住地域・興味関心など、非常に細かいターゲティングが可能で「20代女性・関東在住・旅行好き」など、ニーズにマッチした層へ効率的にアプローチできます。
たとえば、Instagramストーリーズ広告を活用して限定セールを訴求すれば、短期間でのコンバージョンが狙えます。一方で、クリエイティブのクオリティやクリック率が成果に大きく影響するため、定期的なABテストや改善が欠かせません。予算配分・ターゲット設定・配信時間帯など、綿密な設計がROIを左右します。
アフィリエイト広告(成果報酬型広告)
アフィリエイト広告は、他のwebサイトやブログに自社商品・サービスを紹介してもらい、成果(購入・申込・資料請求など)が発生したときに報酬を支払う「成果報酬型」の広告手法です。ASP(アフィリエイトサービスプロバイダー)を経由してパートナーと提携するのが一般的です。
自社ではリーチできない層にもアプローチできる一方、紹介記事の内容を完全にコントロールできないというデメリットもあります。過剰な表現や誤解を招くレビューがブランドイメージに悪影響を与えるリスクがあるため、ガイドラインの整備やモニタリング体制も重要です。
ウェビナー(webセミナー)の開催
ウェビナーとは、ZoomやGoogle Meet、YouTube Liveなどを用いてオンライン上で行うセミナーのことです。参加者は場所を問わず気軽に参加できるため、対面のセミナーよりも集客のハードルが低く、リード獲得や関係構築に活用されています。たとえば、BtoB企業が「業界動向セミナー」を開催し、参加者にホワイトペーパーやサービス資料を提供することで、商談のきっかけを作ることも可能です。
さらに、リアルタイムでの質疑応答やアンケートを通じて、ユーザーの課題やニーズを把握できる点もメリットです。ただし、台本・スライドの準備・進行管理・録画・アーカイブ対応など、運営には事前準備が欠かせません。回を重ねて改善しながら、信頼性のあるブランド体験を提供することが求められます。
LINEマーケティング
LINEマーケティングは、LINE公式アカウントを活用し、ユーザーに直接アプローチできる施策です。メッセージ配信やチャット機能、リッチメニュー、クーポンの提供などを通じて、既存顧客との関係を深めながら購買行動を促します。たとえば、飲食店が「今週限定クーポン」を送ったり、ECサイトが「再入荷のお知らせ」を配信したりと、即時性の高い活用が可能です。開封率や到達率に優れており、メールよりも高い反応が得られるケースも少なくありません。
ただし、頻度や内容によってはユーザーに煩わしさを感じさせ、ブロックされるおそれもあるため注意が必要です。セグメント配信によって個々の関心に応じた情報を届ける工夫や、友だち登録を促すキャンペーンの設計が成功のポイントになります。さらに、CRMと連携すれば、より精度の高いパーソナライズ施策も展開できます。
インフルエンサーマーケティング
インフルエンサーマーケティングは、Instagram・YouTube・TikTokなどで影響力を持つインフルエンサーに、商品やサービスを紹介してもらうプロモーション施策です。特定のジャンルやコミュニティ内で高い信頼を得ている人物を起用することで、広告色を抑えつつ自然な形で商品の魅力を伝えられます。
たとえば、美容系インフルエンサーがスキンケア商品をレビューすることで、同世代のフォロワーに広くリーチできます。ただし、フォロワー数だけに注目するのではなく、エンゲージメント率や投稿の信頼性、過去の案件実績なども含めて慎重に選定することが重要です。
また、案件感が強すぎると逆効果になるため、自然な世界観の中で紹介してもらえるように、企画内容やトーンの擦り合わせも欠かせません。
webマーケティングに必要な準備と手順

webマーケティングを成功に導くためには、施策の目的やターゲットを明確にし、分析と改善を繰り返すサイクルを確立することが重要です。
そのための準備と実行は、以下の8つのステップに沿って進めていきます。
- 1.マーケティングの目的を明確にする
- 2.ターゲット(ペルソナ)を設定する
- 3.顧客の行動や競合をリサーチする
- 4.KPI(重要指標)を設定する
- 5.適切なチャネルと施策を選定する
- 6.コンテンツ・クリエイティブを制作する
- 7.配信・公開・運用を開始する
- 8.効果測定・改善を繰り返す
この章では、上記の各ステップについて、順を追ってわかりやすく解説していきます。
手順1|マーケティングの目的を明確にする
最初に取り組むべきなのは、企業のビジネスゴールや売上目標を踏まえた「マーケティングの目的」を明確にすることです。
たとえば、ブランドの認知拡大・新規リードの獲得・ECサイトの売上向上など、目的は企業によってさまざまです。この目的が曖昧なままだと、最適な施策の選定が難しくなり、プロジェクト全体の方向性がぶれる恐れがあります。
一方で、ゴールが明確になれば、KPIの設定や実行計画の立案もスムーズに進みます。加えて、チーム間の連携や予算配分の判断もしやすくなるでしょう。
手順2|ターゲット(ペルソナ)を設定する
次のステップとして、商品やサービスを利用する見込み客をイメージ化したペルソナを設定します。年齢や性別、職業だけでなく、どんな悩みやニーズを抱えているのかを詳細に想定することが重要です。ペルソナを明確にすることで、メッセージやコンテンツ、広告訴求などが一貫性を保ちやすくなります。
また、ペルソナ設定の段階でユーザーの行動特性を考慮しておくと、最適な媒体選定や配信時間の見極めがスムーズに進みます。
手順3|顧客の行動や競合をリサーチする
ペルソナを設定したあとは、実際の顧客行動や競合の取り組みをリサーチする段階に移ります。GoogleトレンドやSNS検索、競合分析ツールなどを活用すれば、さまざまな視点から情報を得ることが可能です。
たとえば、顧客がどのようなキーワードで情報収集しているのか、競合がどのチャネルに注力しているのかを把握することで、自社にとって有効な施策が見えてきます。こうした市場とのズレを防ぐには、一度きりの調査で終わらせず、継続的なリサーチを習慣化することが欠かせません。
手順4|KPI(重要指標)を設定する
マーケティングの目的やリサーチ結果を踏まえたあとは、KPI(重要指標)を設定する段階に進みます。セッション数やCVR(コンバージョン率)、CPA(顧客獲得単価)などを指標として用いれば、施策の効果を客観的に捉えることが可能です。KPIを明確にしておくことで、施策の進捗を定量的に把握しやすくなり、改善の判断にも役立ちます。
一方で、こうした指標がないまま取り組みを進めると、成果を見失いがちになり、軌道修正のタイミングを逃すおそれもあるでしょう。その結果、時間や予算を非効率に消費するリスクが高まるため、初期段階でのKPI設定が欠かせません。
手順5|適切なチャネルと施策を選定する
KPIが定まったら、目的達成に必要なチャネルと施策を絞り込みます。
SEOやリスティング広告、SNS運用、メールマーケティングなど、webマーケティングには多様な手段があります。予算とターゲット、求める効果を考慮しながら、複数の施策を組み合わせて最適なポートフォリオを構築することがカギです。自社サイトへの流入を増やす施策とリード育成に効果的な施策を連携させるなど、意図的な連動を意識すると相乗効果が期待できます。
手順6|コンテンツ・クリエイティブを制作する
施策とチャネルを選定した後は、実際に発信するコンテンツや広告素材を制作します。記事やランディングページ、バナー画像や動画など、ターゲットが興味を惹かれるようなテーマやデザインを採用することが大切です。ペルソナのニーズを意識しつつ、専門用語を使いすぎずにわかりやすく伝える工夫も必要になります。質の高いコンテンツやクリエイティブは、サイトへの滞在時間やSNSでの拡散率を高めるうえで欠かせません。
手順7|配信・公開・運用を開始する
素材が揃ったら、実際に配信や公開を行い、運用をスタートさせます。
たとえばリスティング広告であれば予算やキーワード入札の設定、SNS投稿であれば曜日と時間帯の選定など、細かい調整を繰り返すことがポイントです。運用開始後は必ずデータのトラッキングを行い、広告のクリック率やコンバージョン率をこまめにチェックします。
初期段階で問題点を見つけた場合は即座に修正し、無駄なコストを抑えることが望まれます。
手順8|効果測定・改善を繰り返す
最後に、実施した施策の効果を数値で確認し、PDCAサイクルを回しながら継続的な改善を図っていきます。アクセス解析や広告レポートなどのデータをもとに、改善点を洗い出し、仮説を立てて次の施策に反映させる流れを構築することが重要です。効果の低かったコンテンツは修正を行い、広告のクリエイティブもテストを重ねて最適化を目指しましょう。
このような改善サイクルを粘り強く続けることが、webマーケティングの成果を積み上げる確かな道となります。
webマーケティングの成功率を挙げるポイント

ポイント1|データを軸に判断する「数字に基づく意思決定」
webマーケティングでは、感覚や経験だけに頼らず、実際のデータに基づいて施策を見直すことが成功への近道です。Googleアナリティクスや広告レポート、ヒートマップなどを使えば、ユーザーの行動や成果指標を客観的に把握できます。
たとえば、直帰率が高いページが見つかれば、導線やコンテンツ内容に課題があると判断できるでしょう。こうした根拠ある分析は、社内での意思決定をスムーズにし、施策の精度向上にもつながります。数字を正しく読み取り、次のアクションに活かす力こそが、継続的な成果を生み出す原動力です。
ポイント2|ユーザーの立場で考える「顧客視点を最優先に」
施策を設計する際に最も重要なのは、「企業が伝えたいこと」ではなく、「ユーザーが求めている情報」を出発点に据える姿勢です。
たとえば、FAQや比較表のようなコンテンツは、疑問や不安を解消しやすく、満足度の向上に直結します。さらに、ユーザーの悩みや目的に寄り添った内容を提供すれば、サイト滞在時間の延長や再訪率の改善にもつながるでしょう。「この情報は本当に役立つのか?」という視点を常に持ちながら進めることで、長く信頼されるブランドへと育てていけます。
ポイント3|やりっぱなしにしない「テストと改善を止めない」
一度作ったLPや広告クリエイティブを放置していませんか?webマーケティングでは、常に仮説を立ててテストし、改善を繰り返す姿勢が成果を左右します。キャッチコピーやボタン配置、色使いなど、ユーザーの反応を引き出す要素は細部に宿ります。
たとえば、ABテストで2パターンの画像を比較するだけでも、CVR(コンバージョン率)が劇的に変わる可能性もあるでしょう。小さな改善の積み重ねが、最終的に大きな成果差を生むのです。
ポイント4|限られた戦力を活かす「社内外リソースの使い分け」
自社の体制やスキルに応じて、何を内製し、何を外注するかを明確にしておくことが、効率的な運用につながります。
たとえば、戦略設計や成果分析は社内で行い、ライティングや広告運用は外部に委託するなど、強みを活かした分業が理想です。すべてを自社で抱えるとスピードが落ち、逆に外注依存だとノウハウが蓄積されません。プロジェクトの内容やリソース状況に合わせて、柔軟な体制を構築しましょう。
ポイント5|一時的な成果で終わらせない「長期視点でブランドを育てる」
短期的なコンバージョンにこだわるだけでなく、ブランドの信頼を積み重ねていく視点も欠かせません。定期的な情報発信や丁寧なコミュニケーションは、顧客との関係性を深め、ファン層の形成につながります。
これにより、自然なリピートや口コミ、紹介が増え、広告費に頼らない安定した集客へとつながっていきます。瞬間的な売上ではなく「選ばれ続ける存在」を目指してマーケティングを設計することが、最終的な成功を支えるカギとなるのです。
ポイント6|モバイルユーザーを意識した「モバイルフレンドリーな設計」
スマートフォン経由のアクセスが主流となった現在、Webサイトをモバイルフレンドリーに設計することは非常に重要です。レスポンシブデザインの採用や読みやすいフォントの設定、指で押しやすいボタンの配置など、スマホでの操作性に配慮することでユーザー体験の質を高められます。
さらに、Googleはモバイル対応を検索順位の評価基準のひとつにしているため、SEOの観点からも対応が求められます。加えて、画像の圧縮や不要なスクリプトの削除によって読み込み速度を最適化すれば、離脱を防ぎ、CV率の改善にもつながるでしょう。
こうした設計の工夫によって、スマホユーザーにとって快適な閲覧環境が整い、最終的な成果の向上にも寄与するはずです。
webマーケティングに必要な能力

分析力
webマーケティングでは、施策の効果を数値で測定し、次の一手に活かす「分析力」が必須です。アクセス解析ツール(Google アナリティクスなど)を使ってユーザーの行動を把握し、滞在時間・離脱率・コンバージョン率などの指標から課題を読み取ります。
また、広告の配信結果や売上データ、SNSの反応なども分析対象です。重要なのは、単にデータを眺めるのではなく、「なぜその数値になったのか」を考え、仮説と改善策を導き出せるかどうかです。分析力が高ければ、無駄な施策を減らし、費用対効果を大きく向上させることが可能になります。
コミュニケーション能力
webマーケターの業務は、単独で完結するものではありません。営業や商品企画、デザインチーム、外部の広告代理店やライターなど、さまざまな関係者と連携しながらプロジェクトを動かしていく必要があります。そのため、情報を正確に伝える力に加え、相手の立場や意図をくみ取る「コミュニケーション能力」が不可欠です。
たとえば、広告運用担当にターゲティングの意図を適切に共有したり、経営層に施策の成果を論理的に報告したりと、状況に応じた対応が求められます。また、意見を調整する役割を担う場面も多く、信頼関係の構築がプロジェクト成功のカギを握ります。
コンテンツ企画力
ユーザーの心をつかむコンテンツを作るには、単なる情報発信では不十分です。市場トレンドやターゲットの興味関心、競合状況を調査したうえで「誰に」「何を」「どのように伝えるか」を設計する企画力が求められます。
たとえば、BtoBでは課題解決型のホワイトペーパー、BtoCでは共感性の高いSNS投稿が効果的です。さらに、見出しや導線設計、視覚的な見せ方までを含めて戦略的に設計できると、成果に直結しやすくなります。コンテンツ企画力は、SEOやSNS運用、メールマーケティングなど多くの施策と連動する、webマーケティングの中核スキルです。
最新トレンドへの対応力
デジタルマーケティングの世界は日進月歩で変化しており、トレンドへの感度と柔軟な対応力が非常に重要です。たとえば、SNSで新たなアルゴリズム変更があった際にはすぐに投稿戦略を見直す必要がありますし、Googleの検索アルゴリズムのアップデートにも継続的に対応しなければなりません。
また、ChatGPTなどの生成AI、ショート動画、ライブ配信など新たな表現手法が登場すれば、いち早く取り入れて試す姿勢が差別化要因になります。情報収集力に加えて「自社にどう活かせるか」を考える応用力があることで、常に一歩先を行くマーケティングが可能になります。
webマーケティングに役立つツール

Google Analytics
1つ目は「Google Analytics」です。
サイトのアクセス数やユーザーの行動経路を可視化し、施策の効果を測定できます。流入元や離脱ページなどを確認することで、改善ポイントを正確に把握できるのがメリットです。導入は基本的に無料で、初心者から上級者まで幅広く利用されています。
参考:https://bow-now.jp/media/column/webmarketing/“
Google Search Console
2つ目は「Google Search Console」です。
主にSEOに特化した解析ツールで、検索キーワードやクローラーの状況、サイトエラー情報などを確認できます。表示回数やクリック数をもとに、検索エンジン対策を行う際の指針を得られる点が特徴です。サイトのメンテナンスや改善に欠かせません。
Microsoft Clarity
3つ目は「Microsoft Clarity」です。
Webサイトにおけるユーザーの行動を可視化することに特化した解析ツールです。ヒートマップやセッションリプレイといった機能があり、ユーザーがサイトのどこに注目し、どのように操作しているかを具体的に把握できます。これにより、コンテンツの改善点や離脱の原因などを特定し、よりユーザーフレンドリーなサイトへと改善を図ることが可能で、データだけでは見えにくい、ユーザー体験を改善できます。Google AnalitycsやGoogle Search Consoleと併用することでより自社サイトの状況を正確に把握できるでしょう。
MAツール(マーケティングオートメーションツール)
4つ目は「MAツール(マーケティングオートメーションツール)」です。
メール配信やスコアリングなど、顧客を自動的に育成・管理できる機能を持ちます。見込み客の行動をトラッキングし、必要なタイミングで適切なアプローチを行うことで、営業効率を大幅に向上させる可能性があります。
SFAツール(営業支援システム
5つ目はSFAツールです。SFAとは見込み客や顧客との商談状況、対応履歴を一元管理できる営業支援システムです。
MAツールやCRMと連携することで、webマーケティングで獲得したリードをスムーズに営業へ引き継げます。属人的な管理を減らし、営業活動の効率化と情報共有を促進する点が大きなメリットです。BtoBマーケティングではとくに重要な役割を果たします。
webマーケティングにおける成功事例

【事例①】サイト刷新とMA活用により新規顧客と設計案件が急増
ある建設関連企業では、新型コロナウイルスの影響により対面営業が難しくなり、案件や受注の減少という課題に直面していました。この状況を受けて、webマーケティングの導入を決断し、Webサイトのリニューアルをはじめ、コンテンツの整備や広告出稿、さらにMAツールを活用したメール配信にも取り組んでいます。
その結果、セッション数は従来の約5.3倍にまで拡大し、コンバージョン数も3倍以上に増加。売上も240%まで伸びるなど、明確な成果が見られるようになりました。なかでも、新規層からの問い合わせが大きく増加し、設計関連の相談件数もおよそ3倍に。Web施策を通じた商談創出が順調に進んでいることがうかがえます。
【事例②】専門商材で成果を出したwebマーケティングによる新規開拓
ある精密機器関連企業では、高額かつ専門性の高い製品を扱っていたため、既存顧客への依存が大きく、新規開拓に課題を抱えていました。紙媒体や展示会による販促にも取り組んでいましたが、継続的な成果にはつながらず、限界を感じていたそうです。そこでwebマーケティングに注力し、CMS導入によるサイト刷新から始めて、自社の強みや技術的なノウハウを発信する体制を整えました。
SEO対策やweb広告に加え、MAツールを活用したメール配信にも取り組み、見込み顧客との関係を継続的に築いています。その結果、CVが268件から622件に増加し、セッション数の伸びと合わせて商談の質も高まりました。
SFAのことなら『Knowledge Suite』

ここまで、webマーケティングについて解説してきました。webマーケティングで継続的に成果を上げるためには、営業活動とマーケティングを連携させることと顧客情報の一元管理、営業プロセスの可視化が重要です。そこでご紹介したいのが、ブルーテック株式会社が提供する統合型ビジネスツール『Knowledge Suite』です。
『Knowledge Suite』は、営業支援(SFA)や顧客管理(CRM)、グループウェアなどの機能をひとつに集約したクラウド型プラットフォームで、営業活動の見える化と情報共有を支援します。顧客とのやり取りを含めた履歴を一元的に管理できるため、担当の引き継ぎ時も混乱が起きにくく、チーム全体で安定した対応が可能となります。
さらに、名刺のデジタル管理やオンラインでの名刺交換機能も備えており、非対面営業にも柔軟に対応可能です。webマーケティングと連動させることで、獲得したリードをスムーズに営業へ引き渡し、商談化の精度を高められる点も大きなメリットです。
まとめ
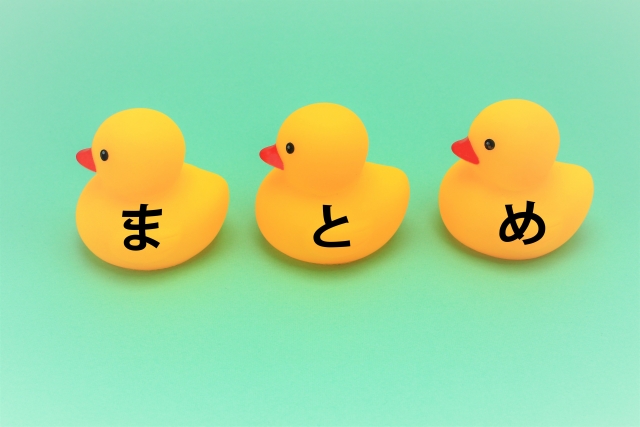
webマーケティングとは、インターネットを通じて顧客との接点を作り、認知・購買・継続利用へと導くための戦略的な取り組みです。SEOやSNS運用など複数の施策を組み合わせることで、見込み客との関係性を深め、成果に直結する動線を構築できます。
さらに、データに基づいた分析と改善を重ねることで、費用対効果を高めながら施策の質を継続的に向上させることが可能です。再現性のあるPDCAサイクルを回す仕組みが整えば、限られたリソースの中でも着実な成果拡大が期待できるでしょう。
デジタルの強みを最大限に活かし、自社にとって最適なwebマーケティング戦略を設計・実行していくことが、これからの時代における成長のカギとなります。
ユーザー数無制限で利用できるシンプルで使いやすい
SFA/CRMツール Knowledge Suite!
営業活動の効率化と情報共有を一体化におすすめ!