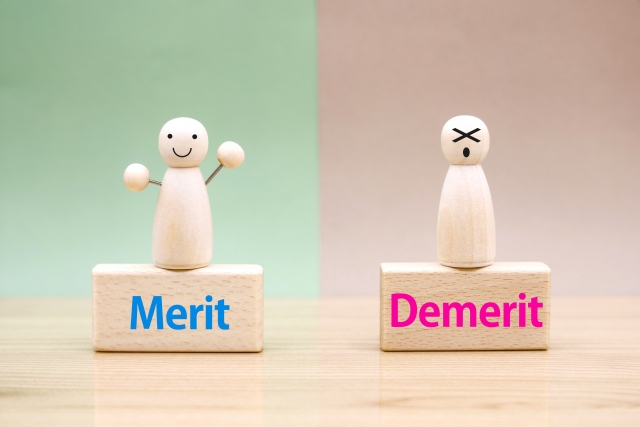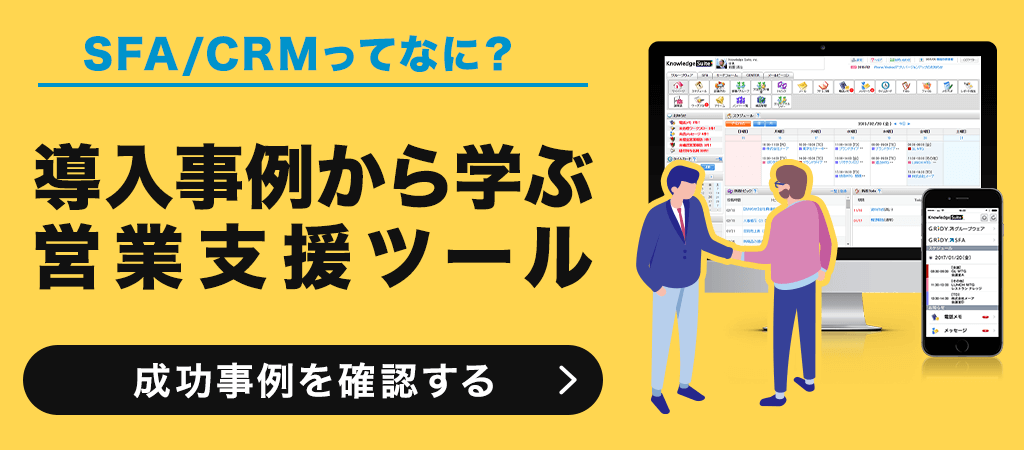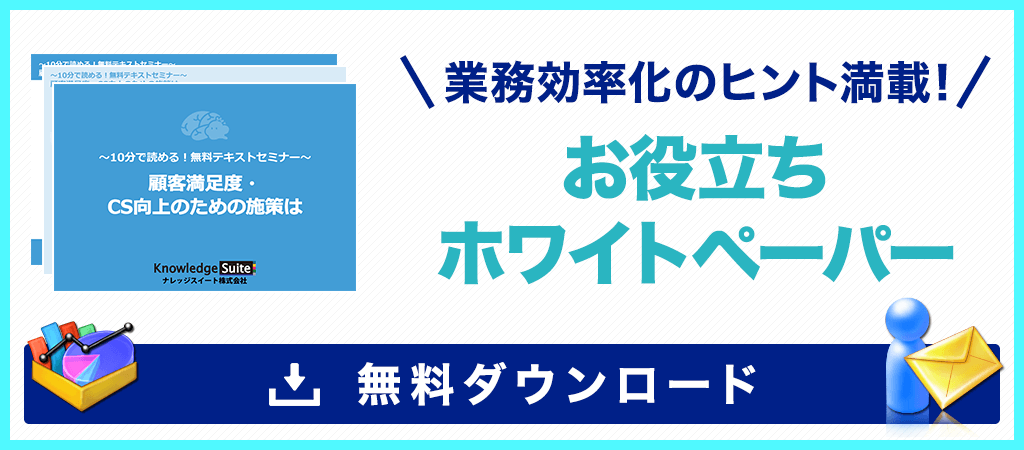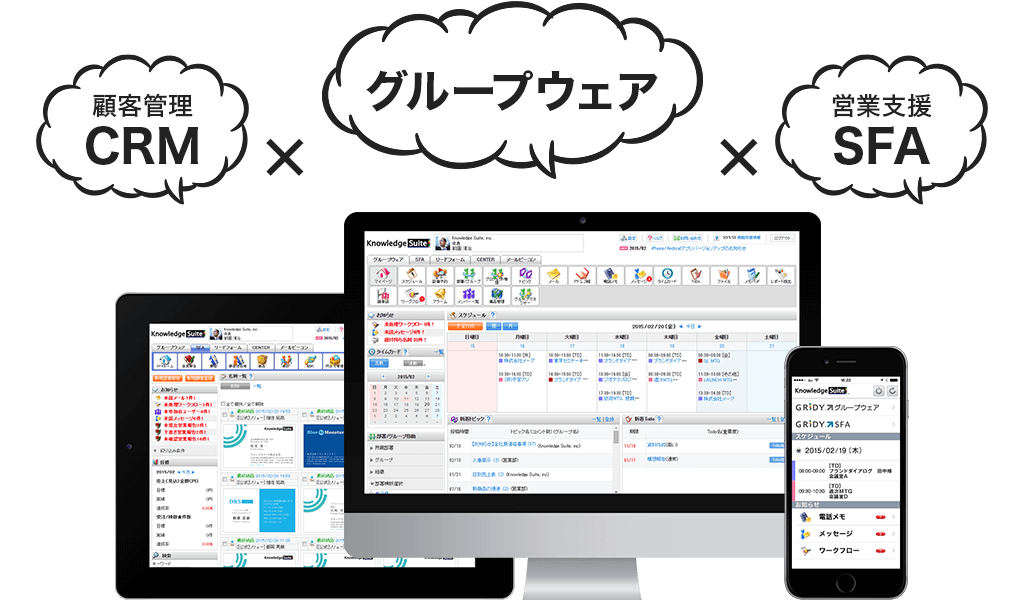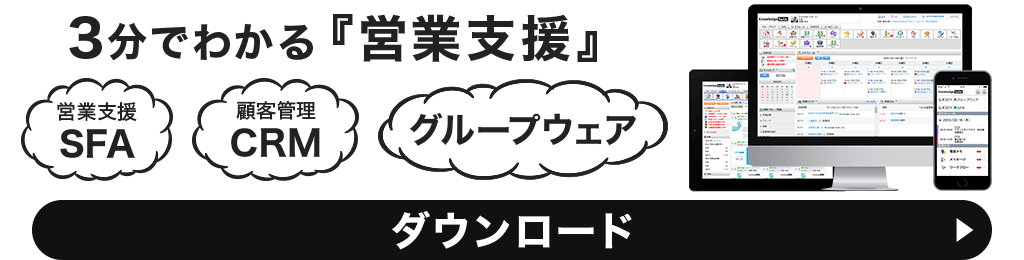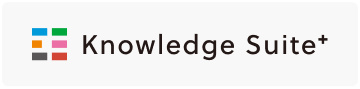PDCAとは?OODAとの違いや古いと言われる理由、成功事例を紹介
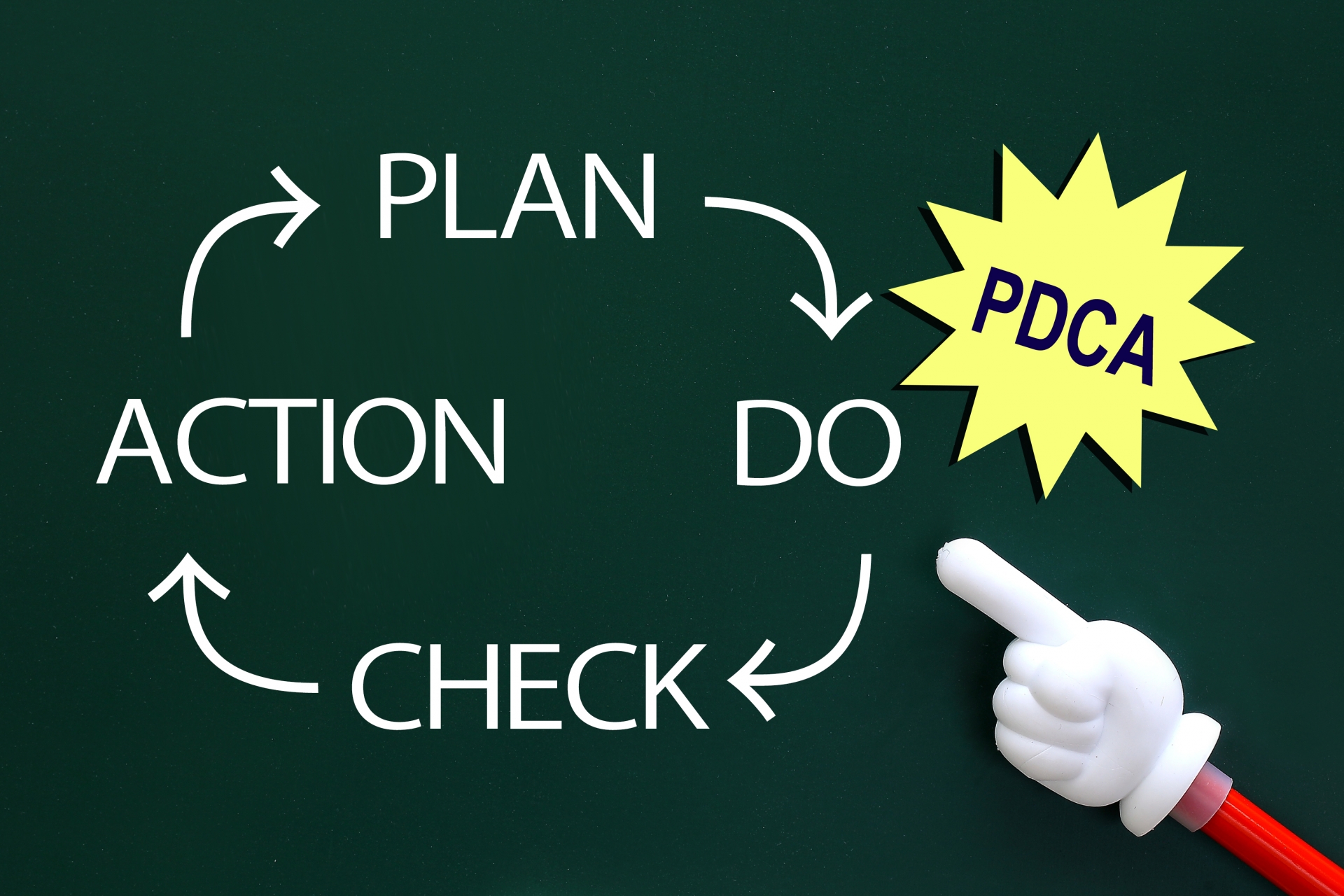
PDCAは、品質向上や業務の効率化を目的に、多くの企業で長く使われてきた改善の仕組みです。しかし、変化のスピードが速い今の時代では「古い」「通用しにくい」といった声も聞かれるようになりました。
そこで注目されているのが、迅速な意思決定を得意とするOODAです。そこで本記事では、PDCAの基本や使い方のポイント、OODAとの違いや成功事例までをわかりやすく解説しています。業務改善や組織力強化のヒントを探している方は、ぜひ参考にしてください。
【この記事の目次】
PDCAとは

PDCAとは「Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Act(改善)」という4段階を繰り返し、継続的な改善を目指す仕組みのことです。
立てた計画を実行し、その結果を確認・評価して課題を見つけ、改善策を実施することで、業務や品質の向上を図ります。もともと製造業の現場で多く活用されてきましたが、現在では医療・教育・サービス業などさまざまな分野で、プロセスマネジメントや業務効率化の手法として幅広く使われています。
PDCAの成り立ち
PDCAの起源は1920年代、ベル研究所に所属していた統計学者ウォルター・シューハート博士が、統計的品質管理の概念を提唱し、管理図や品質改善のサイクルを開発したことに始まります。
その後、弟子のW. E. デミング博士が1940年代にこの手法を体系化し、アメリカで実践を重ねた上で、1950年代に日本へ伝えました。デミング博士は統計学者であり経営コンサルタントとして、日本の品質革命に大きな影響を与え、1951年にはその功績を称える「デミング賞」が創設されています。
PDCAは1950年代以降、日本の品質管理やISO 9001などの国際規格に取り入れられ、企業の業務管理やプロセス改善の標準手法として広まりました。その後、品質管理の第一人者である石川馨氏の品質サークル運動を通じて、「継続的改善=カイゼン」という文化へと発展していったのです。
PDCAサイクルを効果的に回す方法
PDCAサイクルを形だけで終わらせず、実効性を高めるには、以下のポイントを意識しましょう。
- ・目標は数値化・具体化し、期限を明確にする
- ・計画はタスク分解し、担当や期限をはっきりさせる
- ・実行時は進捗や事象を記録し、データを可視化する
- ・評価では数値データをもとに要因分析を徹底する
- ・改善策は論理的に検討し、仮説を立てて次に活かす
- ・小さく高速にサイクルを回し、結果を迅速に反映する
これらを徹底することで、PDCAのサイクルが形だけのものにならず、実際の業務改善や成果につながります。小さな成功を積み重ねる意識が、継続的な成長のカギとなるでしょう。
PDCAの各プロセスにおける内容とポイント

PDCAは「Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Act(改善)」の4つのプロセスにわかれています。
以下では、それぞれのステップで実施すべき内容とポイントを順に解説していきます。
Plan(計画)
最初の段階のPlanでは、まず現状を分析し、解決すべき課題や達成すべき目標を具体的に設定します。目標は数値化し、期限を明確にすることが大切です。その上で、課題の原因を整理し、仮説を立てて改善策を考えます。
さらに、タスクを細分化し、担当者・期限・必要なリソースを決め、実行計画を具体化します。ここでの準備がPDCA全体の精度を左右する重要なポイントです。
Plan(計画)のポイント
Planの段階で意識すべきポイントは以下のとおりです。
- ・現状を定量的・定性的に分析する
- ・KPI・KGIを明確にする
- ・課題を抽出し、ロジックツリーで整理する
- ・5W2Hで「誰が・いつ・どこで・何を」を決定する
- ・メンバーと計画を共有し、妥当性を確認する
- ・スケジュールとタスクの優先順位を設定する
- ・無理のない目標とリスク管理を組み込む
どれかひとつでも欠けると、計画が形だけになり、実行・評価・改善の質が十分に確保できません。これらのポイントを意識し、実現可能で具体的な計画を立てることが、PDCAを成功させる第一歩です。
Do(実行)
Doの段階では、Planのときに立てた計画を実行しながら、プロセスや結果を記録していきます。
小規模な試行から始め、リスクを抑えて実施するのがポイントです。進捗や問題点は日報やチェックリストで可視化し、計画通り進んでいるかを確認します。現場での気づきはその都度記録し、次のCheck(評価)やAct(改善)に活かせるよう意識しましょう。
Do(実行)のポイント
Doの段階で意識すべきポイントは以下のとおりです。
- ・計画で決めたタスクを確実に実行する
- ・到達度や進捗、かかった時間をしっかり記録する
- ・予想外の出来事も詳しく記録する
- ・時間や件数など数値化できる情報を意識する
- ・「大体できた」で終わらせず、最後までやり切る
- ・試行の結果から次に生かせる学びを得る
これらを徹底することでDoの段階が単なる作業で終わらず、今後のプロセスで役立つ大切なデータになります。記録と振り返りを忘れずに進めていきましょう。
Check(評価)
Checkの段階では、Do(実行)で得られた記録やデータをもとに、計画通りに進んだか、目標を達成できたかを客観的に確認します。成功や失敗の要因を分析し、どこに差が生まれたのか理由を探るのがポイントです。
たとえば、KPIダッシュボードや管理図を使って数値を比較することで、課題がどこにあったのかが見えてきます。また「Five Whys」や「特性要因図」といったツールを活用すれば、改善の方向性も整理しやすくなるでしょう。
Check(評価)のポイント
Checkの段階で意識すべきポイントは以下のとおりです。
- ・定量的に目標達成度を評価する
- ・実行とのギャップを明確にする
- ・成功要因・失敗要因を分析する
- ・感想ではなくデータに基づいて検証する
- ・責任追及ではなく原因究明を重視する
- ・Checkの結果を次のActionに確実につなげる
これらを徹底することで、評価が単なる振り返りで終わらず、次の改善に生かせるものとなります。曖昧な判断や感覚だけで評価を進めてしまうと、的確な改善策が立てられず、課題を見逃すことになりかねません。
Act(改善)
Actでは、Check(評価)で見つかった課題をもとに改善策を考え、新たな仮説を立てて次のPlan(計画)に反映し、業務改善や目標達成を図ります。改善策は実行可能で効果を測定できる形にまとめ、次のサイクルに確実につなげることが大切です。
Act(改善)のポイント
Actionの段階で意識すべきポイントは以下のとおりです。
- ・原因ごとに複数の改善案を検討する
- ・改善策の優先順位を明確にする
- ・次回の計画に具体的に反映させる
- ・必要に応じて計画自体を見直す(延期・修正・中止)
- ・改善ごとに仮説を立て、効果の検証方法も決める
- ・チーム全体で共有して理解を浸透させる
これらを徹底することで、Actが次の成果につながる確かな改善プロセスになります。
PDCAを実行する5つのメリット

ここからは、PDCAを実践することで得られる具体的な5つのメリットを見ていきましょう。
目標ややるべきことが明確になること
PDCAを実行することで、目標ややるべきことが数値や言葉で具体的に示され、組織や個人の進むべき方向が明確になります。
たとえば「売上を上げる」ではなく「半年後までに売上を5%向上させる」といった具合に、目標が定量化されるため、何を・いつまでに・どのように取り組むかがはっきりします。タスクや役割分担も具体化されるため、メンバー間で認識のズレが生じにくくなり、チーム全体の動きが揃いやすくなるでしょう。
これにより、迷いや手戻りが減り、計画的に成果を追求できるようになります。
行動に集中しやすくなること
PDCAを実行することで、計画に基づく明確な行動指針と数値目標が示されるため、無駄を省き集中して実行できるようになります。とくにPlanの段階で目標やアクションプランが具体的に決まることで、自分が何をすべきか、組織として何が求められているのかがはっきりします。
こうした明確さは、日々の行動や作業への集中力を高め、生産性の向上にもつながるのです。
課題や改善点が浮き彫りになること
PDCAでは、記録と評価によって問題点や成功要因が「見える化」され、次の改善につながります。たとえばCheck(評価)の段階で「目標に届かなかった要因は何か」「予想外の障壁はどこにあったか」を数値や事実として整理可能です。これは、単なる反省ではなく、原因の特定と再発防止策の検討というアクションにつながります。
さらにDo(実行)の際に記録していたログや日報を振り返ることで、成功のパターン(例:午後に効率が上がった・顧客問い合わせが少なかった等)も明確になるでしょう。
業務効率・品質の改善が図れること
PDCAを繰り返すことで、業務やプロセスの精度と品質が向上します。たとえば、製造現場では不良率の低下、IT部門ではシステムのバグ減少が実証されており、継続的改善の効果が明確です。教育や医療の現場でも、記録や評価を通じて無駄やミスが見える化され、改善策を立てやすくなります。
さらに、PDCAはLean(無駄を省く仕組み)やSix Sigma(品質のばらつきを抑える手法)といった多くの効率化手法の基礎となっており、組織全体の成長を支える仕組みとしても役立ちます。
小さく早く試す文化が醸成されること
PDCAを回す最大の意義は、「小さな改善を素早く繰り返す文化」を組織に根付かせることです。
これはKaizen(改善)の考え方とも重なり、成功体験を早期に得やすく、学びや成果を組織全体で共有できるようになります。従業員も「試す・評価する・改善する」サイクルに関わることで、課題解決力や当事者意識が高まり、柔軟で強い組織に成長していくでしょう。
PDCAを実行する2つのデメリット

PDCAは継続的な改善に役立つ手法ですが、メリットだけでなく注意すべき課題もあります。以下からは、PDCAを実行する際に直面しやすい、2つのデメリットについて見ていきましょう。
スピード感に欠ける
PDCAは計画・実行・評価・改善の各フェーズを順に踏む仕組みのため、変化の激しい環境では対応が遅れるリスクがあります。たとえば、計画に数日かけて原因分析や改善策を練っている間に、市場や競合の動きが先行してしまうこともあるでしょう。
一方、OODAループのような即断即決型フレームワークでは、短時間で判断と行動を繰り返すことで俊敏に対応できます。そのため、PDCAだけを頼りにすると、変化への反応速度で不利になりかねません。
過去の延長線上になりやすいこと
PDCAは過去のデータや実績をもとに計画や改善策を立てる仕組みのため、どうしても「これまでのやり方」を前提とした発想に偏りがちです。
結果として、抜本的な改革や斬新なアイデアが生まれにくくなることがあります。とくに、急激な市場変化やイノベーションが求められる場面では、PDCAの枠組みだけでは限界を感じるケースもあるでしょう。
PDCAが失敗する理由

PDCAは継続的な改善の手法として広く知られていますが、計画の詰めが甘い・形だけのサイクルになっている・評価や改善が十分でない、といった理由で失敗するケースもあります。
ここでは、PDCAがうまく回らない原因を整理し、注意すべきポイントを解説します。
Plan(計画)が失敗する理由
Planが失敗する大きな理由は、計画が現実離れし、実行に移せない内容になってしまうことです。現状分析が不十分なまま目標を立てると、現場の実情とかけ離れ、無理や無駄が生じます。
たとえば「売上を倍増させる」といった高すぎる目標は、計画が形骸化するリスクを高めます。さらに「頑張る」といった曖昧な内容では、行動や責任が不明確となり、実行段階で混乱を招きかねません。失敗を防ぐには、データに基づく現状分析と、数値目標・具体的アクション・担当・期限を明確にした計画を立てることが重要です。
Do(実行)が失敗する理由
Doが失敗するのは、計画の実施が中途半端になり、検証や改善に必要な情報が残らなくなることが大きな原因です。たとえば、計画の意図や目的が現場に十分共有されていないと、メンバーの動きにズレが生じ、統一感のない実行になってしまいます。
また、進捗や結果の記録が不十分だと「何がうまくいき、何が課題だったのか」が見えず、次の改善に生かせません。さらに「大体できたからOK」と途中で手を抜いてしまうと、Check(評価)やAct(改善)の精度が落ち、改善の質も低下します。失敗を防ぐには、計画の意図をしっかり共有し、進捗や結果を記録しながら最後まで確実に実行する姿勢を持つことが重要です。
Check(評価)が失敗する理由
Checkが失敗する主な理由は、記録やデータが不足していて客観的な評価ができず、感覚や印象だけで振り返りを終えてしまうことです。
その結果、問題の本質が見えず、次の改善につながらなくなります。さらに、評価が「誰が悪いのか」という責任追及に偏ると、原因の究明や改善策の検討が進まず、PDCA の本来の目的が失われてしまいます。失敗を防ぐには、データに基づく冷静な分析と、原因の特定・次の行動に結びつく評価を意識することが大切です。
Act(改善)が失敗する理由
Actが失敗する大きな理由は、Check(評価)で特定した原因と結果の因果関係を深く分析しないまま、曖昧な改善策を立ててしまうことです。これでは次のPlan(計画)に具体性や一貫性がなく、場当たり的な計画になりやすくなります。
また、改善策が実行可能か、効果をどう検証するかが不明確なままだと、次のサイクルで同じ失敗を繰り返すリスクが高まります。失敗を防ぐには、原因と改善策のつながりを意識し、現実的かつ検証可能な形で次期計画に落とし込むことが重要です。
PDCAを成功させるコツ

PDCAをしっかりと機能させ、成果につなげるためには、いくつかの成功のポイントを押さえることが大切です。ここからは、PDCAを効果的に回すための具体的なコツを紹介していきます。
目標の「定量化と期限設定」
PDCAを成功させるためには、目標を数字で表し、期限を明確にすることが不可欠です。たとえば「売上を上げる」ではなく「3か月で売上を5%向上させる」と具体的にすることで、進捗や成果を客観的に評価しやすくなります。
さらに、期限を設定することで、実行フェーズでの行動がだらだらと長引くのを防ぎ、計画的に進める意識が高まります。定量的な目標と明確な期限は、Check(評価)やAct(改善)に必要なデータの基準にもなるため、必ず意識しましょう。
小さく高速に回す
PDCAは、一度に大きな成果を狙うのではなく、小さな改善を短いサイクルで繰り返すことで真価を発揮します。
たとえば、週や月単位で小刻みに回すことで、計画や実行のズレを早期に発見し、すぐに修正することが可能です。こうした取り組みは、環境の変化や新たな課題への柔軟な対応を後押しし、着実に成果の積み重ねにつながります。「小さく早く回す」文化は、とくにIT開発やサービス改善のようにスピードと柔軟性が求められる現場で、大きな武器となるでしょう。
記録と振り返りを重視
PDCAを効果的に回すためには、感覚や印象に頼らず、事実に基づいた記録を取ることが欠かせません。進捗や結果を数値・データ・現場の出来事として正確に残しておくと、「なぜうまくいったのか」「どこに問題があったのか」を客観的に振り返ることが可能です。
こうした記録は次の評価や改善の質を高め、場当たり的な対応を防ぐ強力な武器になります。
チームで気づきを共有できる仕組みを作る
PDCAは一人で進めるものではなく、チーム全員で計画・実行・評価・改善に取り組むことが大切です。データや状況を共有し、みんなで意見を出し合えば、学びや気づきが広がり、改善の質も高まります。こうした仕組みを整えることで、チーム全体に前向きな改善意識が根づき、変化に強い組織づくりにつながります。
PDCAを導入した企業の成功事例2選

ここでは、PDCAを導入し、実際に業務改善や成果向上につなげた企業の事例を2つご紹介します。自社でPDCAを進める際のヒントとして、ぜひ参考にしてください。
成功事例①:医療機関の待ち時間改善
ある医療機関では、PDCAサイクルを活用し、電子予診票の導入や予約・動線管理ツールによる業務改善を進めました。
その結果、受付から会計までの院内滞在時間は平均165.6分から154.2分へと短縮され、待ち時間の削減につながりました。とくに眼科では、待ち時間の要因を分析した上で患者の流れを最適化し、診察や処置の待ち時間を大幅に短縮。新患の受付待ち日数も、従来の2〜3か月から3週間程度にまで改善されています。
これらの取り組みにより、患者満足度が向上し、スタッフの業務負担や労働時間も軽減されました。まさにPDCAによる継続的改善の成果が表れた好例です。
成功事例②:製造業(トヨタ・Nike)の継続改善
トヨタとナイキは、PDCA(Kaizen)文化を全社的に根付かせ、継続的な改善を実現した好例です。トヨタでは、全ての社員が現場で改善の提案を行い、PDCAを活用して工程の標準化と不良防止に取り組んでいます。その結果、作業の無駄が減り、生産効率が飛躍的に向上しています。
一方ナイキは、Lean(無駄を省く仕組み)を取り入れ、工場の効率化と社員の主体的改善活動を推進しました。その結果2015年から2021年にかけて、売上と利益の両方で 約1000億ドルから2000億ドルへと倍増を達成しており、LeanやPDCAはその成長を支えた大きな原動力となっています。以上のように、両社ともPDCAを単なる手法に留めず、全社員参加型の改善文化として醸成することで、品質向上・効率化・利益拡大という成果につなげています。
PDCAサイクルが古いと言われる理由とは

PDCAは現在も多くの現場で有効な手法とされていますが、一方で「古い」「時代に合わない」と指摘されることもあります。ここからは、その理由や背景についてわかりやすく解説していきます。
理由①:スピード不足
PDCAは各サイクルを丁寧に進める構造のため、とくに市場変化が激しい環境では反応が遅れることがあります。とくに、OODAループのような即断即決型のフレームワークと比べると、柔軟性に欠ける場面が少なくありません。
たとえば、計画段階で数日以上かけて原因分析や目標設定を行っている間に、市場や競合の状況が変わってしまえば、その計画は実行前に古くなってしまう恐れがあります。つまり、PDCAでは「思考に時間がかかるあまり、現実の変化に遅れを取る」可能性があるのです。
理由②:イノベーションが生まれにくい
PDCAは過去のデータや実績をもとに改善を進める仕組みのため、取り組みがどうしても既存の延長線上にとどまりやすい特徴があります。
その結果、新たな発想や大胆なイノベーションを起こしにくい傾向があります。たとえば、問題解決の際に過去の成功パターンや定石ばかりを参考にすると、新しいアプローチや発想の転換が後回しになりがちです。実際、PDCAは「創造性や革新的思考を抑える恐れがある」と指摘する専門家もいます。
PDCAとOODAの違いとは

PDCAとOODAは、どちらも組織や個人が成果を上げるための思考法・手法ですが、その目的や進め方に大きな違いがあります。PDCAは、計画(Plan)から始まり、実行・評価・改善と順を追って進める「サイクル型」の手法です。主に製造業や医療、サービス業など、安定した環境で、品質向上や業務改善を継続的に進めるのに適しています。
一方、OODAは「観察(Observe)」から始まるのが特徴で、状況を見極め、素早く判断し、行動を起こす「ループ型」の手法です。変化の激しい市場や不確実な状況下で、即断即決が求められる軍事、マーケティング、スタートアップの戦略に向いています。
PDCAはデータや分析を重視し、着実な改善を目指すのに対し、OODAはスピードと柔軟性を優先し、試行錯誤を繰り返しながら適応していくアプローチといえるでしょう。それぞれの特徴や意味を理解し、状況に応じて使い分けることが成果を高めるカギとなります。
PDCAとOODAを上手く使い分ける方法
PDCAとOODAはそれぞれ特性が異なるため、状況に応じて使いわけることで組織の対応力と成果を高めることができます。PDCAは、安定した環境や長期的な業務改善・品質向上を目指す場で有効です。製造や医療のプロセス管理では、データに基づいて計画・検証・改善を重ねるPDCAが大きな力を発揮します。
一方、OODAは変化が激しく予測が難しい環境に強い方法です。スタートアップや災害対応のように即断即決が求められる場面では、観察・判断・行動を素早く回せるOODAのスピードが武器となります。
OODAを導入するメリットとは

ここまでPDCAの特徴や使い方について解説してきましたが、変化の激しい現代では「迅速な意思決定」を求められる場面が増えており、OODA(観察・状況判断・意思決定・行動)が注目を集めています。
では、OODAを導入することで具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか?ここからは、OODA導入のメリットについて順番にわかりやすく解説します。
リアルタイムな対応力の強化
OODAループでは「観察→方向付け→意思決定→実行」のサイクルを高速で回すことで、急激な変化が起きた際にも即座に対応できます。
たとえばサプライチェーンの混乱や市場ニーズの急変といった状況でも、数時間以内に状況把握から行動まで完了させることが可能です。実際に製造業や小売業などの一部企業ではこの手法を活用し、急な需給変動や物流のトラブルに迅速に対応することで、競争優位の確保につなげています。
柔軟性・自由度の高さ
OODAループは、決められた順序に縛られず、必要なステップから始められる自由度の高さが特長です。
たとえば、新市場への参入時にまず「観察」で情報を集め、状況が変わればすぐに「判断」や「行動」に移ることができます。急な環境変化やトラブルにも、その場で優先度を変えて柔軟に対応できるため、変化の激しいIT業界やスタートアップでとくに効果を発揮します。
変化に強い組織になる
OODAループは「観察」を起点に現状を正確に捉え、状況に応じた判断と行動を繰り返すことで、変化に強い組織文化を育みます。実際に需要や顧客ニーズが急に変わる小売業や物流業では、現場のデータをもとに即時に軌道修正することで、売上やサービス品質の維持に成功している事例もあります。
こうした迅速な適応力が、VUCA(変動性・不確実性・複雑性・曖昧性)の時代における競争優位を生む土台になるのです。
OODAのデメリット
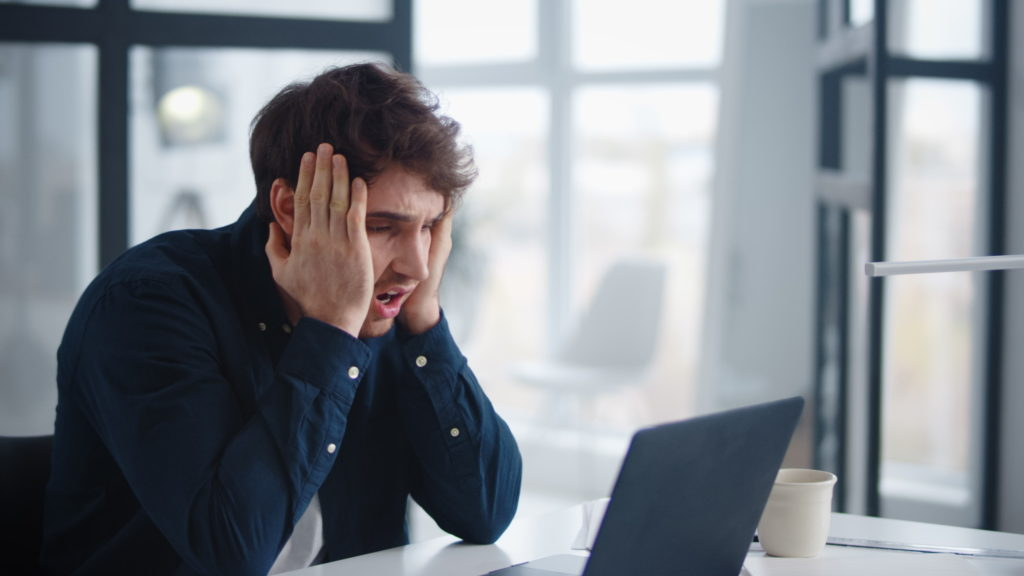
柔軟性やスピードといった利点が多いOODAですが、導入にあたっては注意すべき点もあります。ここからは、OODAを運用する際に起こりやすい課題やデメリットについて見ていきましょう。
計画性が薄れる可能性
OODAは即応性に優れる反面、短期的な判断の積み重ねが中長期戦略との連携を弱めることがあります。
とくに、大規模組織や複数部署をまたぐ業務では、各現場がその場で最適と考えた対応を続けるうちに、全体最適から外れるリスクが高まります。これを防ぐには、OODAでの意思決定の基準をあらかじめ全体戦略と結びつけ、組織として一貫した方向性を維持できる仕組みづくりが重要です。
混乱やリソース浪費の懸念
OODAの強みである迅速な判断・行動が、繰り返されることで現場の負担となり、判断疲れや混乱を招くことがあります。
とくに情報が多く錯綜する状況では、個々の対応が場当たり的になり、全体としての優先順位が見失われ、時間や労力の浪費につながりかねません。これを防ぐには、日頃から意思決定の優先基準や手順を明確化し、現場での判断に一定の統制を持たせることが求められます。
一貫性と成果の継続性が課題
OODAは短期的な状況対応には強いものの、即断即決を重ねるうちに中長期の方針や全体的な成長戦略が後回しになりやすいという課題があります。
その結果、短期的な成果は出せても、持続的な改善や本質的な成長につながらないリスクがあります。これを防ぐには、短期対応のなかでも、OODAの運用を定期的に振り返り、全体戦略やビジョンと照らし合わせる仕組みが必要です。
SFAなら『Knowledge Suite』

ここまで、PDCAとOODAそれぞれの特徴やメリット・デメリットについて解説してきました。最後に、これらを実務でうまく活かしたい企業におすすめのツールとして『Knowledge Suite』をご紹介します。
『Knowledge Suite』は、PDCAの計画・実行・評価・改善を一貫して管理できるだけでなく、OODAの即応力や判断スピードを支える機能も備えたSFA(営業支援)プラットフォームです。目標やKPIの設定・共有、商談や訪問の記録、リアルタイムでの進捗可視化や分析が可能で、計画的な業務改善を着実に支援します。
一方で、外部データを活用した市場・顧客の状況把握、目標未達やトレンド変化時の即時アラートなどにより、変化への迅速な観察・判断・行動も実現可能です。
さらに、ダッシュボードを通じてメンバー間で計画や進捗をリアルタイムで共有でき、PDCA・OODAのどちらのアプローチでも学びや気づきを組織全体で共有しやすい環境が整います。PDCAとOODAを両立させ、計画的な改善と即応的な対応のバランスを取った強い組織を目指すなら、『Knowledge Suite』の導入は非常に有効な選択肢といえるでしょう。
まとめ
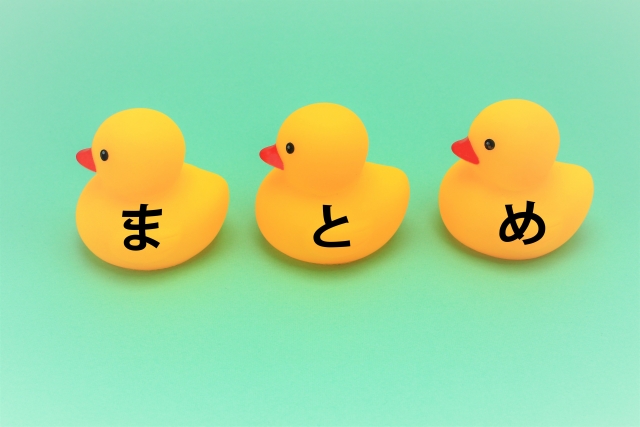
PDCAは「計画→実行→評価→改善」を繰り返し、品質向上や業務効率化に役立つ汎用性の高いフレームワークです。ただし、市場変化や革新が求められる場面では「古い」と見なされることもあります。
一方、OODAは「観察→判断→行動」を素早く回すことで変化への即応力を発揮します。重要なのは、状況に応じてPDCAとOODAを使い分け、それぞれの強みを活かすことです。本記事で紹介した『Knowledge Suite』のようなSFAツールを活用すれば、両サイクルを一元管理でき、質とスピードを両立する組織運営が実現できるでしょう。
ユーザー数無制限で利用できるシンプルで使いやすい
SFA/CRMツール Knowledge Suite!
営業活動の効率化と情報共有を一体化におすすめ!
【執筆者】
![]()
松岡 禄大朗
ブルーテック株式会社・デマンドジェネレーション部所属。
前職のWEB広告代理店で広告運用やアクセス解析を担当。
WEBマーケティング知識を活かして、現在はコンテンツマーケティングに携わり数多くの記事を執筆。