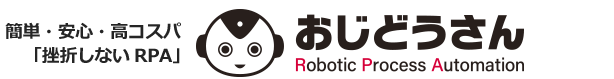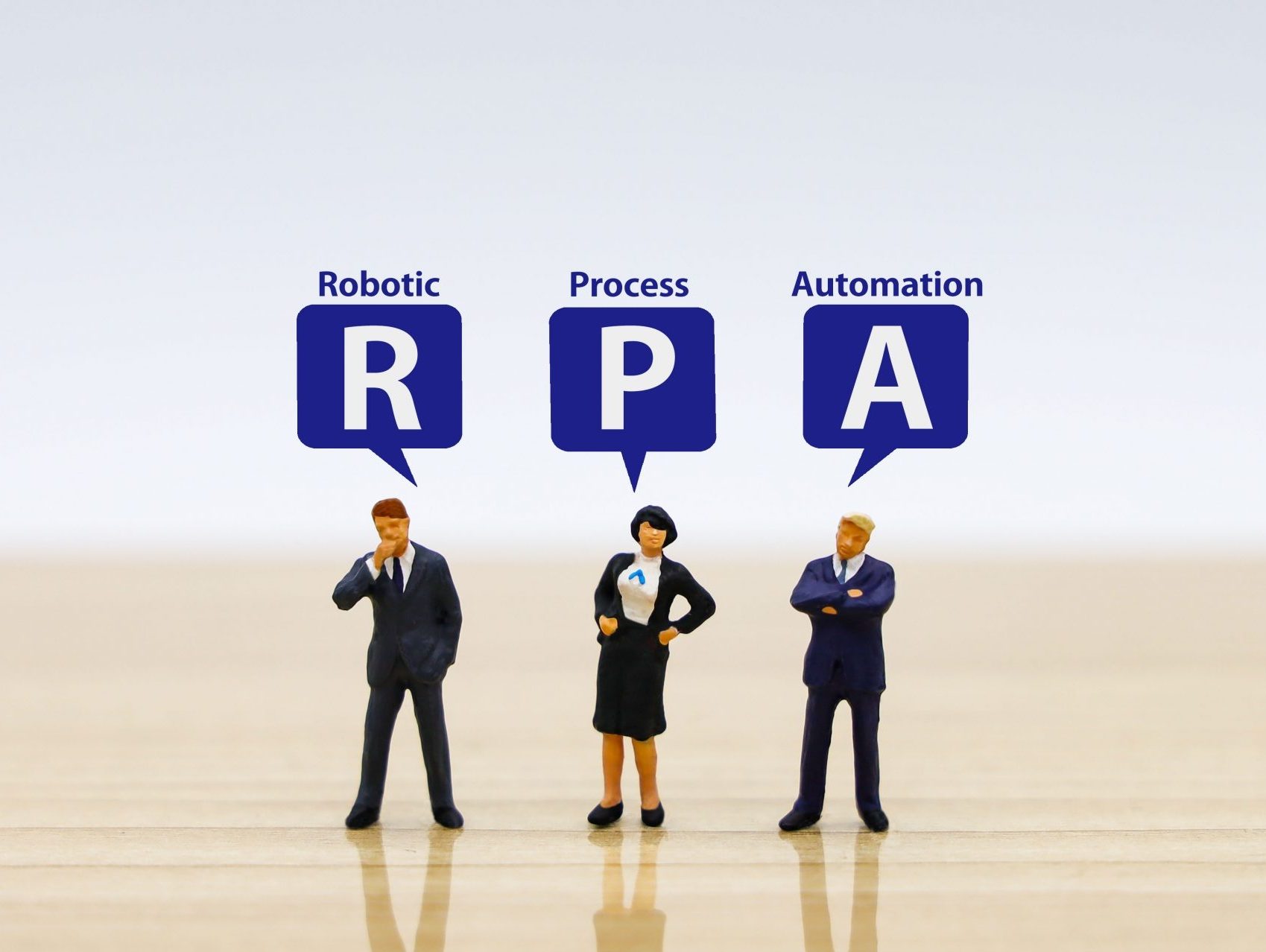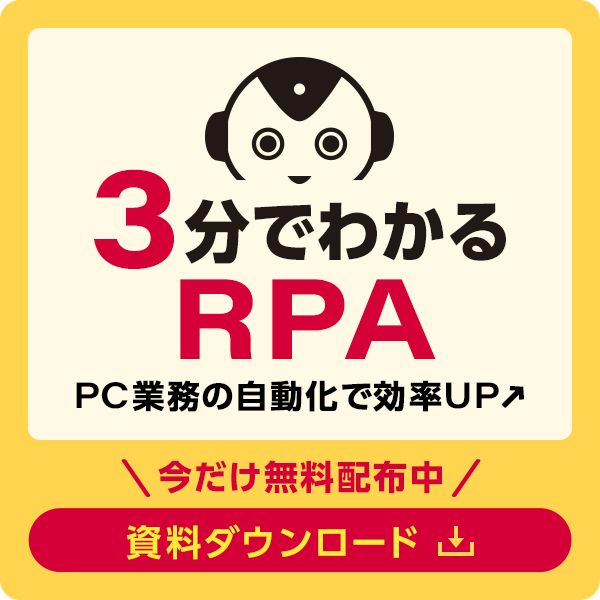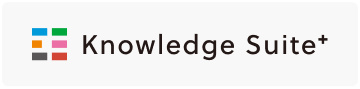RPAとロボットイノベーションとの違いは?事例や各メリットを紹介

業務の効率化を目指す企業の間で注目されているのが「RPA」と「ロボットイノベーション」です。いずれも自動化を実現する手段ですが、その目的や活用領域には明確な違いがあります。
本記事では、それぞれの定義や特徴、導入によるメリット、さらに実際の活用シーンまでをわかりやすく整理しました。業務自動化を検討している企業や、DX推進に取り組む担当者の方にとって、具体的なヒントとなる情報をご紹介します。
【この記事の内容】
RPAとロボットイノベーションとの違い
RPA(Robotic Process Automation)は、パソコン上で繰り返される事務作業(データ入力や定期レポート作成など)をソフトウェアで自動化する技術です。対してロボットイノベーションは、工場や倉庫にロボットを導入し、搬送・組み立てなど現場の「力仕事」を自動化します。
- RPA = デジタル業務の自動化
- ロボットイノベーション = 物理作業の自動化
RPAはPC内で完結するためヒューマンエラーを防ぎやすく、ロボットイノベーションは現場の人手不足を補いながら生産性と安全性を底上げできます。世界的に人材不足が進むなか、両技術はそれぞれ異なる角度から課題を解決しますが、少子高齢化が進む日本だけは導入メリットがより際立って見えるのが特徴です。
AIとは何が違うのか
AI(人工知能)とは、データから学習し、判断や予測を行う技術です。たとえば、顧客の行動を分析して次のアクションを提案したり、不良品を自動検出したりする場面で活用されます。
一方、RPAは決まったルールに従って業務を処理する仕組みで、判断力は持ちません。ロボットイノベーションも、あくまで物理的な作業を担う装置であり、AIのように自己学習や予測を行うことはできません。つまり、AIは「考える」、RPAやロボットは「動く」という役割の違いがあります。
ロボットイノベーションのメリットとは
ロボットイノベーションの最大の強みは、現場の安全性と生産性を飛躍的に高められる点にあります。たとえば、高所での作業や重量物の搬送といった危険な工程をロボットに任せることで、事故のリスクを抑えながら長時間の稼働を実現可能です。作業精度のばらつきが減るため、品質も安定しやすくなり、人為的なミスの削減にもつながります。
また、慢性的な人手不足の対策としても有効で、省人化と業務の継続性を両立させる手段として注目されています。製造業や物流現場ではその効果が顕著であり、ロボットの導入は単なる自動化を超えた、現場改革のカギといえるでしょう。
RPAで自動化できる業務の例

RPAは、主に「ルールが明確な業務」を得意としています。ここでは、実際にどのような業務がRPAによって自動化されているのか、具体的な事例をご紹介します。
顧客データの入力・更新業務
RPAは、CRMや基幹システムにおける顧客情報の入力・更新といったルーチン業務に最適です。
たとえば、営業担当者が収集した顧客情報(会社名や連絡先など)を、ExcelシートやSFAツールからCRMへ転記する作業はミスが起こりやすく、人的負担も大きくなりがちです。RPAを導入することで、こうした定型入力作業を正確かつ高速に自動化できます。データ形式の変換や項目のチェックもロボットが処理するため、誤入力や漏れを大幅に抑制できます。
また、定期的に取引先情報や顧客の属性情報を更新する必要がある企業では、古い情報を一括で最新データに置き換えるバッチ処理にも対応可能です。
請求書の発行・送付処理
請求書の発行業務は、経理部門でもとくに負担の大きいタスクのひとつです。RPAを導入することで、請求データの取得・帳票の作成・PDF化・メールへの添付・送信に至るまでの一連の流れを自動化できます。複数の業務システムから情報を抽出し、あらかじめ設定されたフォーマットに従って帳票を生成し、ミスのないかたちで送信できる点が大きな強みです。
これにより、請求書処理の正確性が向上し、経理担当者の作業負担を軽減できます。月末や月初の繁忙期でも処理が滞らなくなるため、担当者は内容確認や例外処理といった重要な業務に集中できるようになります。取引件数が多い企業ほど、作業時間の短縮や人件費の削減といった導入効果を実感しやすくなるでしょう。
定型レポートの作成・送付
営業日報や月次レポートなど、定期的に発生する帳票作成業務は、RPAの導入により高精度かつ効率的に自動化できます。売上データや在庫状況、顧客対応履歴などを基幹システムやExcelから抽出し、指定のフォーマットに自動反映する仕組みを構築することで、日々の集計作業を大幅に削減可能です。作成されたレポートは、設定されたタイミングで上司や取引先に自動送信されるため、人的リソースをほとんど使わずに業務を遂行できます。
また、送信漏れや入力ミスといったヒューマンエラーを未然に防ぐ効果もあり、報告の正確性が向上します。その結果、担当者は数値集計などの単純作業から解放され、より付加価値の高い分析や戦略立案に専念しやすくなるでしょう。
ロボットイノベーションで自動化できる業務の例

ロボットイノベーションでは、人手を必要とする現場作業を効率化できます。ここからは、どのような業務が実際に自動化されているのか、具体的な導入事例を紹介します。
製品のピッキング作業
倉庫や物流センターにおけるピッキング作業は、AGVやAMRといった物流ロボットの導入によって自動化が進んでいます。注文データをもとに、ロボットが自動で棚まで移動し、必要な商品を作業者のもとへ運ぶ「GTP(Goods to Person)」方式や、ロボットアームが直接商品をピックアップする方式が実用化されています。
さらに、バーコードや重量センサーによる自動検品を組み合わせることで、出荷ミスを未然に防ぐことも可能です。人手不足が深刻化する中、ピッキングの自動化は、業務効率と品質の両立を支える有効な手段といえるでしょう。
部品の組み立て作業
工場における小型部品の組み立てでは、協働ロボット(コボット)の活用が広がっています。これらのロボットは、人と同じ作業空間で安全に動作するよう設計されており、柵を設ける必要がないため、限られたスペースでも導入しやすいのが特長です。ネジ締めやパーツの挿入といった単純反復作業を正確かつ安定してこなせるうえ、作業者との分業によって工程全体の効率を高めることが可能です。
また、動作プログラムの柔軟性も高く、多品種少量生産にも適応できます。人手不足が深刻化する製造業の現場において、協働ロボットの導入は、作業の省力化と品質の安定化の両立に貢献する有力な手段となるでしょう。
製品検査の自動化
製造現場では、カメラやセンサーを搭載した検査用ロボットによる自動化が急速に進んでいます。たとえば、ライン上を流れる製品の外観や寸法をリアルタイムで撮影・分析し、あらかじめ設定された基準と照合することで、不良品を瞬時に識別します。高解像度カメラやAI画像認識技術の活用により、人間の目では見落としやすい微細なキズや汚れ、異物混入まで正確に検出できる点が強みです。
また、検査結果のデータは自動で蓄積・記録されるため、品質トラブル発生時の原因追跡や工程改善にも役立ちます。検査精度のばらつきを防ぎつつ、人的コストや工数を削減できることから、多品種・大量生産を行う工場を中心に導入が進んでいる状況です。こうした自動化の仕組みは、品質管理体制を強化し、顧客満足の維持にも貢献していくことでしょう。
RPAとロボットイノベーションを連携するメリット

RPAとロボットイノベーションを組み合わせることで、業務全体の自動化範囲を飛躍的に広げることが可能です。現場とバックオフィスの両方をカバーするこの連携は、以下のような効果をもたらします。
| メリット | 内容 |
| 業務の端から端まで自動化できる | 工場内の物理作業(ロボット)と、事務処理(RPA)を連動させることで、物流から帳票処理まで一括で自動化できます。 |
| 人的ミスの削減 | 各工程での手入力や伝達ミスを防ぎ、業務品質が安定します。 |
| コスト削減効果が大きい | 重複作業や待ち時間がなくなり、全体の作業時間が短縮されます。 |
| データの一元管理が可能に | ロボットが取得した情報をRPAが自動でシステムに反映させ、リアルタイムでの状況把握ができます。 |
このようにRPAとロボットの連携は、それぞれの利点を補完し合いながら業務の断絶を防ぎ、全体最適を実現する強力な手段といえるでしょう。
RPAとロボットイノベーションの連携を活用できる業種

RPAとロボットイノベーションを組み合わせた取り組みは、さまざまな業界で導入が進んでいます。ここでは代表的な3つの業界について、その活用方法を具体的にご紹介します。
製造業
製造現場では、ロボットが部品の搬送や組み立てを担当し、その作業データをRPAが自動で集計してレポートを作成する仕組みが普及しています。たとえば、生産ラインの進捗・不良率・設備の稼働状況をリアルタイムで可視化し、異常が発生した際にはすぐにアラートを通知することで、迅速な対応が可能になります。
このように、RPAとロボットを組み合わせることで製造工程全体の効率性と精度が向上し、持続的な生産体制の構築につながっていくでしょう。
物流業
物流業界では、ロボットとRPAを連携させることで、倉庫内作業から出荷処理までを一貫して効率化できます。具体的には、搬送ロボットが商品を自動でピッキングして指定エリアへ搬送し、RPAが受注データに基づいて配送情報を入力。帳票の作成や納品スケジュールの調整まで、自動で対応可能です。このような自動化により、人的ミスの削減や作業スピードの向上が実現し、繁忙期でも業務の平準化と安定運用がしやすくなります。
さらに、出荷精度が高まることで納期遵守率が向上し、取引先や顧客からの信頼を得やすくなるでしょう。
医療業界
医療現場では、ロボットとRPAの導入により、安全性と業務効率の両立が進んでいます。たとえば、検体搬送ロボットは院内を自律走行し、検体を衛生的かつ迅速に届けるため、手作業の負担や感染リスクを抑えられます。調剤ロボットも薬剤を自動で仕分け・充填し、薬剤師の確認作業を大幅に軽減できる仕組みです。
さらに、作業ログや検査・投薬データはRPAが電子カルテや病院情報システムに自動入力し、転記ミスを防止。これにより、医療スタッフは診療や患者対応により集中できるようになります。こうしたロボットとRPAの連携によって、医療の質と安全性を高めつつ、限られた医療資源を最大限に活かせる体制が整いつつあるのです。で含めた総合的な働き方改革の実現が期待できるでしょう。約4,700時間の業務時間削減が見込まれています。
RPAを導入するなら『おじどうさん』

ここまで、RPAとロボットイノベーションの違いや活用例、連携による効果について解説してきました。業務自動化を成功させるためには「現場に合った使いやすいRPAツール」の選定が欠かせません。そこで紹介するのが、ブルーテック株式会社が提供する『おじどうさん』です。『おじどうさん』は、専門知識やプログラミングがなくても誰でも簡単に操作できるのが特長です。マウス操作やドラッグ&ドロップでシナリオを作成できるため、現場部門主導で素早く自動化を始められます。
また、サーバー不要でPC1台から導入できるため、初期費用や運用コストを大幅に抑えられるのも魅力です。加えて、国産ツールならではの手厚いサポート体制により、導入から運用まで安心して活用できます。定型業務の効率化はもちろん、バックオフィス全体のDX推進にもつながる『おじどうさん』。中小企業から大企業まで幅広い導入実績を誇り、スモールスタートから段階的な拡張まで柔軟に対応できます。業務効率化を本格的に進めたい企業にとって、『おじどうさん』は心強いパートナーとなるでしょう。
まとめ

RPAとロボットイノベーションは、それぞれ「デジタル業務」と「現場作業」の効率化を担う異なる技術ですが、両者を組み合わせることで、業務全体をシームレスに自動化できる強力なソリューションになります。単独でも十分な効果が期待できますが、連携させることで生産性の向上やミスの削減、データの有効活用といった多くのメリットが生まれます。
まずは自社の業務プロセスを見直し、どこに自動化の可能性があるかを探ることから始めてみてはいかがでしょうか。
【執筆者】
![]()
松岡 禄大朗
ブルーテック株式会社・デマンドジェネレーション部所属。
前職のWEB広告代理店で広告運用やアクセス解析を担当。
WEBマーケティング知識を活かして、現在はコンテンツマーケティングに携わり数多くの記事を執筆。