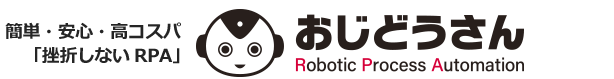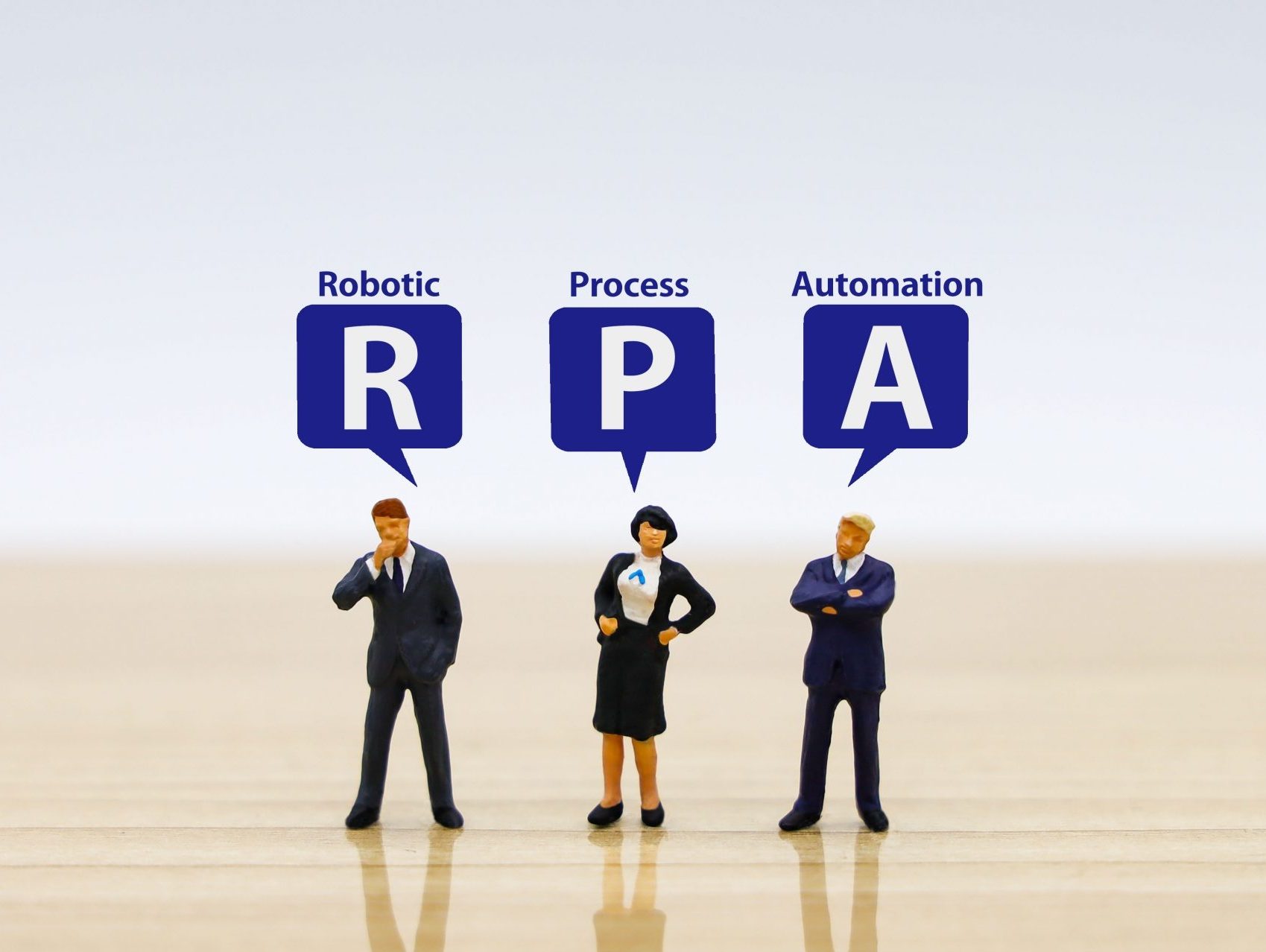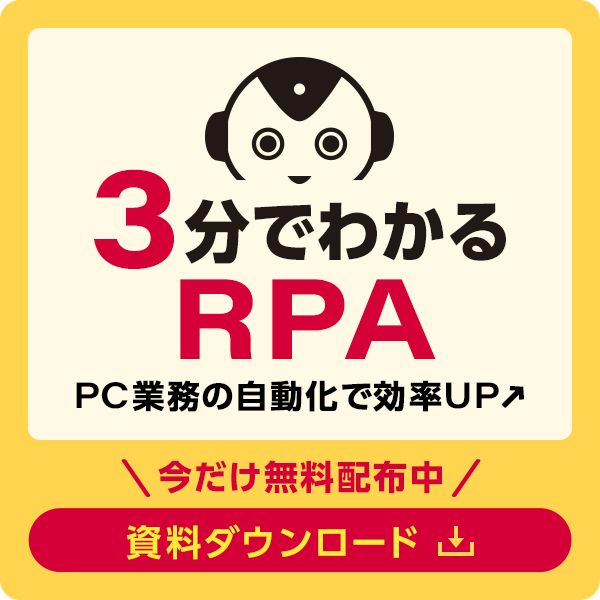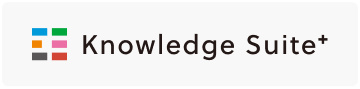RPAとAIの違いは?組み合わせるメリットや活用事例を徹底解説

RPAは「決められた手順の自動化」を得意とし、AIは「状況に応じて学習や判断を行う技術」として発展してきました。両者は性質こそ異なりますが、組み合わせることで単純な定型業務から複雑な非定型処理までを一貫して自動化でき、業務効率と品質を同時に高めることが可能です。
本記事では、RPAとAIの基本的な仕組みと特徴を整理し、その違いや相性、さらに組み合わせたときのメリットや具体的な活用事例までを徹底解説します。まずは両者の基本を押さえながら、ビジネスへの活用イメージを明確にしていきましょう。
そもそもRPAとは何か
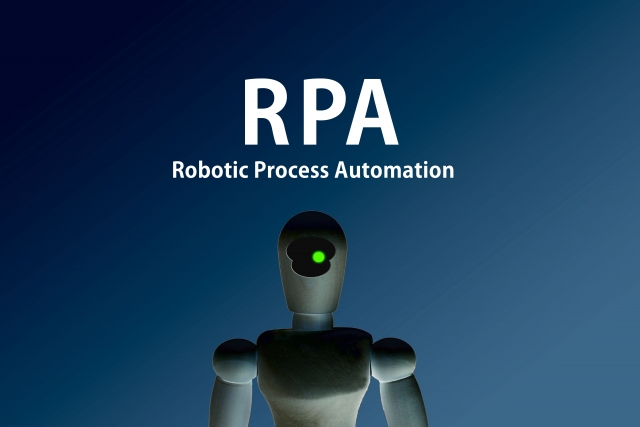
RPA(Robotic Process Automation)とは、パソコン上で人間が行っているクリックや入力、ファイル操作といった一連の処理を、ソフトウェアロボットが代わりに実行する仕組みです。請求書の転記やシステムへのデータ入力、定型メールの送信といったルーチンワークを正確かつ高速に処理できるため、作業時間の短縮やヒューマンエラーの削減に大きな効果を発揮します。
近年のRPAツールは、プログラミングの知識がなくても操作できるように設計されており、画面操作を記録して自動化したり、処理フローをドラッグ&ドロップで組み立てたりすることが可能です。そのため既存システムを改修せずに導入でき、短期間で効果を出しやすい点も普及を後押ししています。
運用形態は大きく3つに分かれます。
- ・利用者が端末上で起動して動かすデスクトップ型
- ・サーバー上で集中管理されスケジュールに従って自動実行されるサーバー型
- ・ブラウザ中心で柔軟に拡張可能なクラウド型
これらは業務の特性や体制に応じて適切に選択されます。
ただしRPAはあくまで「決められた手順の繰り返し」に強みを持つ技術であり、例外処理が多い業務や状況判断を伴うタスクには不向きです。そのため導入にあたっては業務を標準化し、手順を明確に設計しておくことが欠かせません。適切に活用できれば単純作業を自動化し、従業員はより重要な業務に集中できるようになり、組織全体の効率化と品質向上につながるのがRPAの大きな魅力です。
AIとは何か
AI(Artificial Intelligence、人工知能)とは、データを学習し、パターン認識や推論を通じて判断を行う技術の総称です。音声や画像を識別したり、文章を理解して応答したりと、人間の知的活動を機械に再現することを目的としています。AIにはいくつかの段階やタイプが存在していて、いわゆる「弱いAI(特化型AI、ANI)」は、画像認識や音声変換のように特定の分野に特化したAIです。
一方で、人間と同等の汎用的能力を目指す「汎用AI(AGI)」や、人間の知能を超える「超知能(ASI)」という概念も存在します(現時点では実現していません)AIはシステムやツールに組み込まれて「頭脳」として機能し、大量データの解析や予測、分類に優れています。
たとえば売上データをもとに需要を予測したり、問い合わせ内容を自動で分類して適切な回答を提示したりと、幅広い場面で人の判断を補完しながら精度を高めることが可能です。こうした特長から、AIは現代のビジネスや社会に欠かせない基盤技術となっています。
RPAとAIの違いとは?

RPAは定義済みの手順を正確に実行することを得意とし、AIはデータをもとに学習し判断する力に優れています。両者は互いを補い合う関係にあり、組み合わせれば自動化の範囲を大きく広げられます。
ここではその違いを主要な観点から比較していきましょう。
| 項目 | RPA | AI |
| 基本的な役割 | ルールどおりに作業を自動実行 | データから学習し判断を生成 |
| 得意領域 | 定型・ルーチン業務 | 非定型処理やパターン認識 |
| 入力データ | 構造化データが中心 | 画像や音声など非構造化データも扱える |
| メリット | ・作業速度が速い ・再現性が高い ・ミス削減に効果的 | 精度を高めながら柔軟に対応できる |
| デメリット | イレギュラー処理に弱い | 学習データや運用設計が不可欠 |
| 導入ハードル | 比較的容易 | 目的設計と学習環境の整備が必要 |
| 主なユースケース | ・伝票転記 ・定型メールの自動送信 ・業務システムへの登録 | ・需要予測 ・AI-OCR ・対話型チャット |
| 使い分け | 手足として確実に動かす | 頭脳として判断を付与する |
このように、RPAはルールに従った処理を正確にこなす「手足」として、AIはデータを分析して判断を与える「頭脳」として機能します。比較することで両者の特性がより明確になり、どの業務にどちらを適用すべきかが分かりますね。
RPAとAIを組み合わせるメリット

RPAとAIを組み合わせると、これまで人手に頼っていた幅広い業務を一連の流れで自動化できます。たとえばAI-OCRが紙やPDFの情報を正確に読み取り、そのデータをRPAが基幹システムに登録すれば、入力作業の手間を大幅に削減でき、スピードと精度の両方を確保できます。さらにAIによる需要予測や不良品検知の結果をRPAの処理フローに組み込めば、帳票の作成やメール通知、チケットの起票まで自動で実行可能です。
こうした仕組みによって、人が関わるべき判断と定型作業を分担でき、業務全体を効率的に回せるようになります。結果として処理時間の短縮と品質の安定が実現し、例外対応や戦略的な業務に人材を集中させられる点が大きな強みです。
導入も段階的に進められるため、まずは定型業務の自動化から始め、徐々にAIを組み合わせれば、リスクを抑えながら効果を積み重ねられます。このように両者を掛け合わせることで、効率性・精度・柔軟性を同時に高め、組織全体の生産性を大きく向上させられるでしょう。
RPAとAIを組み合わせた活用事例

以下では、実務でイメージしやすい 「AI-OCR × RPA」 と 「対話型AI × RPA」 の2つの組み合わせ事例を紹介します。課題から導入、そして効果までの流れを整理していますので、自社業務に置き換えて考えるきっかけにしてみてください。
自治体における申請書処理の効率化(AI-OCR × RPA)
千葉県内の中規模自治体では、紙の申請書を職員が目視で確認し、住民システムへ入力していました。繁忙期には数千件単位の申請が集中し、処理の遅れや転記ミスが大きな課題でした。
そこでAI-OCRを導入して手書き文字をデータ化し、RPAで台帳システムへ自動登録する仕組みを構築。結果、入力作業が数分の一に短縮され、誤入力の件数も大幅に減少しました。職員は窓口対応や市民への説明に時間を割けるようになり、結果として住民サービスの質も向上しました。
大手損害保険会社における請求受付の自動化(対話型AI × RPA)
国内大手の損害保険会社では、顧客からの事故や保険金請求をオペレーターが電話で聞き取り、その内容を基幹システムへ手入力していました。しかし、聞き取りの精度やスピードは担当者ごとにばらつきがあり、処理時間や顧客満足度に影響していました。そこで導入されたのが、対話型AIとRPAの連携です。
AIが顧客との会話から必要事項を漏れなく収集し、RPAが基幹システムへ即時反映するフローを構築。導入後は平均処理時間が大幅に短縮し、夜間や休日の問い合わせにも自動対応できるようになりました。結果、オペレーターは複雑なケースの対応に専念でき、全体的な応答品質が安定しました。間削減が見込まれています。
RPAを導入するなら『おじどうさん』

ここまで、RPAとAIの仕組み・違い・連携メリット、そして現場での活用例まで解説してきました。自社に合った自動化を定着させるには、操作が簡単で安定稼働し、導入〜運用サポートが手厚いRPAを選ぶことが重要です。そこでおすすめしたいのが、ブルーテック株式会社が提供する国産RPAツール『おじどうさん』です。
シンプルなUIと安定した動作が特長で、導入から勉強会、運用サポートまで無償で提供されるため、初めてでも安心して取り組めます。無料トライアルも用意されているため、効果を検証したうえで導入判断ができる点も大きな魅力です。まずは実際に試してみて、自社業務にどのようにフィットするのかを確認してみるとよいでしょう。
まとめ

RPAは手順の自動実行に強く、AIは学習と判断によって非定型処理を補います。両者を組み合わせれば、入力から登録、さらには予測や回答までを一連で自動化でき、工数削減と品質向上を実感しやすくなります。
本記事で紹介した『おじどうさん』のようなRPAツールを活用して、自社の業務に合った自動化を進めてみてはいかがでしょうか。日々の負担が軽くなり、より価値の高い仕事へ集中できるようになるでしょう。
【執筆者】
![]()
松岡 禄大朗
ブルーテック株式会社・デマンドジェネレーション部所属。
前職のWEB広告代理店で広告運用やアクセス解析を担当。
WEBマーケティング知識を活かして、現在はコンテンツマーケティングに携わり数多くの記事を執筆。