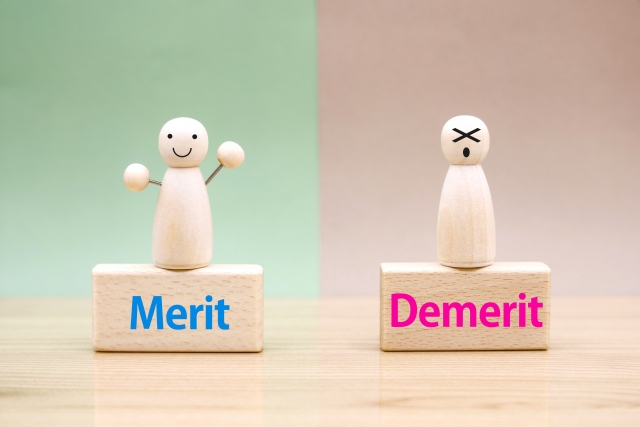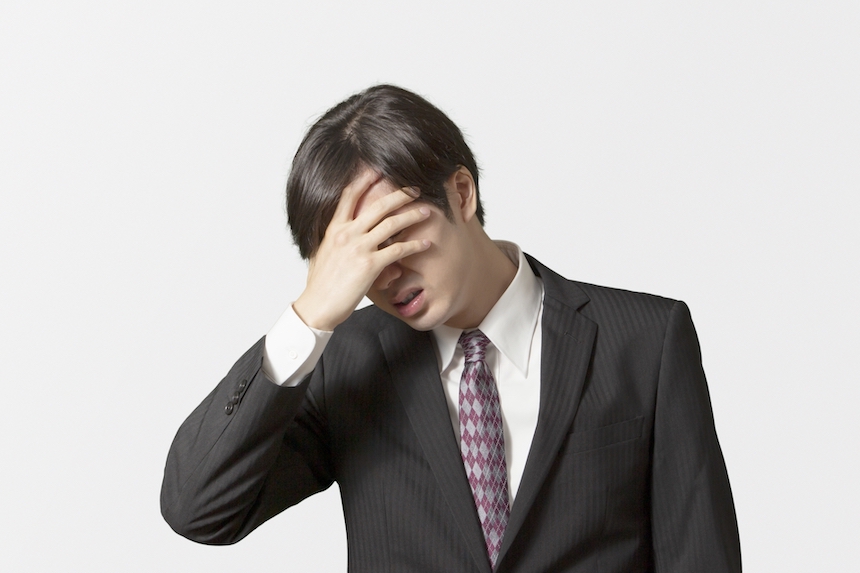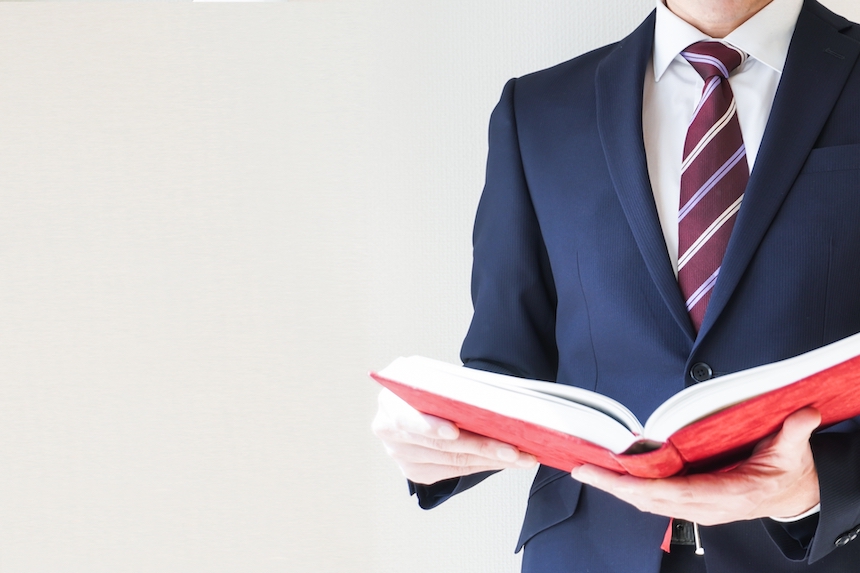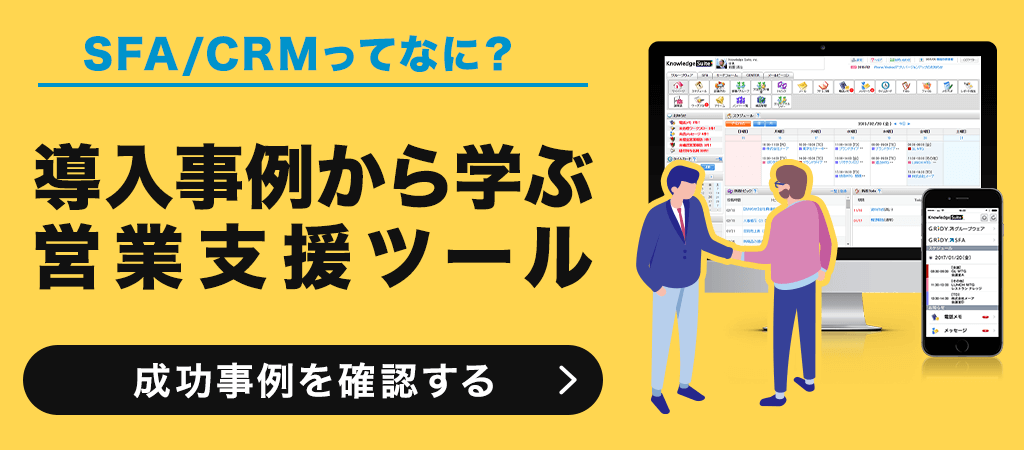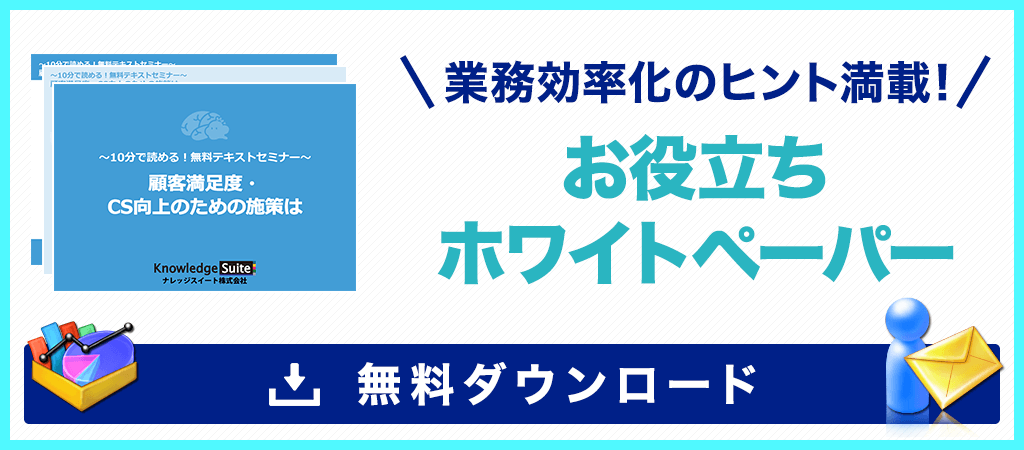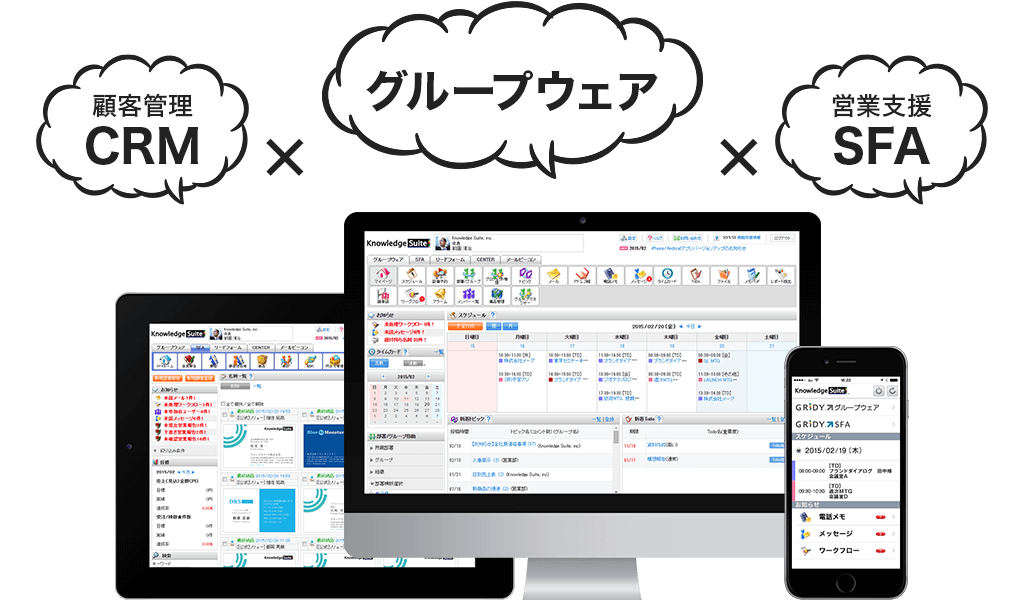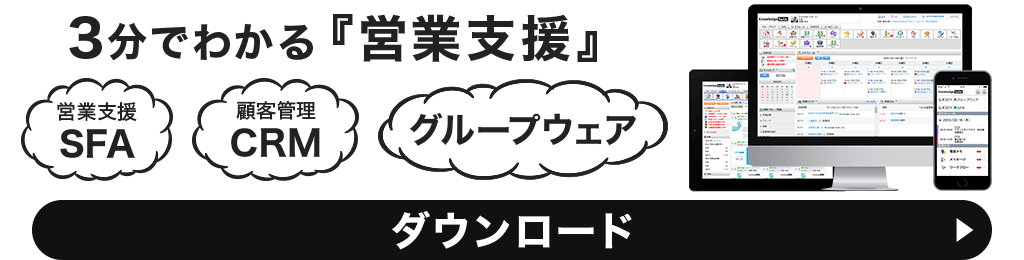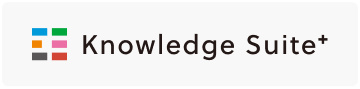デジタル化(情報化)のメリット・デメリットは?進め方、導入事例を紹介

近年、企業や自治体において「デジタル化」の重要性がますます高まっています。業務の効率化やコスト削減など多くのメリットが期待される一方で、導入コストやセキュリティリスクといった課題も無視できません。
そこで本記事では、デジタル化によって得られる主なメリット・デメリットをはじめ、IT化・DXとの違いや導入事例、導入の進め方などをわかりやすく解説します。これからデジタル化を検討されている企業様の一助となれば幸いです。
【この記事の目次】
デジタル化(情報化)とは何か

デジタル化(情報化)とは、これまで紙や手作業で行っていた業務や情報管理を、パソコンやITツールなどのデジタル技術を使って行うことを指します。
たとえば、紙の書類を電子データに変換して保存したり、手作業で行っていた処理をシステム化して自動化したりするケースが代表的です。これにより、業務のスピードと正確性が向上し、情報共有もスムーズになります。結果として、企業全体の生産性や競争力の向上につながります。
デジタル化・IT化・DX化の違い
「デジタル化」「IT化」「DX化(デジタルトランスフォーメーション)」は、いずれもデジタル技術を活用する取り組みですが、それぞれの意味や目的は異なります。
| 用語 | 定義 | 目的・効果 |
| デジタル化 | アナログ情報をデジタルデータに変換し、業務を効率化すること。 | ・業務の効率化 ・情報の共有 ・管理の容易化 |
| IT化 | デジタル化された情報を活用し、ITシステムを導入・活用すること。 | ・業務プロセスの最適化 ・コスト削減 |
| DX化 | ITを活用してビジネスモデルや組織文化を変革すること。 | ・競争優位性の確保 ・新たな価値創出 |
まず、デジタル化は紙の書類やアナログな業務をデジタルに置き換えることで、業務の効率化や情報共有を図る最初のステップです。次の段階であるIT化では、デジタル情報を活用して業務全体を見直し、最適化やコスト削減を図ります。
さらにDX化では、ITを活用してビジネスモデルや組織そのものを変革し、新たな価値を生み出すことが求められます。これらは段階的に進めるべきプロセスであり、自社の成長段階や課題に応じて、適切なステップを見極めることが重要です。
デジタル化(情報化)が重視されている理由

近年、多くの企業や自治体でデジタル化が強く求められている背景には、いくつかの社会的・経済的課題があります。この章では、特に重要とされる「2025年の崖」問題と、日本が直面する人材不足の課題に着目し、なぜ今デジタル化が欠かせないのかを解説します。
「2025年の崖」問題にどう向き合うか
デジタル化が急務とされる大きな要因のひとつが「2025年の崖」問題です。
これは、古くなったITシステム(レガシーシステム)を放置したままにしておくことで、企業の競争力が低下し、日本経済全体の停滞につながると懸念されているものです。経済産業省の「DXレポート」では、レガシーシステムの維持に多くのコストや人材が割かれている現状を指摘し、2025年以降には年間最大12兆円の経済損失が発生する可能性があるとされています。
こうした事態を回避するには、既存の仕組みに依存し続けるのではなく、最新のIT技術へとシフトする決断が求められます。今後の企業活動を支える基盤として、デジタル化への投資と実行が不可欠です。
労働人口の減少と人材不足への対応
もうひとつの重要な背景が、日本全体で進む少子高齢化による労働力不足です。特に地方や中小企業では人材の確保が難しく、採用が思うように進まないことで事業継続に支障が出るケースも増えています。限られた人員で多くの業務をこなす現場では、従業員の負担が日々増しているのが現状です。
こうした状況を打開するには、業務の自動化や効率化の推進と同時に、柔軟な働き方を実現する職場環境の整備が求められます。デジタル技術の導入は、単なる効率化にとどまらず、人材不足という構造的な課題に対する解決策のひとつとしても非常に有効です。
今後の持続的な成長を見据えるなら、デジタル化を土台とした働き方改革が不可欠といえるでしょう。
デジタル化(情報化)を進めるメリット

デジタル化を推進することで、企業は業務の効率化やコスト削減、柔軟な働き方の実現など、多岐にわたる利点を得られます。以下では、具体的な7つのメリットについて詳しく解説します。
業務効率化と生産性の向上
デジタル化は、日々の業務を効率化し、生産性を高めるための有効な手段です。たとえば紙の書類を電子化することで、情報の検索や共有がスムーズになり、作業時間を短縮できます。
さらに、ITシステムによる業務の自動化は、ミスの防止や作業の標準化にも効果的です。こうした環境が整えば、従業員はルーチンワークから解放され、付加価値の高い仕事に集中できるようになります。また、蓄積データの活用により、業務改善や新たなビジネスチャンスにつながる可能性もあります。
コスト削減の実現
デジタル化の推進は、コスト面でも多くのメリットをもたらします。たとえば、業務の自動化やクラウドサービスの活用により、作業時間を短縮できるだけでなく、人件費や管理コストの削減にもつながります。
また、オンライン会議の導入によって出張の機会を減らすことで、交通費や宿泊費といった間接コストの削減も可能です。このように、デジタル化は単なる業務効率化にとどまらず、継続的なコスト最適化を実現するための重要な施策といえるでしょう。
情報共有とコミュニケーションの円滑化
デジタル化を進めることで、情報はクラウド上で一元的に管理できるようになります。
これにより、部署や拠点をまたぐ連携がしやすくなり、外部パートナーとのやり取りも効率的に進められます。必要な情報に素早くアクセスできる環境が整えば、確認作業や伝達ミスが減少し、業務の無駄を減らすことも可能です。
さらに、意思決定のスピードが向上し、チーム内外の連携が強化されることで、組織全体のパフォーマンス向上にもつながっていきます。
働き方の多様化を実現
デジタル化の進展により、時間や場所にとらわれない柔軟な働き方が可能になりました。テレワークや在宅勤務の浸透は、子供を育てながら働く世代の負担軽減にもつながり、ワークライフバランスの向上や離職防止に寄与しています。
さらに、オンライン会議や電子契約の活用によって出張や対面業務が減少し、移動時間や交通費の削減にも効果を発揮しています。
データ活用による意思決定の高度化
デジタル化の進展により、企業はさまざまな業務データを蓄積できるようになりました。これらの情報を分析することで、経験や勘に頼らず、客観的かつ論理的な判断が行えるようになります。
また、リアルタイムでデータを把握することで、状況の変化にも迅速かつ柔軟に対応できる体制を整えられます。このように、データを基盤とした意思決定は精度を高めるだけでなく、企業の競争力を底上げする重要な要素です。持続的な成長を図るうえでも、データドリブンな経営は欠かせません。
セキュリティの強化とリスク管理の向上
デジタル化の進展に伴い、サイバーセキュリティの重要性が増しています。企業は、ファイアウォールや侵入検知システム、データ暗号化などの技術的対策を導入することで、不正アクセスや情報漏洩のリスクを低減できます。
さらに、従業員へのセキュリティ教育や物理的なアクセス制御の強化など、人的・物理的な対策も重要です。これらの多層的なセキュリティ対策を講じることで、サプライチェーン全体のリスクを総合的に管理し、企業の安定性を強化することが可能になります。
顧客満足度の向上と新たな価値創出
デジタル化により、顧客の行動や好みがより明確に見えるようになり、一人ひとりに合ったサービスを届けやすくなります。加えて、フィードバックや市場の変化をリアルタイムで把握することで、新たな製品やサービスの開発もスムーズに進められます。
このように、顧客との関係性を強化しながら、継続的に新たな価値を生み出せる点は、デジタル化の大きなメリットです。
デジタル化(情報化)を進めるデメリット

デジタル化を進めることで、業務効率の向上やコスト削減など多くのメリットが得られます。
しかしその一方で、導入や運用にあたっての課題や注意点も無視できません。ここからは、企業がデジタル化を進める際に直面しがちな主なデメリットについて、具体例を交えながら解説します。
初期導入や運用にコストがかかる
デジタル化を進める際には、ハードウェアやソフトウェアの購入費用に加え、導入・設定、外部コンサルの依頼費用などがかかります。既存データの移行作業なども必要になるため、初期投資が高額になる可能性が高いです。企業規模や導入範囲によって費用は変動し、大企業では年間売上の数%を充てる場合もあります。
また、クラウドサービスの利用料やライセンス更新費・通信費・人件費など、運用面でもコストは継続的に発生します。セキュリティ対策や社員研修といった支出も無視できません。これらを見落とすと、想定外のランニングコストに悩まされるおそれがあります 。
セキュリティリスクへの備えが不可欠
業務のデジタル化が進むにつれ、情報資産を狙ったサイバー攻撃やシステムトラブルの発生件数が増加しています。顧客情報や企業機密が外部に流出するケースも後を絶たず、信頼の失墜や多額の損害につながる恐れがあります。マルウェアやランサムウェアによる被害も深刻化しており、実際にシステムが停止し、業務が一時中断する事例も少なくありません。
加えて、外部からの攻撃だけでなく、従業員による不正行為や設定ミスなど、内部要因によるリスクも見過ごせない課題です。こうした背景から、セキュリティ対策は単なる技術的な課題にとどまらず、経営戦略の一環として取り組むべき重要なテーマといえるでしょう。
システム障害やトラブルによる業務停止リスク
デジタル化のために導入したシステムが、障害や故障によって一時的に使えない可能性がある点もデメリットといえます。万が一システムが停止した場合「必要なときにデータを確認できない」「操作方法を担当者しか把握していない」など、営業活動や日常業務に支障をきたすおそれがあります。
こうしたリスクに備えるためには、データの定期的なバックアップや業務マニュアルの整備、代替手段の確保といった対策が欠かせません。
社内にデジタル化が定着しないおそれ
デジタル化を進めるには、実際に業務を行う現場からの理解が不可欠です。デジタル化の目的や必要性などが共有されていない状態では、導入したツールやシステムの効果を十分に発揮できない可能性があります。
デジタル化を進める際は、現場に対して目的や必要性を説明して、十分な理解を得るようにしましょう。現場の理解を得ると組織全体が同じ意識を持てるため、スムーズに導入を進められます。
デジタル化(情報化)の導入事例4選

昨今、業務効率化やコスト削減を目的に、デジタル化を成功させている企業が増えています。以下では、実際にデジタル技術を活用し成果を上げている企業の事例をご紹介します。自社の取り組みを検討する際のヒントとして、ぜひ参考にしてみてください。
事例①:大手自動車メーカー|材料開発プロセスのDXで開発期間を大幅短縮
とある大手自動車メーカーでは、新素材の開発に多くの時間とコストを要する点が大きな課題となっていました。
特に、車両の軽量化や耐久性向上を目指す材料選定では、従来の試作・実験に頼る手法では限界があり、非効率な状態が続いていたのです。この課題に対応するため、同社はAIとシミュレーション技術を導入。物性を予測しつつ設計を最適化できる仕組みを構築し、開発プロセス全体をデジタル化しました。
その結果、試作の手間を減らしながら素材の精度を高めることに成功し、開発スピードと市場投入までの期間短縮を同時に実現しています。コスト削減と品質向上の両立を達成したことで、製品開発における競争力が大きく向上しました。
事例②:大手食品メーカー|AIによる原材料の不良品検知で品質管理を自動化
ある大手食品メーカーでは、原材料の品質管理を目視に頼っていたため、見落としや判断のばらつきが課題となっていました。特に、ライン作業では集中力の維持が難しく、見落としによる品質リスクが懸念されていたのです。
この問題を解決するため、同社はAIを活用した画像解析システムを導入。カメラで撮影した原材料の画像をAIがリアルタイムで解析し、表面の傷や異常を自動で検出できる仕組みを構築しました。人間の主観に依存せず、客観的かつ安定した判定が可能となっています。
その結果、検査ミスと不良率が減少し、負担軽減やライン速度の向上にもつながりました。
事例③:中堅製造業|AIとセンサーを活用したスマートファクトリー化の推進
ある中堅規模の製造業でも、人手不足に加え、作業者によって製品の品質にばらつきが出るなど、安定した生産体制の維持が課題となっていました。
そこで同社は、AIと各種センサーを組み合わせたシステムを導入。製造ラインに設置したセンサーから収集される温度・振動・稼働データなどをリアルタイムで分析し、設備の状態や製品の品質を常時モニタリングできる体制を整えました。これにより、不具合の兆候を早期に察知してメンテナンスに活かせるだけでなく、作業の自動化や稼働率の向上にもつながりました。
結果として、生産性と品質管理の精度がともに向上しています。
事例④:精密加工メーカー|デジタルツイン活用で機械加工の最適化を実現
ある精密加工メーカーでは、数ミクロン単位の加工精度が求められる現場において、加工条件の微調整に多くの時間と熟練の勘が必要とされていました。
そこで同社は、加工機や製品の状態をリアルタイムで反映する「デジタルツイン」技術を導入。実際の加工工程を仮想空間で再現し、工具の挙動や加工条件の違いが仕上がりに与える影響をシミュレーションしながら、最適な設定を事前に検証できる環境を整えました。
この取り組みにより、加工の精度と再現性が高まり、準備作業や条件調整にかかる手間と時間も削減されました。その結果、リードタイムの短縮・コストの低減・品質の安定化を同時に実現し、高精度加工分野での競争力が一段と強化されています。
デジタル化(情報化)を進める手順

デジタル化の推進は、単なるツールの導入ではなく、業務プロセスや組織全体の変革を伴います。そのため、以下のような段階的なアプローチが推奨されます。
ステップ①:目的の明確化と現状の把握
まずは「なぜデジタル化が必要なのか」という目的をはっきりさせます。
次に、今の業務の流れや使っているシステムを見直し、どこにムダや問題があるのかを洗い出しましょう。この段階で方向性が見えると、次のステップがスムーズになります。
ステップ②:戦略の策定と体制の構築
目的や課題がはっきりしたら、それをどう実現するかという計画を立てます。
あわせて、実行をリードするチームをつくり、必要な人材や予算なども準備しておきましょう。関係部署とも連携できる体制を整えることで、スムーズに進められるようになります。
ステップ③:優先順位の設定と段階的な実行
デジタル化を実施したあとは、どれだけ効果が出たかをしっかり確認しましょう。うまくいった点だけでなく、改善が必要な部分も洗い出して、次の取り組みに活かすことが大切です。こうした見直しを繰り返す「PDCAサイクル(計画・実行・評価・改善)」を回していくことで、取り組みの質がどんどん高まります。
その結果、組織全体としてデジタル化に強くなり、変化にも柔軟に対応できる体制が整っていきます。
ステップ④:効果の検証と継続的な改善
すべての業務を一度に変えようとすると、負担が大きくなり、かえって混乱を招くことがあります。そこで、影響の大きい業務や、改善効果が見込める部分から順に取り組むのが効果的です。まずは小さな業務から始めて、成果を見ながら段階的に広げていくことで、リスクを抑えて着実に進められます。
SFAなら『Knowledge Suite』

デジタル化を成功させるには、自社の目的に合ったツール選びが欠かせません。営業や顧客管理を含む業務全体の効率化には、ブルーテック株式会社の『Knowledge Suite』が注目されています。このツールはユーザー数無制限の定額制で、社員数に関係なくコストを抑えて運用できるのが特長です。
SFA・CRM・スケジュール管理などを一体化したオールインワン型で、複数システムを使い分ける必要もありません。操作は直感的で情報共有やセキュリティも万全、スマホやタブレット対応でテレワークにも最適です。
初めてSFAを導入する企業はもちろん、既存ツールを見直したい企業にも選ばれているので、まずは無料トライアルで使い勝手を体感してみてはいかがでしょうか。
まとめ
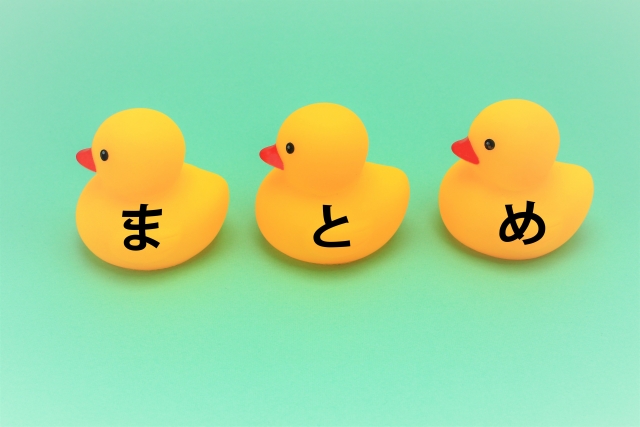
デジタル化は業務効率の向上やコスト削減、柔軟な働き方の実現など、多くのメリットをもたらします。
その一方で、導入コストやセキュリティ対策といった課題もあるため、目的に応じて段階的に進めることが大切です。導入にあたっては、自社の業務課題や目的に合致したツールを選定することが重要です。業務全体をカバーし、柔軟かつコスト効率に優れた『Knowledge Suite』のようなSFAツールを活用することで、より実用的で持続可能なデジタル化を実現できるでしょう。
自社に合った形で、計画的にデジタル化を進めていきましょう。
ユーザー数無制限で利用できるシンプルで使いやすい
SFA/CRMツール Knowledge Suite!
営業活動の効率化と情報共有を一体化におすすめ!