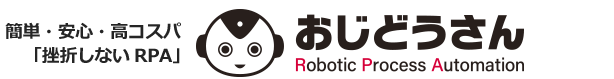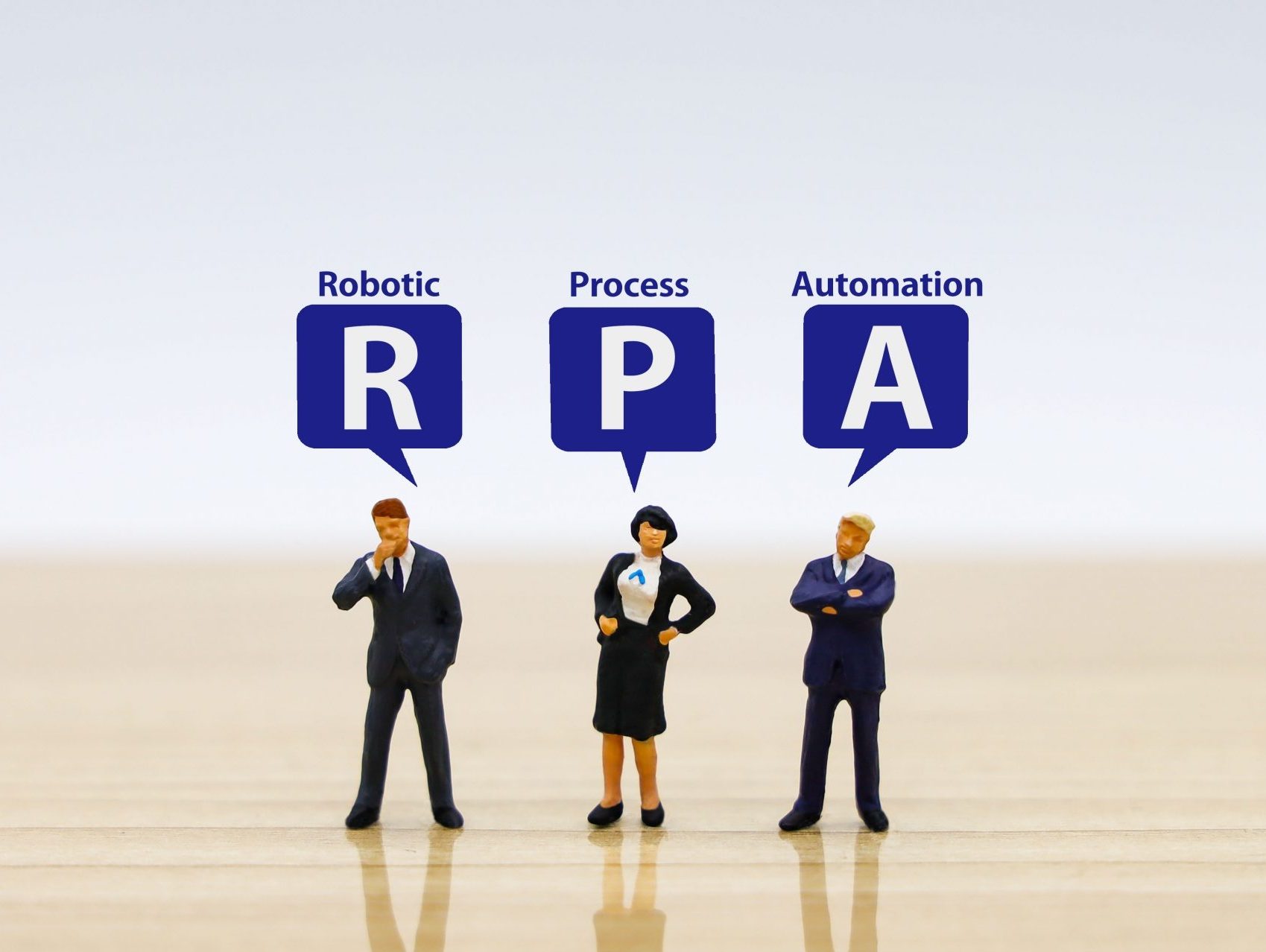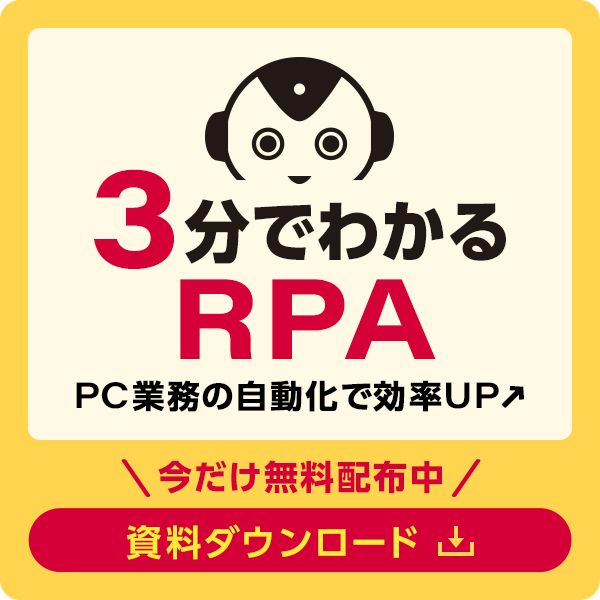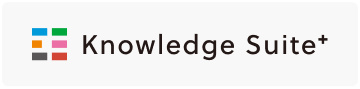RPAを活かして人材不足を解消!成功のコツや活用例を紹介

深刻化する人手不足の解決には、「人を増やす」よりも「ムダを減らす」視点が重要です。RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を活用すれば、定型業務を自動化し、限られた人材をより重要な業務へ集中させることが可能になります。少子高齢化によって労働力が減少するなか、RPAは今や多くの企業にとって欠かせない生産性向上ツールといえるでしょう。
本記事では、人手不足の背景・RPA導入のメリット・活用事例、さらに業種別におすすめのRPAツールまで詳しく解説します。「人手が足りない」「業務を効率化したい」とお悩みの方は、ぜひ最後までご覧ください。
【この記事の内容】
人材不足が深刻化している現状

日本の労働力人口は年々減少しており、社会全体に深刻な影響を与えています。厚生労働省の推計によると、生産年齢人口(15〜64歳)は、2020年の7,509万人から2040年には6,213万人、2070年には4,535万人にまで減少する見通しです。今後も加速度的に働き手が減っていくことが明らかになっています。
また、帝国データバンクの調査では、2024年の「人手不足倒産」が342件にのぼり、過去最多を更新しました。とくに「退職型倒産」と呼ばれる、従業員の離職が直接の引き金となるケースも87件に達し、あらゆる業界で人材確保の難しさが浮き彫りになっています。
さらに、人件費の上昇や新人教育の負担が経営を圧迫しつつあり、今後は「2025年問題」による大量退職の影響で、業務ノウハウの継承すら危うくなると予測されています。企業にとっては、単なる採用強化だけでなく、抜本的な生産性向上策が急務となっているのが現状です。
人手不足が著しい業界

少子高齢化の進行に加え、業界ごとの需要が急増することで、人材不足が深刻な課題となっています。ここでは、そうした「人手不足の最前線」にある代表的な3業界について、それぞれの現状と背景を詳しく見ていきましょう。
医療・介護業界
高齢化で患者・利用者は増える一方、医師や看護師、介護士の確保が追いついていません。介護職の有効求人倍率は約3.9倍と、全職種平均の約3倍に達しており、人手不足は深刻です。残業や夜勤の負担も大きく、離職率の上昇につながっています。また、カルテ入力や請求処理などの事務作業が医療行為の時間を圧迫し、サービス品質低下や残業増加を招きがちです。
こうした状況を人員補充だけで解決するのは難しく、ITや自動化による業務効率化が不可欠という認識が業界内でも広がっています。国もデジタル化を後押しするDX補助金を用意しており、早期の対策とシステム導入が喫緊の課題となっています。
物流業界
EC市場の拡大により荷物量は増加し続けていますが、現場では深刻な人手不足が進行中です。トラックドライバーの平均年齢は48歳を超え、求人倍率は5.2倍に達しています。長時間労働への懸念から若手の採用は難航し、物流の「2024年問題」による時間外労働の上限規制で、輸送力の不足がさらに顕在化しました。
また倉庫現場では、ピッキングやデータ入力といった定型作業に多くの人手が割かれ、誤出荷などの品質リスクも増えています。作業時間を抜本的に削減しなければ、今後は荷物の取扱量すら維持できなくなる恐れがあります。こうした課題に対応するには、RPAとロボットの連携による業務自動化が不可欠です。
飲食業界
コロナ禍を経て客足は戻りつつあるものの、人手不足は依然として深刻です。アルバイトの応募数は10年前の半分以下に減り、ピーク時に人手が足りず、売上機会を逃すケースも増えています。
さらに、深夜営業の負担や低賃金といった労働環境の厳しさが、スタッフの定着率を下げる要因となっています。現場ではPOS入力や棚卸し、シフト作成などのバックヤード業務が多く、管理職が改善活動にまで手が回っていないのが現状です。こうした構造が続く限り、生産性を高めなければ多店舗展開の実現は難しいといえるでしょう。
人手不足に対してRPAが必要な3つの理由

人材確保に頼らず生産性を底上げするには、繰り返し事務を自動化し、人を価値創出業務へ再配置する仕組みが不可欠です。ここでは「時間削減」「品質向上」「従業員満足」の三視点でRPAが必要な理由を整理します。
大幅な時間削減とコスト圧縮
RPAは、人手では30分かかるデータ転記作業を数秒で処理し、24時間365日稼働し続けます。なかには、1台のロボットが年間1,500時間分の作業を代替し、人件費を約30%削減できたというケースもあるようです。
作業時間の短縮はそのままリードタイムの短縮や顧客満足度の向上につながり、浮いたコストを新サービスの企画や人材育成にも充てられます。こうした即効性の高さも、RPAが支持される理由のひとつです。
ヒューマンエラーの防止と品質向上
RPAは、設定されたルールに基づいて正確に処理を行うため、人的ミスの発生を最小限に抑えられます。実際に、ある医療機関では診療報酬請求書の桁ズレミスがなくなり、返戻率が大きく改善されました。業務品質が安定すると、監査対応やチェック作業の負担も軽減され、スタッフは改善活動に専念しやすくなります。
こうした積み重ねによって顧客からの信頼が高まり、ブランド価値の向上にもつながることが、RPAの大きな魅力です。
働き方改革と従業員エンゲージメント向上
繰り返し発生する単純業務をRPAに任せれば、残業や休日対応の負担が軽減され、働き手の時間にゆとりが生まれます。実際、導入企業のなかには月間残業時間が15%減ったという報告もあります。こうした余剰時間は、スキルアップや改善活動といった前向きな取り組みに振り向けることが可能です。
結果として従業員の満足度が高まり、離職率の低下や職場全体の活性化にもつながります。このように、RPAの活用は単なる業務効率化にとどまらず、持続可能な働き方の実現にも貢献します。
RPAを活用することで人材不足を補える業務の例

各部門で人手を奪う「ルーチン作業」を中心に、RPAで代替しやすい具体的な業務を紹介します。自社業務へ置き換えて考えることで導入効果をイメージしやすくなるので、ぜひ参考にしてください。
受注処理と請求書発行
RPAの活用により、受注処理と請求書発行は大幅な効率化が可能です。ECサイトでは、注文データの転記から請求書の作成・送信まで、繁忙期には1日数千件に及ぶケースもあります。
こうした業務をRPAで自動化すれば、CSVの読み込みからPDF請求書の生成、メール送信までを一括で処理可能です。実際に、月100時間かかっていた作業がわずか5分で完了した事例も見られます。ミスの削減や業務の安定化にもつながり、浮いた時間を販促活動に活かすことで、売上の向上も期待できるでしょう。
勤怠集計と給与計算
多拠点を抱える企業では、勤怠データの回収や法定控除の計算に膨大な時間と手間がかかります。RPAを導入すれば、打刻データの取得から給与ソフトへの入力まで自動で処理でき、実際に毎月3日かかっていた作業が半日で完了した例もあります。計算ミスによる差額調整も不要となり、労基署への報告も自動化が可能に。
その分、経理部門は戦略立案や分析といった中核業務に注力できるようになり、組織全体の生産性向上につながります。
在庫管理と発注
担当者が手作業で行っていた在庫集計や補充業務は、RPAによって大幅に効率化できます。POSデータの取得から安全在庫の計算、発注書の作成、ラベルの印刷まで、一連のプロセスを無人で処理することが可能です。
たとえば、ニチレイロジグループ本社では、在庫関連業務の自動化によって年間1,900時間の作業を削減し、欠品率を1%以下に抑えることに成功しています。この取り組みにより、棚卸し作業の短縮やキャッシュフローの改善も実現し、保管コストの圧縮にもつながっています。
顧客問い合わせ一次対応
RPAを活用すれば、受信メールを内容ごとに自動で仕分けし、顧客データベースを参照したうえで定型文による返信を自動化できます。実際、あるIT企業では、1日あたり約100件の問い合わせのうち約7割を自動応答に切り替え、対応時間を従来の2時間から10分に短縮。その結果、カスタマーサティスファクション(CS)スコアが10ポイント上昇し、アップセル率も改善しました。
さらに、担当者の対応負担が軽減されたことで、離職率の低下にもつながっています。
RPA導入の成功事例2選

以下の章では、医療と物流の現場で、作業時間や人手不足といった課題を根本から見直した事例を紹介します。自社での導入イメージをつかむヒントとしてご活用ください。
医療機関での活用事例|医療事務9,800時間の削減に成功
ある大学病院では、紙ベースの事務処理が業務を圧迫し、残業や人手不足が深刻化していました。そこで、院内IT部門の主導でRPAを21体導入し、勤務時間の集計・会議案内・統計資料の作成など、計68業務を自動化しました。
その結果、年間で約9,800時間の作業が削減され、返戻処理の件数も大幅に減少。離職率は約5%改善し、導入コストも半年で回収されています。事務スタッフは本来注力すべき業務に専念できるようになり、結果として患者満足度の向上にも貢献しています。
物流企業での活用事例|年間10,000時間の工数削減
ある大手物流企業では、在庫管理や発注業務の属人化により、残業の常態化と業務負担の増加が大きな課題となっていました。この状況を改善するため、受注残データの取得から安全在庫の算出まで、一連の業務をすべてRPAで自動化しました。
その結果、年間約10,000時間の作業工数を削減し、欠品率は40%以上改善。捻出された時間は配送ルートの最適化や新規案件の対応に充てられ、売上も前年比で8%増加しました。従業員満足度も15ポイント向上し、働きやすさと業務効率の両立を実現しています。度・運用・人材活用まで含めた総合的な働き方改革の実現が期待できるでしょう。約4,700時間の業務時間削減が見込まれています。
RPAを導入するなら『おじどうさん』

ここまで、RPAとBPMの連携による働き方改革のメリットについて詳しく解説してきました。働き方改革のここまで、人材不足に対応するためのRPA活用法や導入事例をご紹介してきました。今や、業務の自動化はコスト削減や生産性向上だけでなく、企業の持続的成長を支える重要な施策です。そこで注目されているのが、ブルーテック株式会社が提供する国産RPAツール『おじどうさん』です。
「おじどうさん」はプログラミング知識がなくても直感的に操作できるため、現場担当者でもすぐに業務を自動化できます。請求書の処理や勤怠管理、ファイル形式の変換など、定型的な業務を自動化することで、限られた人員でも多くの作業を効率的にこなせるようになります。また、導入前の相談やロボット作成のフォロー、運用中のサポートが手厚く無償で提供されるため、初めてRPAを導入する企業でも安心です。結果として、従業員は単純作業に追われることなく、より付加価値の高い業務に集中できるようになり、人材不足の影響を最小限に抑えることが可能になります。
まとめ

人口減少が進むなか、人材の確保だけに頼った経営には限界があります。RPAを導入することで、作業時間や人件費の削減にとどまらず、業務品質の安定化や職場環境の改善にもつながります。医療や物流など、すでに多くの現場で成果が報告されており、早期導入の利点は明らかです。
まずは負荷の大きな業務を特定し、小規模に導入して効果を確認しながら、段階的に自動化の範囲を広げていきましょう。自社の課題や体制に合ったRPAの活用は、持続可能な業務改善を力強く後押ししてくれるはずです。
【執筆者】
![]()
松岡 禄大朗
ブルーテック株式会社・デマンドジェネレーション部所属。
前職のWEB広告代理店で広告運用やアクセス解析を担当。
WEBマーケティング知識を活かして、現在はコンテンツマーケティングに携わり数多くの記事を執筆。