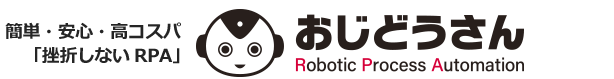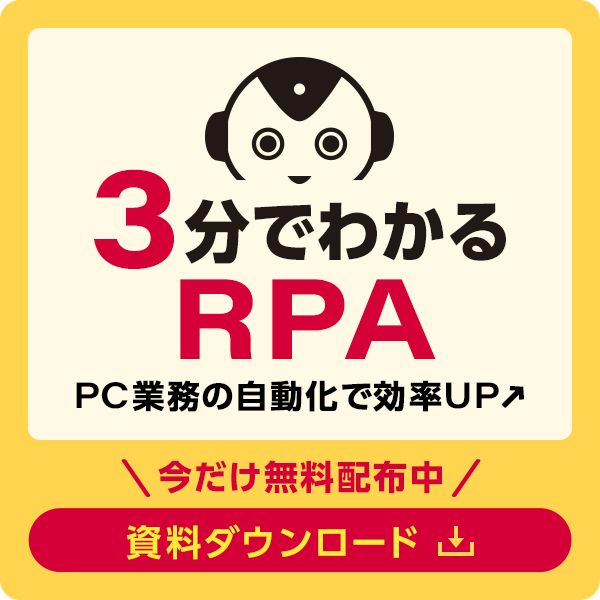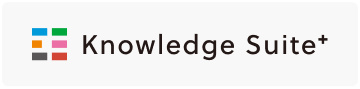RPAのクラスとは?Class1・2・3の違い、導入成功事例も紹介

RPA(Robotic Process Automation)は、自動化の成熟度に応じて「Class1(RPA)」「Class2(EPA)」「Class3(CA)」の3段階に分類されます。
この記事では、各クラスの特徴や違いを整理したうえで、代表的な活用例や導入事例、成功させるためのポイントまでを詳しく解説します。RPA導入を検討中の方は、自社にとって最適な活用ステップを描く手がかりとして、ぜひ参考にしてみてください。
【この記事の内容】
RPAの3つのクラス
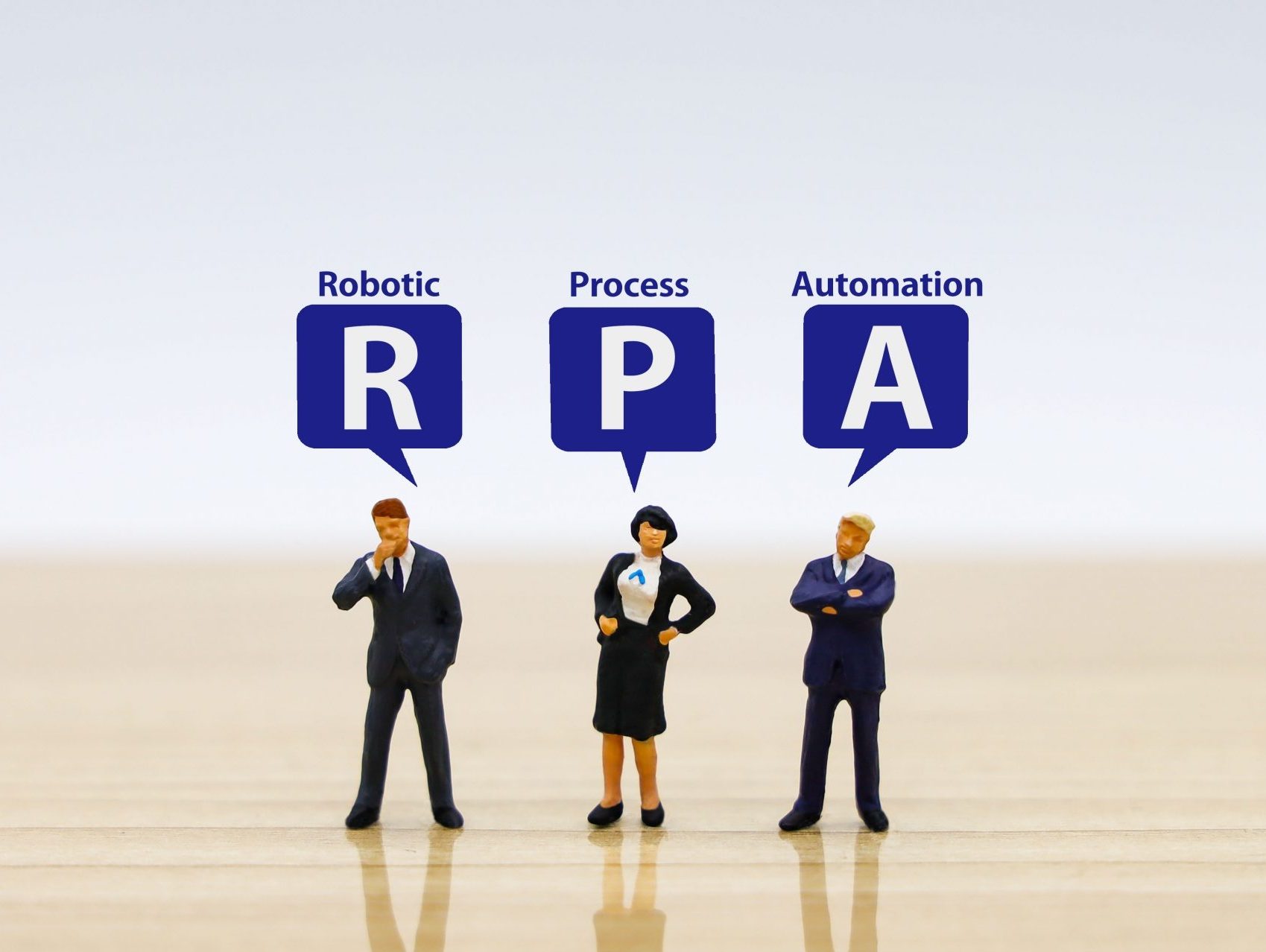
RPAは、自動化の成熟度や適用範囲に応じて、Class1(RPA)・Class2(EPA)・Class3(CA)の3段階に分類されます。それぞれのクラスは、対応できる業務の複雑さや技術レベルが異なり、企業のニーズや導入フェーズに合わせて使い分けられます。
以下、それぞれのクラスの概要と違いを表でまとめました。
| クラス | 自動化レベル | 特徴 |
| class1(RPA) | レベル1:定型業務 | ルールに沿った繰り返し作業を自動化 |
| class2(EPA) | レベル2:拡張型自動化 | RPA+AIで非定型作業にも対応 |
| class3(CA) | レベル3:高度自律化 | 自律判断や深層分析まで自動化 |
クラスが上がるにつれて、導入にかかるコストや技術的なハードルは高くなりますが、そのぶん自動化できる業務の幅が広がり、より高度な効率化が実現できます。
①【class1】 RPA(Robotic Process Automation)
クラス1(RPA) は、Robotic Process Automation(定型業務自動化)の略で、主に定型業務の自動化を目的とした技術です。AIは搭載されておらず、あらかじめ決められた手順を正確に実行する点が特徴で、判断や例外対応が求められる場面では人の関与が不可欠です。
現在、世の中で「RPAツール」と呼ばれている多くの製品はこのクラス1に該当します。導入時のコストを抑えながら、既存システムを大きく変更せずに運用できるため、業務効率化の第一歩として多くの企業が採用しています。
RPAで効率化できる業務
以下は、RPAを導入することで効率化できる、主な業務です。
データ入力・転記
- ・ExcelやCSVの内容をWebフォームやERPに自動入力
- ・複数システム(CRM・会計・在庫)間での一括転記
- ・PDFやスキャン画像からのデータ抽出(OCR連携)
- ・請求書や見積書の内容を基幹システムへ登録
定型レポート作成・配信
- ・毎日の売上・在庫レポートを自動生成して共有
- ・会議資料用の定期集計とフォーマット整形
- ・月次KPI・経営指標の自動抽出とダッシュボード更新
- ・CSV→PDF変換&関係者へのメール送信
メール送信・問い合わせ対応
- ・請求書や契約書をPDF化し自動送付
- ・定期連絡メール(検診通知など)の配信業務
- ・問い合わせメールの内容分類とテンプレート返信
- ・添付ファイル付きメールの一括送信
ファイル・フォルダ操作
- ・フォルダ構成の自動作成・整理・バックアップ
- ・古いファイルのアーカイブや自動削除
- ・ファイル名の一括変更や移動処理
- ・サーバー間の定期コピーや同期
データ検証・チェック
- ・顧客データの重複チェックとフラグ付け
- ・売上・在庫データの整合性確認
- ・入力フォーマットの自動チェックとエラー報告
- ・会計帳票・請求書の突き合わせと不整合検出()
②【class2】EPA(Enhanced Process Automation)
クラス2(EPA)は、Enhanced Process Automation(拡張型業務自動化)の略で、RPAにAI技術を組み合わせることで、より複雑で判断を要する業務も自動化できる技術です。クラス1(RPA)が定型的でルールベースの作業を自動化するのに対し、EPAではAIによる判断機能を加えることで、一部の非定型業務や例外対応にも対応できます。
たとえば、自然言語や画像・音声の解析、非構造データの理解と処理などが可能になり、業務の幅が大きく広がります。EPAは、あらかじめ定義されたルールに従うだけでなく、状況に応じて最適な処理を選択する「柔軟な自動化」が特徴です。
そのため、請求書の読み取りや問い合わせメールの分類、音声応答の自動化など、人の判断を必要とする場面でも活用されています。現在では、特に業務効率の高度化を図る大手企業を中心に導入が進みつつあります。
EPAで効率化できる業務
以下は、EPAを導入することで効率化できる、主な業務です。
請求書処理・支払い管理
- ・請求書データの自動抽出と照合
- ・支払いスケジュールの自動管理
- ・経費精算プロセスの自動化
在庫管理・発注処理
- ・在庫レベルの自動モニタリング
- ・発注トリガー条件に応じた自動発注
- ・サプライチェーン情報の統合・最適化
顧客サポート業務
- ・チャットボットによる一次対応の自動化
- ・問い合わせ内容の分類とエスカレーション
- ・FAQナレッジを活用した自動応答の生成
データ分析・レポート作成
- ・マーケティングデータの自動集計・可視化
- ・売上予測や傾向分析レポートの生成
- ・KPIや業績指標のモニタリングと通知
③【class3】CA(Cognitive Automation):高度な自律化
クラス3(CA) は、Cognitive Automation(認知自動化)の略で、AIや機械学習を活用し、高度な判断や予測が必要な業務まで自動化できる最上位のRPA技術です。RPAやEPAがルールベースの作業や限定的な判断を支援するのに対し、CAは非構造データを分析し、自律的に意思決定を下すレベルまで進化しています。
たとえば、過去のデータから傾向を読み取り、最適な行動を提案したり、業務上の異常を検知して自動で対応策を実行することも可能です。自然言語処理(NLP)・画像解析・音声認識といった高度な技術を備え、使えば使うほど学習して精度が高まるのが特徴です。企業はこれにより、専門性の高い業務や予測分析、複雑な判断を伴う業務を効率化・高度化できます。
CAで効率化できる業務
CAは高度な意思決定や予測分析が求められる業務に適しており、以下のような領域でその効果を発揮します。
顧客サポート・チャットボット
- ・自然言語処理(NLP)により、問い合わせの意図を分析し適切に自動応答
- ・FAQ対応だけでなく、複雑な質問や感情を含むやり取りにも対応
- ・顧客満足度に基づく応答改善(自己学習機能付き)
帳票・文書の自動分類と情報抽出
- ・OCR・画像認識で契約書、請求書、レシートなどから項目を自動抽出
- ・書類の自動仕分け・ラベリング・データベース登録
- ・誤認識リスクに対する信頼度評価と再学習
不正検出・リスク予測
- ・金融取引ログや業務データから異常パターンをAIが検出
- ・機械学習による継続的なルール強化
- ・リスクシナリオごとの自動アラートと対応提案
意思決定支援・予測分析
- ・売上データや在庫情報、外部要因(天候・SNSトレンド)を分析
- ・売上・需要・在庫不足の予測レポートを自動生成
- ・経営戦略や販促施策に活用できるデータを可視化
予測保全(設備保守の自動化)
- ・IoTセンサーのデータを解析し、機器の異常兆候を検知
- ・故障リスクを事前に察知し、メンテナンス時期を自動提案
- ・保守履歴や部品寿命も加味した動的スケジュール生成
クラス別のRPAの特徴まとめ

RPAのクラスは、それぞれ自動化できる業務範囲や導入コスト、技術的要件が異なります。自社の課題や運用体制に応じて最適なクラスを選ぶことが、業務効率化を成功させる第一歩です。以下に、各クラスの特徴を「対応範囲」「技術レベル」「適した業務例」などの観点から一覧表にまとめました。
違いを視覚的に把握しながら、導入検討の参考にしてください。
| 分類 | 用途 | 特徴 | 対象範囲 | 導入難易度 |
| class1(RPA) | 単純な定型作業 | ・低コスト ・スピード導入 | ・データ入力・転記 ・定時処理 | ★☆☆☆☆ |
| class2(EPA) | 半定型+非定型作業 | AI技術による適応力 | ・OCR・メール分類・画像判定 | ★★☆☆☆ |
| class3(CA) | ・高度判断・改善提案 | ・自律的学習・判断 | ・予測・異常検知・要約 | ★★★★☆ |
Class1は反復作業の自動化に特化し、ルールベースで動作します。
Class2はAIを組み合わせ、判断を含む準定型業務に対応。
Class3では学習・推論により、高度な意思決定や業務改善も可能です。
RPA技術の今後

今後、RPAは次のような展開が期待されます。
- ・統合プラットフォーム化:チャットボットやERPとの連携が一般化
- ・AIの標準搭載:OCR・NLPの進化でEPAが主流、CA導入も加速
- ・ローコード対応:非エンジニアでも自動化が可能に
- ・自己最適化機能:業務変化に対応し、継続的に効率化
- ・ガバナンス強化:セキュリティ・監査対応を備えたRPAが主流に
総務省や各RPAベンダーも、こうした次世代技術を普及させるための調査や研究を強化し、クラス2以上への移行支援が進んでいます。
RPAを導入する3つのメリット

多くの企業がRPAの導入によって成果を上げており、なかでも注目されるのが次の3つのメリットです。
- ・コスト削減
- ・業務品質向上
- ・従業員の生産性向上
ここからは、RPA導入によって得られる具体的な効果や、業務改善を加速させる戦略的な利点について詳しく解説していきます。
コスト削減|単純作業の自動化で人件費と隠れコストを同時に削減
RPAを導入する最大のメリットのひとつがコスト削減です。とくにClass1では、人が何時間もかけていた単純作業を月に50〜300時間以上削減できたというケースも少なくありません。
また、RPAはヒューマンエラーをなくすため、修正対応や顧客への再送といった「見えにくいコスト」も削減可能です。初期投資が比較的少ないこともあり、半年以内にROI(投資対効果)を回収できた企業も多数あります。
業務品質の向上|エラー防止と判断の標準化で再処理やクレームを削減
RPAを導入すると、人による入力ミスや手順ミスといったヒューマンエラーをなくすことが可能です。さらに、Class2やClass3ではOCRやAIを活用して、請求書の読み取りやメールの対応など「判断を伴う作業」も自動で処理できるようになります。その結果、クレームや再処理が減り、業務の信頼性と顧客満足度の向上につながります。
従業員の生産性向上|単純作業から解放し、組織の力を引き出す
RPAを活用することで社員は単純作業から解放され、企画・分析・顧客対応といった、より創造的で戦略的な業務に時間を使えるようになります。Class1でルーチン業務を削減し、Class2・Class3ではAIの判断補助により、複雑な意思決定の支援まで実現可能です。
結果として、エンゲージメント向上や離職率の改善も期待できるでしょう。
class1のRPAから導入するべき理由

class1のRPAから導入すべき最大の理由は「低リスク&高効果」であるからです。導入コスト・技術障壁ともに比較的低く、成果もすぐに実感できます。また、成功経験を積むことで社内のRPAへの理解が進み、その後のclass2・3へのステップアップもスムーズになるでしょう。
さらに、class1で得られたログや運用データは、次フェーズのEPA・CA導入時のAIモデル構築時に貴重な学習材料となります。そのため最初にclass1を導入することで、継続的な自動化戦略が描きやすくなるのです。
RPAの活用事例

RPAは、業種や企業規模を問わず幅広く導入されており、多くの現場で目に見える成果を上げています。ここからは、各業界での具体的な活用事例を通じて、RPAの実力と再現性の高さをご紹介します。
金融業界|EPAで請求処理を効率化
ある銀行では、Class2に該当するRPAとOCR技術を組み合わせ、請求書の読み取りから仕分けまでを一貫して自動化しました。従来は手作業で行っていた事務処理が不要となり、月間で約200時間の作業を削減。さらに、読み取り精度の向上によりエラー率も80%減少しました。
業務の正確性が高まったことで、担当者は財務分析や顧客対応といった、より付加価値の高い業務に注力できるようになっています。
製造業|RPAで月次レポート作成を自動化
国内のある製造企業では、Class1に該当するルールベース型のRPAを導入し、売上データや在庫情報の転記、月次レポート作成業務を自動化しました。これにより3拠点で分担していた作業のうち、合計150時間分が削減され、各拠点の担当者は分析業務や改善活動に時間を振り分けられるようになりました。作業の標準化と属人化の排除にもつながっています。
物流・運輸業|画像解析で検品ミスを激減
ある物流企業では、Class2相当のRPAに画像認識AIを連携させ、出荷前の荷姿検品を自動化しました。導入前は人手による目視確認が中心で、検品ミスや再梱包コストが課題となっていましたが、AIの導入により検品精度が飛躍的に向上。
結果として検品ミスが60%削減され、作業の正確性とスピードが大きく改善されました。現場スタッフは異常検知後の対応に集中できるようになり、現場全体の生産性向上にも寄与しています。
士業・公的機関|公文書処理の自動化で業務時間を削減
ある行政機関では、Class1のRPAを活用して、e-Govからの公文書のダウンロードや整理作業を自動化しました。これまで担当者が手作業で取得・振り分けしていた処理をRPAが24時間稼働で代行し、月50時間分の作業時間を削減。定型業務を自動化することで、限られた人員でも他の重要業務に余力を持って対応できる体制が整いました。
RPAを導入するなら『おじどうさん』

ここまで、RPAの基礎からClass1〜3の違い、導入メリットをご紹介してきました。こうした効果を最大限に引き出すには、自社の業務にフィットするツールの選定が欠かせません。そこで注目されているのが、ブルーテック株式会社が提供する国産RPAサービス『おじどうさん』です。
『おじどうさん』はClass1から段階的に導入でき、蓄積した実行データを活用しながら、Class2・Class3への移行もスムーズに行えます。業界別のテンプレートやAIモデルが標準搭載されており、導入スピードとコストパフォーマンスの両面で優れている点も魅力です。
さらに、導入後はログ解析や改善提案を通じて、継続的な業務最適化も支援します。RPAの導入を検討する企業はもちろん、将来的にClass2・Class3への拡張を見据えている企業にとっても、『おじどうさん』は有力な選択肢となるでしょう。
まとめ

業務効率化を継続的に進めたい企業にとって、RPAは大きな推進力となります。なかでも、class1は導入しやすく、早期に成果を出しやすい点が特長です。一方で、さらなる高度化を目指すなら、class2・class3への拡張も視野に入れるべきでしょう。自社に合ったクラスを見極め、段階的に活用することで、無理なく着実に効果を高められます。
まずは小さな成功体験を積みながら、全社的な業務改革へとつなげていく姿勢が、RPA活用を成功に導くカギとなります。
【執筆者】
![]()
松岡 禄大朗
ブルーテック株式会社・デマンドジェネレーション部所属。
前職のWEB広告代理店で広告運用やアクセス解析を担当。
WEBマーケティング知識を活かして、現在はコンテンツマーケティングに携わり数多くの記事を執筆。