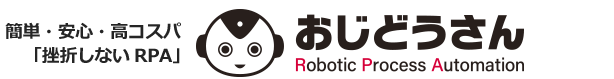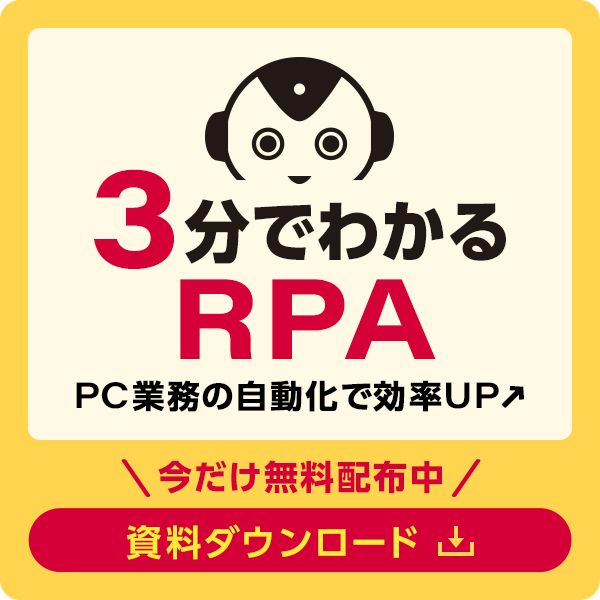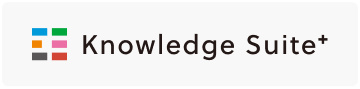RPAとBPMを組み合わせるメリットは?働き方改革を実現するためにできること

働き方改革を実現するうえで、単なる人員削減や残業抑制だけでは、持続的な成果にはつながりません。今、企業に求められているのは、業務品質を維持しながらも生産性を高め、従業員が柔軟に働ける仕組みを構築することです。
その手段として注目されているのが、定型業務を自動化するRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)と、業務プロセスを可視化・改善するBPM(ビジネスプロセスマネジメント)の導入です。両者はそれぞれ独立しても効果を発揮しますが、組み合わせることで「局所最適」と「全体最適」の両立が可能となり、より高い業務改革効果が期待できます。
そこで本記事では、RPAとBPMの違いや役割、併用による具体的なメリット、そして働き方改革を加速させるための活用ポイントを解説します。現場業務の見直しやDX推進を検討されているご担当者様は、ぜひご一読ください。
働き方改革とRPA・BPM

働き方改革の主な目的は、長時間労働の是正、ワークライフバランスの向上、そして生産性の改善にあります。2019年以降の法改正により、時間外労働の上限規制や柔軟な働き方の推進が企業に義務付けられたことで、現場レベルでも具体的な対応が求められるようになりました。こうした背景のなかで、業務の見直しと効率化を両立させる手段として注目されているのが、RPAとBPMです。
RPAは定型的な反復作業を自動化し、BPMは業務プロセス全体を可視化・標準化して継続的な改善を促すことで、人手不足の緩和・残業削減・生産性向上に貢献する基盤となります。両者を組み合わせて活用することで、企業は生産性と柔軟性の両立を図りながら、働き方改革の持続的な成功を実現できるのです。
BPMとは

BPMとは、業務プロセスを一元的に管理し、継続的な改善を実現するための手法、またはそれに役立つITツールのことを指します。BPMは部門や組織を横断してプロセス全体を可視化・分析・最適化する取り組みであり、その実行には「モデリング」「分析」「実行」「監視」といったサイクルを継続的に回していくことが基本となります。
たとえば、複数部門にまたがる手続きや承認フローの中にある非効率や無駄を洗い出し、標準化や効率化につなげることが可能です。また、BPMは環境変化や組織改編にも柔軟に対応できるという特長があり、単なる定型化にとどまらず、変化に応じて業務プロセスを進化させ続けることができます。
RPAとBPMの違い
RPAは、パソコン上の操作を自動で再現することで、決まった手順の作業を代行する技術です。システム間のデータのコピーや入力作業など、ルールが決まっていて繰り返し行うような業務に向いています。
一方BPMは、業務全体の流れを見える化し、ムダを減らして効率化するための仕組みです。複数の部署にまたがる手続きや承認フローを見直し、PDCAサイクルを回すことで、会社全体の業務を継続的に改善していくことができます。
このように、RPAは1つ1つの作業(点)を効率化するのに強く、BPMは業務の流れ全体(線)を整えるのが得意です。BPMで整えた業務フローの中にRPAを取り入れれば、定型作業は自動化され、全体の効率もアップします。ただし、RPAだけでは流れ全体の見直しや変化への対応が難しいため、本格的な業務改善にはBPMとの組み合わせが重要です。
RPAとBPMを組み合わせるメリット

この章では、RPAとBPMを組み合わせることで得られる具体的なメリットについて解説します。単体でも効果を発揮する両者ですが、連携することでより高い業務改革効果が期待できます。
主なメリットは、以下の3点です。
- ・自動化効果の最大化
- ・運用の安定性向上とエラーリスクの抑制
- ・変化に強い業務改善体制の構築
それでは、それぞれのメリットについて順に見ていきましょう。
メリット①:自動化効果の最大化
BPMで業務プロセス全体を可視化することで、どこがボトルネックで、どのタスクを自動化すれば最も効果的か(ROIが高いか)をデータに基づいて特定できます。やみくもに部分的な作業をRPA化するのではなく、事業インパクトの大きい箇所へ戦略的にRPAを導入できるため、自動化による効果を最大化できます。森(全体プロセス)を見てから木(個別タスク)を切る、という全体最適の視点が得られるのが最大の利点です。
メリット②: 業務品質の安定化とガバナンス強化
BPMによって標準化された業務手順をRPAが正確に実行するため、担当者による手順のバラつきやヒューマンエラーがなくなり、業務品質が安定します。また、どの業務をどのロボットが担当しているかがBPM上で明確に管理されるため、ガバナンスが強化され、管理者の目の届かないところでロボットが作られてしまう「野良ロボット」問題の防止にも繋がります。これにより、統制の取れた安全な自動化が実現します。
メリット③:RPAの安定性向上
BPMによって、業務プロセスを可視化させることで、エラーが発生したときの対応手順や、人による確認のポイントを事前に設計しやすくなります。処理中に異常なデータが検出された場合でも、自動的に人の判断を促すルートへ切り替えることで、RPAだけでは対応が難しい例外処理にも柔軟に対処できます。
さらに、リアルタイムのログ収集や監視機能を導入すれば、異常を検知した瞬間にアラートを出し、即座に人の対応へとつなげる体制も構築可能です。このように、業務プロセスの可視化とエラーハンドリングを連動させることで、運用全体の安定性が一層高まることが期待できるでしょう。
RPAとBPMが働き方改革の実現につながる

RPAとBPMの連携は、働き方改革を実現するうえで有効な手段です。RPAは24時間稼働が可能で、夜間や休日の定型業務を自動化することで、残業時間の削減や人件費の抑制に効果があります。
一方でBPMは、業務全体の流れを可視化することで属人化の解消や作業手順の標準化を促し、在宅勤務やフレックスタイム制度といった働き方にも柔軟に対応できる体制づくりを支えます。このように、RPAによる業務の自動化とBPMによるプロセス改善を組み合わせることで、制度・運用・人材活用まで含めた総合的な働き方改革の実現が期待できるでしょう。約4,700時間の業務時間削減が見込まれています。
RPAを導入するなら『おじどうさん』

ここまで、RPAとBPMの連携による働き方改革のメリットについて詳しく解説してきました。働き方改革の取り組みを実現するには、自社の業務にフィットしたRPAツールの選定が欠かせません。そこで注目したいのが、ブルーテック株式会社が提供するRPAツール『おじどうさん』です。
『おじどうさん』は、直感的なパネル操作中心のUIでプログラミング知識が不要で、非IT人材でもロボットを作成できる点が特長です。また、導入支援やアフターサポートまで無償提供される仕組みにより、スモールスタートでも定着率が高い(98%継続)という実績があります。
BPMと連携させることで、自動化だけでなくプロセス改善も一体的に進められる構成になっており、現場が主体的に改善サイクルを回せる環境づくりにも寄与します。業務効率化から柔軟な働き方までを視野に入れる働き方改革を検討されているなら、『おじどうさん』は有力な選択肢となるでしょう。
おじどうさんの詳細はこちら をご確認ください
まとめ

RPAとBPMの連携は、働き方改革を支える強力なアプローチです。RPAは定型業務の効率化や人件費削減に貢献し、BPMは業務プロセス全体の可視化と継続的な改善を支援します。
この2つを組み合わせることで、業務の最適化や余剰時間の創出、柔軟な働き方の実現につながります。導入に際しては、「おじどうさん」をはじめとするRPAツールを活用することで、既存業務へのスムーズな展開と安定的な運用が見込めるでしょう。業務プロセスを見直しながら、定型作業を効率的に自動化する仕組みとして、RPAとBPMの連携導入を検討されてみてはいかがでしょうか。
【執筆者】
![]()
松岡 禄大朗
ブルーテック株式会社・デマンドジェネレーション部所属。
前職のWEB広告代理店で広告運用やアクセス解析を担当。
WEBマーケティング知識を活かして、現在はコンテンツマーケティングに携わり数多くの記事を執筆。