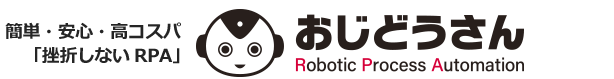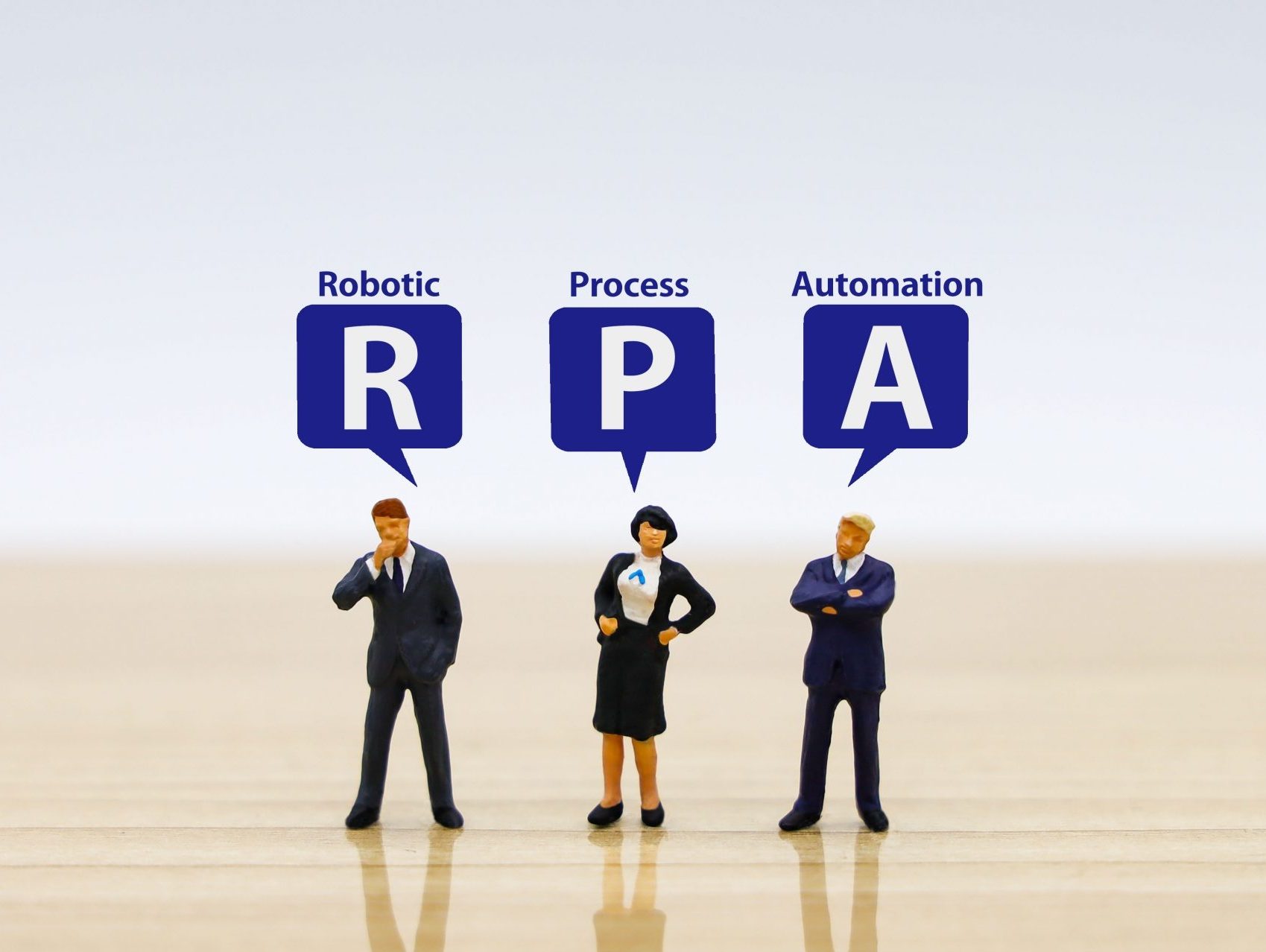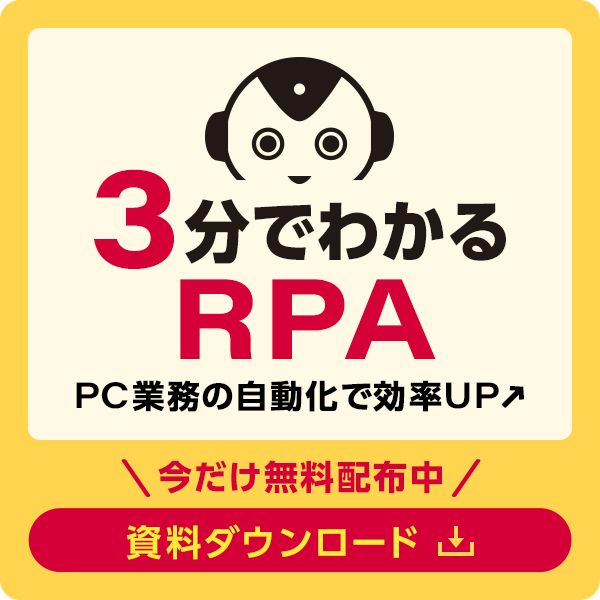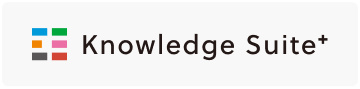RPAツールの選び方は?選ぶ前に確認しておきたいことやポイント、導入手順を紹介

業務効率化を目指す企業にとって、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)の導入は有効な手段です。RPAとは、業務の自動化や生産性向上を目的に、日本だけでなく世界中で導入が進められている技術のことです。
しかし、市場には多くのRPAツールが存在し、自社に最適なものを見極めるのは簡単ではありません。そこで本記事では、RPAの基本からツール選定のポイント、そして失敗した場合の対応策までをわかりやすく解説します。
さらに、初めてRPAを導入する企業におすすめのツールも紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
【この記事の内容】
RPA・RPAツールとは
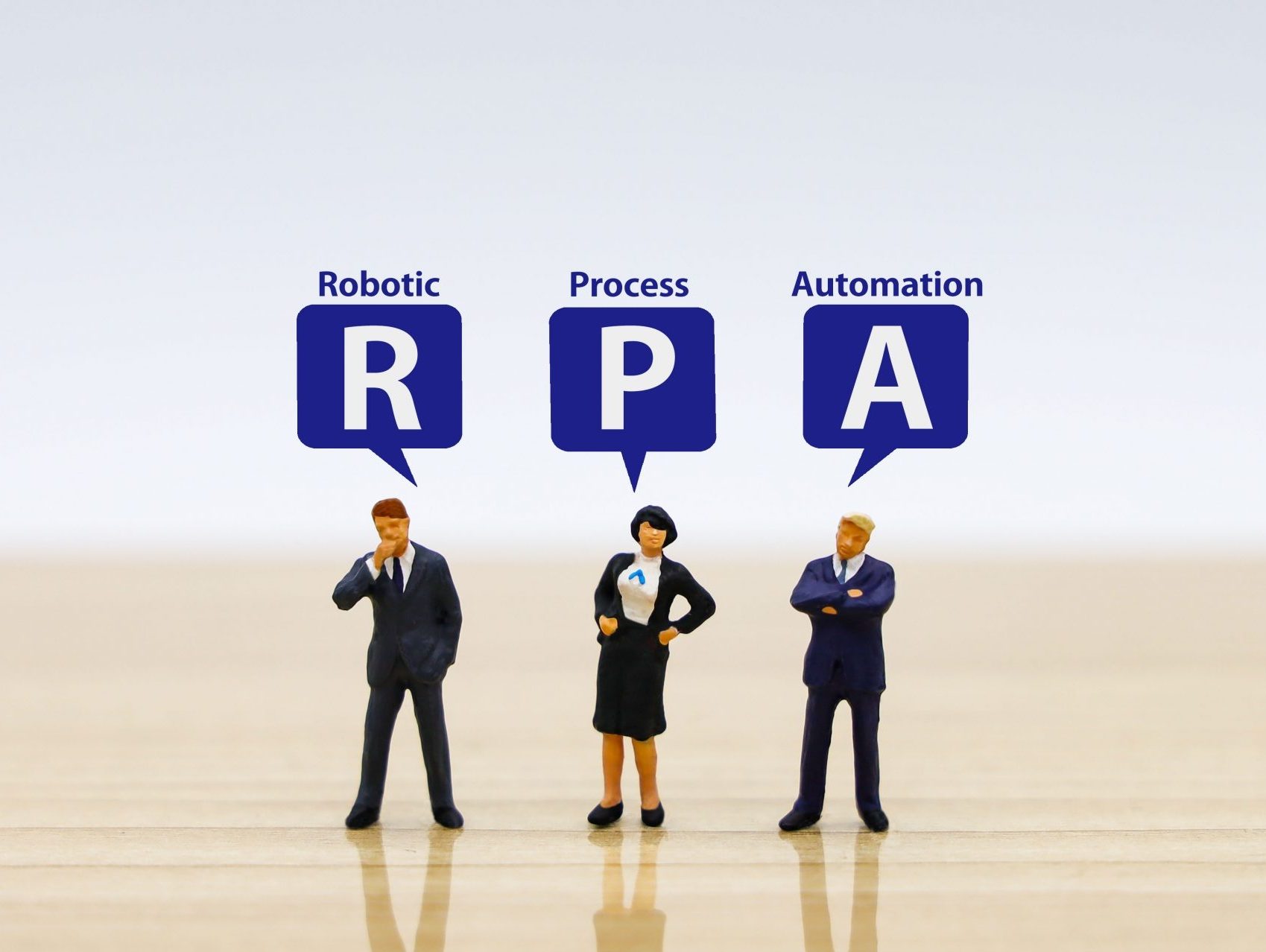
RPAとは、定型的な業務プロセスをソフトウェアロボットが自動化する技術です。RPAツールを導入することで、データ入力・集計・メール送信などのルーチン業務を効率化でき、人的ミスの削減や生産性の向上が実現します。
以下に、RPAツールを活用して、実際に自動化できる業務内容を具体的に紹介します。
RPAを導入することで実現できる業務効率化の例
RPAツールを導入することで、以下のような業務の自動化が可能になります。
| データ入力/転記 | Excelやシステムへの入力を自動化し、ミスと作業時間を削減 |
| メール送信 | 定型文や添付ファイルの送信を自動化し、対応を効率化 |
| レポート作成 | 集計やグラフ作成を自動で行い、資料作成の手間を削減 |
| システム間のデータ連携 | 異なるツール間のデータ移行・連携を自動化し、業務を円滑化 |
これらの自動化により、従業員の作業負担が減り、より重要な業務に集中できるようになります。特にバックオフィス業務や定型作業が多い部門では、RPAの導入効果が大きく期待できるでしょう。
RPAツールを選ぶ前に確認しておきたいこと

RPAツールは、ただ導入すれば効果が出るものではありません。導入前にいくつかのポイントを押さえておくことで、ツール選定の成功率が大きく高まります。事前に確認しておくべきポイントを以下にまとめましたので、最適なツール選びの参考にしてください。
自動化対象業務の明確化
RPAは万能ではなく、すべての業務に適しているわけではありません。特に自動化に向いているのは、ルールが明確で、例外処理が少なく、繰り返し頻度の高い定型作業です。
たとえば、受発注処理・請求書発行・データ転記・メール配信・レポート作成などが該当します。導入にあたっては、まず自社の業務全体を洗い出し、各業務の作業内容・所要時間・実行頻度を可視化しましょう。その上で、「手作業が多い/人為的ミスが起きやすい/処理に時間がかかる」といった課題のある業務を優先的に選定すると効果が出やすくなります。
また、1つの業務に複数部門が関わっている場合は、全体のフロー設計や連携体制の見直しも重要です。このような事前整理を行うことで、RPAの導入効果を最大化し、投資対効果の高い自動化を実現できます。
現場のITリテラシーの把握
RPAツールは、導入するだけでは効果を発揮しません。実際に操作する現場の担当者がツールを使いこなせるかどうかが、導入成功のカギを握ります。
多くのRPAツールは直感的なUIを備えていますが、それでも一定のITリテラシーやロジックの理解力は求められます。導入前に、対象部門の担当者がどの程度PC操作やシステムに慣れているかを確認し、必要に応じて教育・研修・マニュアルの整備などを計画的に用意することが大切です。
また、現場が主体的にRPAを活用できる環境を整えるには、ツールそのものの操作性や難易度を見極める視点も欠かせません。たとえば、ドラッグ&ドロップ操作で自動化フローが作れるような、ノーコード・ローコード型のRPAツールであれば、ITスキルに不安がある現場でも定着しやすいでしょう。現場のリテラシーに合ったツール選定と支援体制の構築が、導入後の運用成功に直結します。
セキュリティとガバナンスの確認
RPAツールを導入する際には、業務効率だけでなくセキュリティやガバナンスの観点も欠かせません。自動化されたプロセスが誰によって、どのように実行されているかが把握できる状態を保つことが、組織としてのリスク管理につながります。
まず確認すべきは、アクセス権限の設定機能です。ユーザーごとに実行可能な処理範囲を細かく設定できるか、機密情報へのアクセスが制限されているかをチェックしましょう。
また、操作ログの自動取得や監査対応機能があるかどうかも重要です。ログが記録・可視化されていれば、万が一のトラブル時にも対応が容易になり、内部統制やコンプライアンスの強化にも寄与します。特に金融・医療・公共機関など、高いセキュリティ基準が求められる業界では、この観点が導入判断の大きなポイントとなります。
RPAツールの上手な選び方

RPAツールを選ぶ際には、機能や価格だけでなく、自社の業務や体制に合ったものを選定することが重要です。主要ツールの機能やコスト、操作性などを比較表にまとめておくと、複数製品を客観的に比較しやすくなります。
ここからは、RPAツールを選ぶうえで押さえておきたいポイントについて、具体的に見ていきましょう。
業務内容に合った機能で選ぶ
RPAツールは「自社の業務に合ったもの」を選びましょう。どれだけ高機能なツールでも、業務内容にフィットしなければ効果は出ません。たとえば、Excel入力や帳票処理が中心なら、Office連携に強いツールが有効です。
一方で、Web上の定型作業が多い職場では、ブラウザ操作に特化したRPAが適しています。また、システム間のデータ連携が必要な場合は、API対応や複数アプリ間の統合がしやすいツールが求められます。導入前に、業務の流れや対象作業を洗い出し、それに対応できる機能を持つRPAかどうかを見極めることが、失敗しない選定のコツです。
操作のしやすさで選ぶ
RPAツールは、操作が簡単であるほど現場で活用されやすくなります。特に、プログラミングの知識がなくても扱える直感的なUIを備えたツールは、非エンジニアの担当者でも自走的に運用できる点が大きな魅力です。現場でRPAを活用するには、都度IT部門に頼るのではなく、現場自身がシナリオの作成や調整を行えることが理想です。
そのため、ツール選定時にはフローデザインのしやすさや操作ステップの視認性、シナリオ編集の自由度などをしっかりチェックしておきましょう。また、操作性が高いツールはトレーニングコストも低く済むため、導入後の定着や改善スピードにもよい影響を与えます。
導入後のサポート体制で選ぶ
RPAツールは「導入して終わり」ではなく、導入後のサポート体制が非常に重要です。運用初期には、エラー対応や現場からの質問が多発するケースもあるため、ベンダーのサポート力がツール活用の成否を左右します。
たとえば、導入支援が手厚く、教育コンテンツや初期トレーニングが充実しているベンダーであれば、現場への定着もスムーズに進みます。また、トラブル発生時のレスポンス速度や、FAQ・マニュアルの充実度、専任サポート担当の有無なども確認すべきポイントです。特に、初めてRPAを導入する企業にとっては「困ったときにすぐ相談できる環境」が、大きな安心材料になるでしょう。
導入後もスケールしやすいRPAを選ぶ
RPAは、将来的な拡張や全社展開を見据えて選ぶことが大切です。初期は一部業務でも、効果が出れば他部門へ広がる可能性が高いため、柔軟に拡張できるツールかどうかを見極めることは重要です。
たとえば、API連携や外部データベースとの接続、クラウド対応など、他システムとの連携機能が充実しているかは必ず確認しましょう。「今だけでなく、成長後も使えるか」という視点でツールを見極めることが、RPA導入を成功に導くポイントになります。
導入・運用コストで選ぶ
RPAツールは価格だけでなく、導入から運用までの総コストを見極めることが重要です。ツールによって、初期費用・月額料金・保守費用・サポート料金などが異なり、表面上の価格だけで判断すると後でコストがかさむこともあります。ライセンス形態にも注意が必要です。たとえば、月額課金のサブスクリプション型は初期導入しやすい一方、長期利用では割高になる可能性もあります。
反対に、買い切り型は導入コストこそ高めですが、長く使うほどコスト効率は高まります。コストだけにとらわれず、必要な機能と予算のバランスが取れたツールを選定することが、無理のない運用を継続するためのポイントになるでしょう。
導入実績と信頼性で選ぶ
RPAツールは、導入実績が豊富で信頼性の高い製品を選ぶようにしましょう。導入企業の数や業種・規模といった実績は、ツールの汎用性や安定性を測るうえで有効な指標となります。
特に、自社と同じ業種や規模感の企業での活用事例があるかどうかは、導入後の適合性を判断する重要なポイントです。公式サイトに掲載されている導入事例やユーザーインタビュー、レビューサイトの評価や口コミなども積極的にチェックしておきましょう。
セキュリティと管理機能で選ぶ
RPAツールを導入するうえで、セキュリティや管理機能の充実度は見逃せない重要ポイントです。業務データを取り扱う以上、不正アクセスや情報漏洩のリスクを最小限に抑えるため、アクセス権限の設定、操作ログの記録、権限管理の仕組みが整っているかを必ず確認しましょう。クラウド型のRPAを選ぶ場合は、通信の暗号化やデータ保護体制も併せてチェックが必要です。
また、複数部門での運用や全社展開を見据えるなら、ユーザー管理や利用状況の一元管理が可能な統合管理機能の有無が、運用効率を左右するカギになります。
RPAツールの選び方で失敗した場合の対処法

RPAツールの選定に失敗したとしても、適切に対応すればリカバリーは十分可能です。以下からは、RPA導入での「選定ミス」に気づいたときに取るべき3つの対処法について、具体的に解説します。
現状の課題の洗い出し
RPAツール選定に失敗したと感じた場合、まず行うべきは「現状の課題を正確に把握すること」です。「使い勝手が悪い」「自動化対象と合っていない」「運用が属人化している」など、どこに問題があるのかを明確にすることで、的確な対処が可能になります。そのためには、現場の担当者や運用チームからのヒアリングを実施し、実際にどの部分で困っているのかを可視化することが重要です。
また、当初の導入目的(作業時間の削減、人的ミスの防止など)と、現在の成果が乖離していないかも確認しましょう。これらの洗い出しを丁寧に行うことで、改善すべきポイントが明確になり、次のステップにつなげやすくなります。
ベンダーとの再協議
RPAツールに課題を感じたときは、まず導入元のベンダーに相談して状況を整理しましょう。現場でのつまずきや問題点を共有することで、原因の特定や具体的な改善策を一緒に検討できます。
また、追加トレーニングやマニュアルの提供など、サポート体制の見直しによって現場での理解度や定着率が改善することも期待できます。ベンダーとの対話を通じて、ツールではなく使い方に問題があったことに気づくケースも少なくありません。すぐに他のツールへ切り替えるのではなく、まずはベンダーと連携し、改善の余地があるかを見極めることが結果的に負担を抑える近道になるでしょう。
他ツールへの乗り換え検討
現在のRPAツールで課題解決が難しい場合は、他ツールへの乗り換えも選択肢のひとつです。
その際は、これまでの運用で見えた課題や改善点を整理し、「なぜうまくいかなかったのか」「どこにギャップがあったのか」を明確にしましょう。「操作が複雑だった」「業務内容と機能が合っていなかった」といった振り返りをもとに、UIの使いやすさや業務との相性、サポート体制などを重視して比較検討するとよいでしょう。
さらに、スモールスタートが可能なツールや、既存システムとの連携がしやすい製品を選ぶことで、再導入のハードルもぐっと下がります。これまでの失敗を活かせば、次のツール選びがより確実な一歩につながるはずです。
RPAツール導入の流れ

RPAツールの選定が終わったら、いよいよ導入フェーズに進みます。以下の7つのステップを踏むことで、スムーズかつ効果的にRPAを導入できるでしょう。
ステップ①:現状業務の棚卸と可視化
まずやるべきことは、自社の業務をすべて洗い出して、どんな作業があるのかを整理することです。この時点では「RPAでできるかどうか」は気にせず、とにかく現場で行われている業務をリストアップすることが大切です。
たとえば次のような情報をまとめておくと、あとで役立ちます。
- ・作業内容と手順
- ・実施頻度(毎日?毎週?)
- ・1回あたりの所要時間
- ・担当者や関係部門
- ・使用するツール(Excelや専用システムなど)
現場の人に話を聞きながら、「どんな業務が、どのくらいあるのか」を見える化しておきましょう。
ステップ②:自動化する業務を選ぶ
業務を整理できたら、次はその中から「RPAに向いている業務」を選びます。
RPAにおすすめなのは、次のような作業です。
- ・作業手順が毎回同じ
- ・判断をほとんど必要としない
- ・件数が多く、時間がかかる
- ・ミスが起きやすい単純作業
特に導入初期は、「簡単に成果が出やすい業務」から始めるのがポイントです。成功しやすい業務から着手することで、現場にも受け入れられやすくなります。
ステップ③:ツール選定と導入計画の策定
次に、選定したRPAツールを実際に導入するための計画を立てます。まずは、どの業務を対象にするのか、どの部門でスタートするのか、誰が運用・管理するのかといった導入範囲や体制を明確にします。導入スケジュールや教育計画もこの時点で整理しておき、関係部署とすりあわせておきましょう。
また、いきなり全社導入せず、小規模なPoC(概念実証)を行うのがおすすめです。これは、実際の業務にRPAを試験的に適用して、ツールの使いやすさ・効果・問題点を事前に検証するプロセスです。PoCを通じて「どんな業務に合うか」「どんなトラブルが起こりうるか」を把握しておけば、本格導入後のトラブルや無駄なコストを回避しやすくなります。
ステップ④:シナリオの設計・作成
このステップでは、RPAが実行する操作手順、いわゆる「シナリオ」を設計していきます。シナリオとは、人間が行っている業務の流れを機械に置き換えるための設計図のようなものです。
たとえば、特定のファイルを開く→データを抽出→別のシステムに入力するといった一連の処理を、順を追ってRPAに覚えさせるイメージです。ファイルの未取得や通信エラーなど、例外パターンへの対応も忘れずに組み込みましょう。将来的な修正に備え、シンプルでわかりやすい構成を意識することも大切です。
ステップ⑤:テスト運用とフィードバック
テスト運用は、RPAが現場で期待通りに機能するかを事前に確認する重要な工程です。この段階では、あえて実業務に近い環境やデータを使い、処理が正確に行われるか、想定外の例外が発生しないかをチェックします。たとえば「特定の形式のデータだけ処理が止まる」「特定時間帯にエラーが出る」といった問題が明らかになることもあります。
また、実際に運用する担当者から操作性や結果の確認方法に関する意見を集め、それを反映させることで、現場で使いやすいRPAに仕上がるでしょう。テスト段階での細かなチューニングこそが、本番導入の成功を左右するといっても過言ではありません。
ステップ⑥:本番導入と業務定着
テスト運用で問題が解消されたら、いよいよ本番導入です。このフェーズでは、シナリオを業務に組み込んで実運用を開始しますが、導入直後は必ず監視体制を敷き、ロボットの処理結果や予期せぬエラーをリアルタイムで把握できるようにしておくことが重要です。突発的なトラブルに備えた対応フローやエスカレーション体制も整備しておきましょう。
また、業務定着を図るためには、現場メンバーがRPAの仕組みを理解し、主体的に活用・改善できる状態を目指すことが求められます。そのためには、運用マニュアルの整備やFAQの共有、継続的なレクチャーの実施が欠かせません。「ロボットが動く仕組みを理解していない」「特定の人しか直せない」という属人化を防ぐためにも、教育と情報共有を並行して進めることがポイントです。
ステップ⑦:運用・保守と改善の継続
RPAは一度導入すれば終わりでなく、業務変化や環境更新に応じたメンテナンスが必要です。たとえば、業務フローの見直しやシステムのアップデートにより、シナリオが想定通りに動作しなくなるケースも少なくありません。これらのケースに柔軟に対応するためには、定期的なシナリオの点検・更新と、動作検証を行う体制が不可欠です。
また、運用ログを活用してエラーの傾向や停止の原因を分析することで、より安定した運用につなげられます。なお、RPAの保守体制は、自社内で対応する方法と外部ベンダーに委託する方法のいずれも選択肢として考えられます。自社のリソースや業務規模に応じて、最適な体制を整えることが、継続的な活用のカギとなるでしょう。
RPAを導入するなら『おじどうさん』

ここまで、RPAツールの選び方や導入ステップについてご紹介してきましたが、「導入しても使いこなせるか不安…」と感じている企業様も多いのではないでしょうか。そんなときにおすすめなのが、弊社の業務自動化サービス『おじどうさん』です。
『おじどうさん』は、専門知識がなくても使いやすい直感的なUIと、幅広い業種・業務に対応できる柔軟なシナリオ設計が特長です。導入前の業務整理から、現場への定着支援、導入後のサポートまで一貫して対応可能な体制も評価されています。
また、スモールスタートに適したプラン構成になっており、初めてRPAに取り組む企業でも、安心して検討できるツールのひとつといえるでしょう。RPA選定に悩んでいる企業様は、まずは情報収集の一環として、こうしたツールの特徴を比較してみるのもおすすめです。
おじどうさんの詳細はこちら をご確認ください
まとめ

本記事では、RPAツールの選び方から導入ステップ、そして運用・改善のポイントまでを解説してきました。
RPA導入を成功させるには、ツールの機能や費用だけでなく、自社の業務にフィットするかどうか、そして導入後のサポート体制まで含めた総合的な判断が重要です。あらかじめ導入プロセスを整理し、適切なステップを踏むことで、業務効率化や生産性の向上につなげられます。
導入後も定期的な見直しと改善を続け、RPAの効果を長期的に最大化していきましょう。
【執筆者】
![]()
松岡 禄大朗
ブルーテック株式会社・デマンドジェネレーション部所属。
前職のWEB広告代理店で広告運用やアクセス解析を担当。
WEBマーケティング知識を活かして、現在はコンテンツマーケティングに携わり数多くの記事を執筆。